【演劇・アート】舞台美術 3人展 ― 2010/09/22

本来は開催期間中に紹介すべきだったのだろうが、今回は終了後のレビューになってしまった(反省)。9月9~21日まで新宿・紀ノ國屋画廊で行われていた「3人展」で、ワタシが足を運んだのは19日。
舞台美術家である堀尾幸男、島次郎、土屋茂昭、が、4作ずつの模型を展示するほか、数多くの作品をプロジェクターで紹介する。
まず会場に足を踏み入れて、目を奪われるのは堀尾の「欲望という名の電車」。場末の酒場とねぐら、ベット…「汚し」と空間を生かした設計でテネシー・ウィリアムズが描いた「世界」を見事に再現。「模型」ながら、時空を超えてその「世界」へと誘う。さらに「彦馬がゆく!」(上記写真)の精巧さと奥行きある舞台空間に驚かされる。そして、「さまよえるオランダ人」「ザ・キャラクター」と続く。
島は、「ヘンリー六世」「橋を渡ったら泣け」で、思いっきり舞台空間を拡げ、「ニュルンベルク裁判」ではアートに、「焼肉ドラゴン」ではあの臭い立つ長屋へ。
土屋は、「鹿鳴館」「エビータ」「クラウディア」でゴージャスに、「思い出を売る男」では陰影にとんだノスタルジックな世界を構築。
ワタシ的には、緻密職人の堀尾、空間派の島、ライティングの魔術師・土屋という印象を持ったが、まったくの私見で、3者ともいずれも技量も素晴らしい。スペースは小さくとも、充実した展示イベントであったと思う。
これらの模型展示を見て思い出されたのが、上々颱風が行っていた野外コンサート「上々颱風祭り」の舞台模型。実物の舞台も素晴らしかったが、維新派の松本雄吉氏によるその舞台模型も本当に、見とれてしまったものだ。
映画美術監督の種田陽平氏も自著で悔しげに語っているがが、こうした舞台美術も公演が終了してしまえば、どんなに素晴らしいセットでも解体されてしまう。そうした意味でも、こうした展示会がもっとひんぱんに開催されればいいと思うし、なんらかの形で舞台美術がデータとして残せないものか…。ワタシなどは、将来的にはホログラム(3D)映像としてアーカイブ化できないものかと、夢想するのであるが…。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


舞台美術家である堀尾幸男、島次郎、土屋茂昭、が、4作ずつの模型を展示するほか、数多くの作品をプロジェクターで紹介する。
まず会場に足を踏み入れて、目を奪われるのは堀尾の「欲望という名の電車」。場末の酒場とねぐら、ベット…「汚し」と空間を生かした設計でテネシー・ウィリアムズが描いた「世界」を見事に再現。「模型」ながら、時空を超えてその「世界」へと誘う。さらに「彦馬がゆく!」(上記写真)の精巧さと奥行きある舞台空間に驚かされる。そして、「さまよえるオランダ人」「ザ・キャラクター」と続く。
島は、「ヘンリー六世」「橋を渡ったら泣け」で、思いっきり舞台空間を拡げ、「ニュルンベルク裁判」ではアートに、「焼肉ドラゴン」ではあの臭い立つ長屋へ。
土屋は、「鹿鳴館」「エビータ」「クラウディア」でゴージャスに、「思い出を売る男」では陰影にとんだノスタルジックな世界を構築。
ワタシ的には、緻密職人の堀尾、空間派の島、ライティングの魔術師・土屋という印象を持ったが、まったくの私見で、3者ともいずれも技量も素晴らしい。スペースは小さくとも、充実した展示イベントであったと思う。
これらの模型展示を見て思い出されたのが、上々颱風が行っていた野外コンサート「上々颱風祭り」の舞台模型。実物の舞台も素晴らしかったが、維新派の松本雄吉氏によるその舞台模型も本当に、見とれてしまったものだ。
映画美術監督の種田陽平氏も自著で悔しげに語っているがが、こうした舞台美術も公演が終了してしまえば、どんなに素晴らしいセットでも解体されてしまう。そうした意味でも、こうした展示会がもっとひんぱんに開催されればいいと思うし、なんらかの形で舞台美術がデータとして残せないものか…。ワタシなどは、将来的にはホログラム(3D)映像としてアーカイブ化できないものかと、夢想するのであるが…。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【CD】My Room In The Trees/The Innocence Mission ― 2010/09/23
 | マイ・ルーム・イン・ザ・トゥリーズ イノセンス・ミッション Pヴァイン・レコード 2010-06-30 売り上げランキング : 55006 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
私見だが、ロックが世界のポピュラーミュージックを牽引していたのは1970年代まで。1980年にその役割を終えた。なぜならTalking Headsがこの年に『Remain In Light』
そして82年、CDが登場する。87年にビートルズの音源がCD化されることによって、このメディアは急速に広がった。それによって何が起こったか? 過去のさまざまな音源がCD化され、「時間の扉」が解かれたのだ。つまり過去の音源も新曲も等価に聴かれるようになった。
若者が集うクラブで、DJがビートルズをかけたところ、フロアの若い客から「これは何ていう新人バンド?」と尋ねられたという笑い話もさもありなん。ワタシが若い頃、日本盤が発売されなかったバンドの音源や、こここまでやるか!?と思えるような過去のレア音源が発掘、リリースされ続けている。それをまた若い世代が新鮮に耳する。まさにバック・トゥ・ザ・フューチャー現象が起こったのだ。
ワールドミュージックが世界のポーダーレス化を勧めたとするならば、CD(音楽のデジタルアーカイブ化)は、音楽文化のタイムレス化を推進した。そして、この動きはまだしばらく続くのではないか…。
と、同様に書籍がデジタル化されたときに同じ現象が起こるのではないか…とワタシは思っている。
前置きが長くなったが、そんなロック幻想が持てなくなったワタシの耳に久かたぶりひっかかった盤が、米ペンシルバニア州出身の3人組The Innocence Missionによる『My Room In The Trees』(2010年6月)。
収録曲の⑥「All the Weather 」が、福山雅治演ずるキューピーハーフのCMに使用されていたというが、ワタシは知らなかった…。話題になっていたのだろうか?
もっとも彼(彼女)らの音楽に、いわゆる「ロック」ではない。ややハスキーで甘酸っぱい声に、ギター、ベース、ストリングスが静かに絡む。タイトルどおり、日陰のツリーハウスか、冬の日に部屋で一人静かに聴くのがふさわしい静寂の音楽。しかし、かえってワタシはそこにかって「ロック」がもっていた強靱さを感じる。自分たちの音楽に対する確信とそれに見合う技量と才能。ワタシが惹かれたのは、きっとそこであろう。
というわけで、ワタシもこれからバック・トゥ・ザ・フューチャー→「THE ROLLING STONES 『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan」に出かけることにするか…(苦笑)。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【音楽・映画】THE ROLLING STONES『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan ― 2010/09/24
![<table border="0" cellpadding="5"><tr><td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FLseQ88ML._SL160_.jpg" border="0" alt="レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]" /></a></td><td valign="top"><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank">レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]</a><br /><br />WHD ENTERTAINMENT(V)(D) 2010-10-13<br />売り上げランキング : 108<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/inTHE ROLLING STONES 『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan <table border="0" cellpadding="5"><tr><td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FLseQ88ML._SL160_.jpg" border="0" alt="レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]" /></a></td><td valign="top"><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank">レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]</a><br /><br />WHD ENTERTAINMENT(V)(D) 2010-10-13<br />売り上げランキング : 108<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/inTHE ROLLING STONES 『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan](http://yui-planning.asablo.jp/blog/img/2010/09/24/12b76c.jpg)
音楽ネタが続くが、やはり書いておかなくてはならない「THE ROLLING STONES 『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan」(9月23日)。1974年に一部公開されたものの、権利の関係でお蔵入りとなっていたローリング・ストーンズのコンサート・フィルムをあの日本武道館で観るという、フィルム・コンサート。3回公演のうちワタシは16:00の回に参戦した。
「あの武道館」と記したのは、このフィルムが72年の全米公演のストーンズの姿を捉えたもので、その72年にストーンズの来日公演が中止になっているからだ。つまり、幻のストーンズ日本公演が38年経った、この2010年に“実現”したという“画期的”なイベントといえる。日本のストーンズ・ファンの怨念(リベンジ)がこめられると言っても過言ではない。
もっとも田舎の小学生だったワタシなどは、来日騒動を東北の空から虚しく見ていただけなので、それほど思い入れはない。なのに、なぜ参戦したかといえば、600インチの巨大スクリーンに天井から巨大スピーカー群を吊るす「フライング・システム」の採用でリアルなライヴ・サウンドが再現される…という煽りつられて、という訳だ。
さて、その1972年のストーンズだが、まず驚かされのはその「音圧」。はっきり言って、音はよくない。ワタシなどは当時、悪名高かった武道館の音を“再現”するために、わざとヒドイ音にしているのではないかと訝ってしまったほど(苦笑)。が、その迫力のストーンズ・サウンドには本当に驚いた。まるで、ハード・ロック・バンド!重工機か、あるいはまるで津波のように音が襲ってくる。
ストーンズのライブは2回経験し、いくつかのフィルムも観ているが、こんなストーンズ聴いたことがない…。キース・リチャーズのワイルドなギターと対をなす流麗なミック・テイラーのプレイ、そしてチャーリー・ワッツの恐ろしく力強いドラムとボトムの効いたビル・ワイマンのベース…強靱なバンド・アンサンブルに加えて、サポートメンバーのボビー・キーズ(s)、ジム・プライス(tp,tb)のブラスがさらに厚みを加えていく。そのマグマが吹き出たようなサウンドは、ニッキー・ホプキンスのせっかくのピアノが聴きとれないほど(笑)。[セットリストはこちら]
しかも、一曲目の「ブラウン・シュガー」からテンション上がりっばなし、途中のブルースナンバーもミック・ジャガーのセクシャルなパフォーマスンで、まるでドロ沼に引きずり込まれるよう…。そして、怒濤のラスト「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」~「ストリート・ファイティング・マン」とさらにテンションは高まり、溶岩となった「石ころ」たちが噴火する。
繰り返すがストーンズがこれほどハードなロック・バンドだったとは、本当に驚きだ。そうした意味では、ワタシたち日本(に住む)人にとっては、ロック史における新たな「発見」だと思う。常套句ではあるが、ストーンズ・ファンだけではなく、ロック・ファンならば、けっして観て損のない作品(体験)。期間限定だが10月には劇場公開もされ、DVD発売もされる されるようだ。
されるようだ。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


「あの武道館」と記したのは、このフィルムが72年の全米公演のストーンズの姿を捉えたもので、その72年にストーンズの来日公演が中止になっているからだ。つまり、幻のストーンズ日本公演が38年経った、この2010年に“実現”したという“画期的”なイベントといえる。日本のストーンズ・ファンの怨念(リベンジ)がこめられると言っても過言ではない。
もっとも田舎の小学生だったワタシなどは、来日騒動を東北の空から虚しく見ていただけなので、それほど思い入れはない。なのに、なぜ参戦したかといえば、600インチの巨大スクリーンに天井から巨大スピーカー群を吊るす「フライング・システム」の採用でリアルなライヴ・サウンドが再現される…という煽りつられて、という訳だ。
さて、その1972年のストーンズだが、まず驚かされのはその「音圧」。はっきり言って、音はよくない。ワタシなどは当時、悪名高かった武道館の音を“再現”するために、わざとヒドイ音にしているのではないかと訝ってしまったほど(苦笑)。が、その迫力のストーンズ・サウンドには本当に驚いた。まるで、ハード・ロック・バンド!重工機か、あるいはまるで津波のように音が襲ってくる。
ストーンズのライブは2回経験し、いくつかのフィルムも観ているが、こんなストーンズ聴いたことがない…。キース・リチャーズのワイルドなギターと対をなす流麗なミック・テイラーのプレイ、そしてチャーリー・ワッツの恐ろしく力強いドラムとボトムの効いたビル・ワイマンのベース…強靱なバンド・アンサンブルに加えて、サポートメンバーのボビー・キーズ(s)、ジム・プライス(tp,tb)のブラスがさらに厚みを加えていく。そのマグマが吹き出たようなサウンドは、ニッキー・ホプキンスのせっかくのピアノが聴きとれないほど(笑)。[セットリストはこちら]
しかも、一曲目の「ブラウン・シュガー」からテンション上がりっばなし、途中のブルースナンバーもミック・ジャガーのセクシャルなパフォーマスンで、まるでドロ沼に引きずり込まれるよう…。そして、怒濤のラスト「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」~「ストリート・ファイティング・マン」とさらにテンションは高まり、溶岩となった「石ころ」たちが噴火する。
繰り返すがストーンズがこれほどハードなロック・バンドだったとは、本当に驚きだ。そうした意味では、ワタシたち日本(に住む)人にとっては、ロック史における新たな「発見」だと思う。常套句ではあるが、ストーンズ・ファンだけではなく、ロック・ファンならば、けっして観て損のない作品(体験)。期間限定だが10月には劇場公開もされ、DVD発売もされる
↓応援クリックにご協力をお願いします。
![レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FLseQ88ML._SL160_.jpg) | レディース・アンド・ジェントルメン [DVD] WHD ENTERTAINMENT(V)(D) 2010-10-13 売り上げランキング : 108 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
【映画】チェイサー ― 2010/09/25

『チェイサー』(2008年・監督:ナ・ホンジン)
実際に起こった連続殺人事件をモチーフにしたという話題の韓国映画。驚くべきはこれが長編デビュー作という監督の手練。猟奇的な殺人を繰り返す犯人を、デリバリーヘルスを経営する元刑事が追う、というストーリーだが、そこはかとないユーモアをまぶしながら、観客もその追跡劇に誘う術はタダ者ではない。
なにしろ、無表情な殺人マシーンによる殺戮シーンはスプラッター映画そのもの。そこに、元刑事の節操のないダメダメぶりが、先輩警官やヘルス嬢とのやりとりのなかで、笑いを誘いながら描かれる。そして監禁されたヘルス嬢の娘と、互いに反発しながらも心通じさせていく様に、やがてワタシたちはこのダメ男に共感を覚え、スクリーンのなかの追跡者(チェイサー)と同期する。
娘が号泣する場面をあえて無音にし、その絶望感と無力感を際立させる。あるいは、ダメ男がなぜ警察を辞めたのか、どんな育ち方をし、なぜ娘のためにヘルス嬢を必死で探そうとするのか、いずれもほぼワンシーンで語ってしまう。その技量はとても「新人監督」とは思えないらつ腕ぶり。
それにしても、さすがは「恨」の国、韓国(映画)人の「業」の描き方はハンパじゃない。『母なる証明』がそうであったように、ラスト近く、あまりの救いのないその展開に、ワタシたちは奈落の底に突き落とされる。…が、最後の一幕。『グムエル~漢江の怪物』のラストを彷彿させる「希望」を暗示させながら、この映画は静かに幕を閉じる…。
それにしても本作、ハリウッドでリメイクされるというがこのラストはどうするのだろうか? 近年の韓国映画の底力を示す、繊細にして、あまりに大胆なコリアン・フィルム・ノワール。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


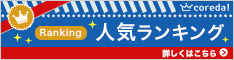

実際に起こった連続殺人事件をモチーフにしたという話題の韓国映画。驚くべきはこれが長編デビュー作という監督の手練。猟奇的な殺人を繰り返す犯人を、デリバリーヘルスを経営する元刑事が追う、というストーリーだが、そこはかとないユーモアをまぶしながら、観客もその追跡劇に誘う術はタダ者ではない。
なにしろ、無表情な殺人マシーンによる殺戮シーンはスプラッター映画そのもの。そこに、元刑事の節操のないダメダメぶりが、先輩警官やヘルス嬢とのやりとりのなかで、笑いを誘いながら描かれる。そして監禁されたヘルス嬢の娘と、互いに反発しながらも心通じさせていく様に、やがてワタシたちはこのダメ男に共感を覚え、スクリーンのなかの追跡者(チェイサー)と同期する。
娘が号泣する場面をあえて無音にし、その絶望感と無力感を際立させる。あるいは、ダメ男がなぜ警察を辞めたのか、どんな育ち方をし、なぜ娘のためにヘルス嬢を必死で探そうとするのか、いずれもほぼワンシーンで語ってしまう。その技量はとても「新人監督」とは思えないらつ腕ぶり。
それにしても、さすがは「恨」の国、韓国(映画)人の「業」の描き方はハンパじゃない。『母なる証明』がそうであったように、ラスト近く、あまりの救いのないその展開に、ワタシたちは奈落の底に突き落とされる。…が、最後の一幕。『グムエル~漢江の怪物』のラストを彷彿させる「希望」を暗示させながら、この映画は静かに幕を閉じる…。
それにしても本作、ハリウッドでリメイクされるというがこのラストはどうするのだろうか? 近年の韓国映画の底力を示す、繊細にして、あまりに大胆なコリアン・フィルム・ノワール。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【本】仕事漂流 就職氷河期世代の「働き方」 ― 2010/09/26
 | 仕事漂流 ― 就職氷河期世代の「働き方」 稲泉 連 プレジデント社 2010-04-15 売り上げランキング : 38529 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
さすがにそこは史上最年少で大宅賞作家となった稲泉氏。一人ひとりに(おそらく)2~3年の取材を重ね、しかも本人だけでなく周囲の人びとにも接触し、エピソードを重ねながら一本一本を読みごたえのある「物語」として完成させている。そこで語られるのは、「氷河期」で希望をそがれ、過酷な「現実」に翻弄されながら、揺れ動きながらも懸命に「働く」若者たちの裸身だ。そこに至る、若者たちの心情を吐露させる巧みな取材力と構成力には、相変わらず舌を巻く。
が、正直言ってワタシは、最後までこれらの「物語」につき合うのが少々辛かった。途中から惰性で頁をめくった。なぜなら、ここに登場する「エリート」たちの話に、どうしても同質な手触りを感じてしまうからだ。いくらおいしい料理でも、同じような料理な並べられたら、こちらも飽きがくる。
著者には同じ「働く」ことをテーマにした『僕らが働く理由、働かない理由、働けない理由』
そして二点目は、本書にする「エリート」たちだけでなく、多くの若者たちが直面している「理不尽な労働」について、その構造的な問題にほとんど触れていないからだ。例えば2章で、廃棄商品のケーキを社員やアルバイトが「買わされる」場面が出てくる。それが売り場の「売上」に計上されるからだ。「ケーキを自ら購入しながら『すみません、これだけしか買えなくて』などと謝っている」…という現実に対して「怒り」はないのだろうか? これは不当労働行為ではあるまいか? 周りにいる若者たちが、本書に登場するような「勝ち組」といはいえないような「労働者」ばかりだから、ワタシだけがそう感じるのだろうか…。
もちろん本書の「役割」はそうしたことではなく、「彼らの見た会社の風景や気持ちを少しでも書き残しておく」(あとがきより)かもしれないが、インタビュー部分を削ってもこうした「肉付け」があったほうが、本書の「意味」は高まったのではないかと思う。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【CD】SUPERJUNIOR/第4集 BONAMANIA(美人) ― 2010/09/27
 | SUPER JUNIOR 第4集(DVD付)【ジャケットA】 SUPER JUNIOR rhythm zone 2010-07-21 売り上げランキング : 1969 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
魅力は何といってもその歌唱力だ。日本の「歌える」男性シンガーのほとんどが声張り上げ系に対して、甘く切なく囁くようなウィスパリングからハイトーン~ファルセットへと、なめらかなヴォイス・コントロールはじつに見事。もちろん、日本の「アイドル」にこれほどの歌い手はいない。
アルバムは、イケイケのダンスナンバー①②に始まり、③④でバラード、⑤~⑦で爽やか系、そして再びバラードの⑧⑨、ラストは⑪前向きソングという、緩急に富んだ構成。楽曲も粒揃い。
メンバー13人がドラマ班、バラエティー班など役割分担していて、メインヴォーカルは、歌唱力に定評のあるイェソン、⑨「春の日」で素晴らしいハイトーンを聴かせるリョウク、ハスキーなキュヒョンが担当しているようだ。
K-POPブームで、話題はもっぱらそのビジュアルやダンスに集中しているようだが、こうした「聴かせる」アルバムをコンスタントにリリースする「アイドル」を次々と輩出していることこそが、コリアン・エンターテイメントの今の実力を端的に示している。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【本】君と会えたから・・・ ― 2010/09/28
 | 君と会えたから・・・ 喜多川 泰 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2006-07-10 売り上げランキング : 1243 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
本書もそうした動機から手にとったのではあるが、感心したのは作品の出来ではなく、ほほぉ、こういうジャンルもありなのかと、見聞を新たにしたこと。そうした意味では、本書の著者は『もしドラ』
で、内容だが、イケてない高校生活を送る主人公が、心よせる少女の「父」が書いた「手紙」の内容に啓発されて、「夢」を掴みとっていくというもの。「手紙」によって、自己分析→実現に向けて具体的な行動までが、レクチャー(ステップアップ)されるのだが、少女との恋愛と「いのち」をサブテーマにした「小説」の形式をとっているので、「自己啓発」モノ特有の押しつけがましさをあまり感じずに読み進めることができる…のだろう。
「…のだろう」と記したのは、啓発本の類をほとんど読んだことのないワタシには、どうしても読みながら、こっ恥ずかしさを払拭できなかったからだ。恥ずかしながら、加藤諦三先生の本を読み漁っていた中高生時代を思い出してしまった(苦笑)。
ベストセラーになっているからには、多くの若い層から支持を得ているのだろうが、主人公が「世間の多くの人から成功者として認められるようにもなり」という結末に、鼻白んでしまうのは、ワタシが「成功者」ではないから? ベタな結末のほうが(若年層の)読者にはわかりやすいのかもしれないが、むしろ「成功者として認められ」ない、現世に無数に存在するシアワセな結末のほうがインパクトがあろうに…と思ってしまうのだが。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【映画】悪魔の発明 ― 2010/09/29

『悪魔の発明』(1957年・監督:カレル・ゼマン)
ジュール・ヴェルヌが1896年に発表した古典的なSF小説 を、チェコアニメ界が生んだ“幻想の魔術師”カレル・ゼマンが瞠目の映像によって奇想天外な世界につくりあげた。まるで、江戸川乱歩の『パノラマ島綺譚』を独自の美学で漫画化
を、チェコアニメ界が生んだ“幻想の魔術師”カレル・ゼマンが瞠目の映像によって奇想天外な世界につくりあげた。まるで、江戸川乱歩の『パノラマ島綺譚』を独自の美学で漫画化 した丸尾末広のように、それは“魔術師”の脳内に渦巻く「妄想」を見事に映画表現として結実させた傑作といえる。
した丸尾末広のように、それは“魔術師”の脳内に渦巻く「妄想」を見事に映画表現として結実させた傑作といえる。
核兵器を思わせる強力な爆弾を開発中に、教授とその助手が海賊に誘拐され、孤島に幽閉される。研究を続ける教授と、それを阻止しようとする助手と彼を助ける美女…というのがストーリーだが、なにしろその映像とアイデアが素晴らしい。
映画全編は銅版画を再現したようなモノクロ世界が覆い、実写、アニメ、模型撮影などがさまざまなに組み合わされ、摩訶不思議な世界をつくりあげている。とにかく、次々に繰り出されるその映像美に、目をみはり、ときに笑い、息をのむことしばし…。
1957年の作品だが、ハリーハウゼンに並ぶアニメーション表現の祖としても、今を予見した核兵器テロ映画としても、現代でこそもっともっと観られてイイ作品。『メトロポリス』復元版上映のように、イベント等での上映機会があれば、アニメ好きの若者たちもきっと熱狂するに違いない。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


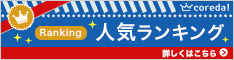

ジュール・ヴェルヌが1896年に発表した古典的なSF小説
核兵器を思わせる強力な爆弾を開発中に、教授とその助手が海賊に誘拐され、孤島に幽閉される。研究を続ける教授と、それを阻止しようとする助手と彼を助ける美女…というのがストーリーだが、なにしろその映像とアイデアが素晴らしい。
映画全編は銅版画を再現したようなモノクロ世界が覆い、実写、アニメ、模型撮影などがさまざまなに組み合わされ、摩訶不思議な世界をつくりあげている。とにかく、次々に繰り出されるその映像美に、目をみはり、ときに笑い、息をのむことしばし…。
1957年の作品だが、ハリーハウゼンに並ぶアニメーション表現の祖としても、今を予見した核兵器テロ映画としても、現代でこそもっともっと観られてイイ作品。『メトロポリス』復元版上映のように、イベント等での上映機会があれば、アニメ好きの若者たちもきっと熱狂するに違いない。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【LIVE】山下達郎 PERFORMANCE2010 ― 2010/09/30

8月6日から開催されている山下達郎のコンサート・ツアーの東京公演初日に参戦(9月29日NHKホール)。今回のツアーはデビュー35年周年ということで、全国35カ所で催される予定が追加があり39公演に。さすがのプラチナ・チケットぶり。
「35周年」というのは、本人はもとより、シュガーベイブ時代からその活動を追いかけてきたワタシたちにとっても感慨ひとしお…。それよりも還暦間際にして(失礼)、ここ数年毎年全国ツアーを行っているその気力、体力、充実ぶりに脱帽。なにせヤマタツのライブといえば、通常、3時間を超えるもので、この日も3時間20分(もちろん休憩なし)にわたって圧倒的なパフォーマンスを魅せてくれた。
ご本人もMCで「ツアー途中なのでネタバレご配慮を」と言っていたので、詳しいセットリストなどは記さないが、コンサートはヤマタツのギターカッティングが冴える3曲で華やかな幕開け。ヤマタツのカッティングといえばギター専門誌にも取り上げられるほど定評あるが、愛器テレキャスターを抱え、本当に気持ちよさそうに、はじけるように弾き、歌う。
そして、これまたヤマタツ・コンサートには欠かせない舞台セットだが、今回はカントリー風の佇まい。ウッドデッキを設えた家や芝生、納屋に収められたトラクター(ここも演奏ステージ)、奥には風力発電の風車が回り、緑の畑が広がる…。このセットが曲に合わせて、昼、夜、冬、街へと表情を変える。ライティングも合せて、いつもながら、その細やかな仕事ぶりには感心させられる。
もちろん、最も感心(激)させられたのは、ヤマタツ氏のパフォーマンス。前回(98年、もう12年も前か!)観たときは、アグレッシブで驚異的なヴォーカリゼーションに驚かされたが、今回はその声をすっかりバンド・アンサンブルに溶け込ませて、じっくり、しっとりとその歌をきかせてくれる。この肩の力の抜け具合は(けっして年のせいだけではなく)、新作アルバムのプロモーションとツアーを切り離し、ツアーそのものを楽しみ、ファンに聴かせたい、というスタイルの変化によってもたらされのではないだろうか。
そして、これも毎回聴きもののヤマタツ・バンドも一糸乱れぬ演奏で、抜群のコンビネーション。ファースト・ソロ作に収められたシュガーベイブのレパートリー曲を、シュガーベイブ・スタイルで演奏(ブルージーでサイケな一面も)するなど、遊び心も満載。アカペラ2曲から、あの名曲に繋ぐあたりの構成も素晴らしい。お約束の地声+トラメガ・パフォーマンス、演歌メロディーなど、聴きどころは枚挙のいとまがない。
選曲もほぼベスト・オブ・ベストで3時間20分、まったくダレることなく、その「孤高な」音楽世界を堪能させてもらった。(褒めてばかりいるが本当に素晴らしかったのだから仕方ない)
結局、ロック/ポップ・ミュージックに原初のエネルギーを求めことはもう難しい。しからば、「後退」でなく「ノスタルジー」でなく、それが生き続けるにはもはや「成熟」しか道はないのであるまいか。毎年クオリティの高い新曲を発表し、新たな若いファンをも獲得するなど、その「成熟」の道を見事に提示しているアーティストの一人が、間違いなく山下達郎だ。
そうした意味では、爆音ロック全盛時代にシュガーベイブを率いて、「孤高」の道を歩んでいたヤマタツは、ずっと「革新」だったのだと思う。もちろん今もそれは変わらない。
これは予見だが、今回のツアーでヤマタツ氏が提示したたような新作プロモーションとツアーを切り離した展開が、今後音楽業界に拡がるのではないだろうか。もちろんそれには、ヤマタツ氏が言うように「(曲など予習せずに)初めてコンサートに来た客を魅了する」アーティストとしてのクオリティがますます求められると思う。
例えば、ラスベガスや劇団四季などのように、しかもノスタルジア・サーキット(懐メロ興行)ではない形で、いつでも山下達郎のコンサートが堪能できる常設小屋が出来たら、それはそれでファンとしてこんな嬉しいことはない…そんなことまで夢想してしまう「ロックの未来」を観たコンサートだった。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


「35周年」というのは、本人はもとより、シュガーベイブ時代からその活動を追いかけてきたワタシたちにとっても感慨ひとしお…。それよりも還暦間際にして(失礼)、ここ数年毎年全国ツアーを行っているその気力、体力、充実ぶりに脱帽。なにせヤマタツのライブといえば、通常、3時間を超えるもので、この日も3時間20分(もちろん休憩なし)にわたって圧倒的なパフォーマンスを魅せてくれた。
ご本人もMCで「ツアー途中なのでネタバレご配慮を」と言っていたので、詳しいセットリストなどは記さないが、コンサートはヤマタツのギターカッティングが冴える3曲で華やかな幕開け。ヤマタツのカッティングといえばギター専門誌にも取り上げられるほど定評あるが、愛器テレキャスターを抱え、本当に気持ちよさそうに、はじけるように弾き、歌う。
そして、これまたヤマタツ・コンサートには欠かせない舞台セットだが、今回はカントリー風の佇まい。ウッドデッキを設えた家や芝生、納屋に収められたトラクター(ここも演奏ステージ)、奥には風力発電の風車が回り、緑の畑が広がる…。このセットが曲に合わせて、昼、夜、冬、街へと表情を変える。ライティングも合せて、いつもながら、その細やかな仕事ぶりには感心させられる。
もちろん、最も感心(激)させられたのは、ヤマタツ氏のパフォーマンス。前回(98年、もう12年も前か!)観たときは、アグレッシブで驚異的なヴォーカリゼーションに驚かされたが、今回はその声をすっかりバンド・アンサンブルに溶け込ませて、じっくり、しっとりとその歌をきかせてくれる。この肩の力の抜け具合は(けっして年のせいだけではなく)、新作アルバムのプロモーションとツアーを切り離し、ツアーそのものを楽しみ、ファンに聴かせたい、というスタイルの変化によってもたらされのではないだろうか。
そして、これも毎回聴きもののヤマタツ・バンドも一糸乱れぬ演奏で、抜群のコンビネーション。ファースト・ソロ作に収められたシュガーベイブのレパートリー曲を、シュガーベイブ・スタイルで演奏(ブルージーでサイケな一面も)するなど、遊び心も満載。アカペラ2曲から、あの名曲に繋ぐあたりの構成も素晴らしい。お約束の地声+トラメガ・パフォーマンス、演歌メロディーなど、聴きどころは枚挙のいとまがない。
選曲もほぼベスト・オブ・ベストで3時間20分、まったくダレることなく、その「孤高な」音楽世界を堪能させてもらった。(褒めてばかりいるが本当に素晴らしかったのだから仕方ない)
結局、ロック/ポップ・ミュージックに原初のエネルギーを求めことはもう難しい。しからば、「後退」でなく「ノスタルジー」でなく、それが生き続けるにはもはや「成熟」しか道はないのであるまいか。毎年クオリティの高い新曲を発表し、新たな若いファンをも獲得するなど、その「成熟」の道を見事に提示しているアーティストの一人が、間違いなく山下達郎だ。
そうした意味では、爆音ロック全盛時代にシュガーベイブを率いて、「孤高」の道を歩んでいたヤマタツは、ずっと「革新」だったのだと思う。もちろん今もそれは変わらない。
これは予見だが、今回のツアーでヤマタツ氏が提示したたような新作プロモーションとツアーを切り離した展開が、今後音楽業界に拡がるのではないだろうか。もちろんそれには、ヤマタツ氏が言うように「(曲など予習せずに)初めてコンサートに来た客を魅了する」アーティストとしてのクオリティがますます求められると思う。
例えば、ラスベガスや劇団四季などのように、しかもノスタルジア・サーキット(懐メロ興行)ではない形で、いつでも山下達郎のコンサートが堪能できる常設小屋が出来たら、それはそれでファンとしてこんな嬉しいことはない…そんなことまで夢想してしまう「ロックの未来」を観たコンサートだった。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


最近のコメント