【本】グーテンベルクの銀河系 ― 2010/09/12
 | グーテンベルクの銀河系―活字人間の形成 マーシャル マクルーハン 森 常治 みすず書房 1986-02-20 売り上げランキング : 93211 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
で、本書は、非文字の「部族社会」から中世・ルネッサンス、そして現代(1960年初頭)に至るその「銀河」をつぶさに検証していくわけだが、…部族共同体、精神分析、ホメロス、シェイクスピア…と哲学書を繙くような(ワタシにとっては)難解な、渦巻くような論理と解析が展開され、これは(ワタシには)ちょっと太刀打ちできないかも…。と、思い始めた矢先に、俄然、本書の言葉が頭に入り始めた。
筆者自ら「本書『グーテンベルクの銀河系』は[グーテンベルクに発した文化が含む]さまざまな問題に対するモザイク的な接近方法(アプローチ)を開発するものである」と記しているが、このモザイク的な事例・エピソード・分析がじつに面白いのだ。
「活版印刷の発明は、応用知識の特色である新しい視覚強調を保証し、拡大した。その結果生れたのが、最初の、均質にして反復可能な<商品>であり、最初に組み立てライン、最初の大量生産方式であった」「印刷されたページからわれわれに伝わってくる均質的反復可能性の概念が、人生の他の部面まで拡張されるとき[新しい]生産様式や社会形態が誕生する。西欧世界はそこから多くの満足を手に入れたのであり、またそれらは西欧世界のほとんどすべての性格的特色の源泉となった」として、その影響は近代のテクノロジーと消費社会を産み、さらには個人主義・ナショナリズムまでを形成したという。
「均質化され反復可能な商品が登場するまで、品物の値段は買い手と売り手の交渉によってはじめて決まったものであった。本の均質性は反復可能性は、このように文字使用および産業と切っても切れない関係にある現代の市場や価格システムを作り出した」と指摘し、さらに「われわれがここ数世紀の間、『国民(ネーション)』の名で呼んできたものはグーテンベルクの印刷技術が出現する以前は発生したことはなかった」と喝破する。
が、本書におけるこうしたマクルーハンの卓越した分析や論点を連ねても、本書の面白さは伝わらないかと思う。ワタシが本書に魅力を感じるのは、ワタシたちが生きるこの「現代」にあてはめて、さまざまな「読み換え」ができることだ。
例えば、「人間の身体の直接的な技術的延長としての印刷によって、それが発明されてしばらくというもの、ひとびとはけっして手に入れることができなかったような力と興奮とを手に入れた」「印刷はいわば筆写(スクリプト)という『冷たい(クール)』媒体によって幾千年間も仕えられてきた世界のなかに、たいへん『熱い(ホット)』媒体として登場した」とする、この「印刷」を「インターネット」としてみたらどうだろうか? あるいは、印刷技術登場によってそれ以前の本の製作技術であった「写本」がどうなったかについての記述もじつに興味深い。
クルト・ビューラー『十五世紀--書記、印刷屋、装幀家』の記述を引いて、「では写本家たちはどうなったのだろう」「修道院の大きな写本室でそれまでやとわれていたプロの写本家たちは肩書きを変えて書道家に変身したかに見える」「とはいうものの身についた技術を生かして書道家となった連中は、専らとはいわずとも、必然的に[豪華本の]「特別注文承り屋」とならざるをえなかった」「書道は応用技芸、最悪の場合はたんなるホビーに堕ちてしまった」という。
どうだろう、デジタル技術と電子出版の革新が押し寄せる現代にあって、この「写本家」を「編集者」と言い換えられる日は近いのではあるまいか?
しかし、その一方で「中世の学生は自分が読む著作者たちの校訂者、編集者および発行人である必要がった」「印刷が出現する以前の読者、つまり本の消費者は、文字どおり本の製作者として製作過程にも加担していた」「写本文化は会話的であった。それは、<公演による新作発表>によって同座する作者と読者とが身体的に結びつけられていた」というだから、今でいう「集合知」に近かったに相違ない。
またこんな記述も見られる。「十七世紀の後半になると、印刷物の量が急激に増大しはじめた現象に対して、相当な警戒心と不安、そして嫌悪の念が表明された」。ここでも「印刷物」を、「インターネット」に置き換えることができる。
そして、マクルーハンは本書が刊行された1962年にすでに予見している。 「電子時代は[中略]、機械の時代ではなく、有機的組織化の時代であり、そのため活版印刷技術[中略]によって手に入れられた諸価値にほとんど共感を抱くことのない時代だからである」「地球上のすべての成員を巻き込んで呉越同舟の状態にしてしまう力をもつ電気回路技術が到来した今日以降、そうした旧来の「国民」は生きのびルことはできないであろう」「電気的情報構造から生れる『同時発視野』は、今日社会のあらゆる面で専門主義や個人の創意よりむしろ、対話や参加のための条件や必要を復活させている」「そして対話と参加といったあたらしい相互依存に迫られているわれわれの状況は、多くの人びとのなかに、西欧人がルネッサンス時代から受けついできた遺産から引き離されるための不安と不安感と挫折感を生み出しているのも事実だ」としている。ここでマクルーハンのいう「電子」とは、テレビやラジオ、映画を指しているのだが「インターネット」と読み換えることも十分可能なはずだ。
このようにマクルーハンは、活版文化を礼賛しているわけではなく、むしろ活字(書物)が視覚強調を促進することで聴覚・触覚を抑圧し、「人間は文字文化、とくに印刷文化の導入によって生への全体的な了解から疎外された」として、「電波文化は楽園への復帰の条件を整えた」(訳者の森常治氏による)と主張している。
哲学者・文芸評論家のジョージ・スタイナーはマクルーハンに触れて、この歴史的な流れを『言語と沈黙』(1967年)でこう記している。
「長い口語時代があり、つぎにごく短い記録可能であり、記憶可能な芸術の時代(マクルーハンのグーテンベルグ銀河系の時代)があり、そしておそらくわれわれは再び多種多様な形式をもつ口語芸術の入口に到達した」 この「口語芸術」(視覚・聴覚芸術)を経て、いまワタシたちは「記憶可能」で、「同時発視野」かつ「対話や参加」が可能な電子の時代に入った。したがって、「本書の読者とともに、まずわれわれ西欧人が、活版印刷革命と、電子技術革命の両方がもつ意味をしっかりと把握理解することを願ってやまない」としたマクルーハンの言葉は、この現代にこそ生きてくる。
今ごろ本書を読んだワタシが言うのもおこがましいが、出版・活字文化に携わる者ならば、一度は「読むべき」名著だと思う。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【CD】While I'm Awake/GIOVANCA ― 2010/09/13
| ホワイル・アイム・アウェイク | |
 | ジョヴァンカ ジョヴァンカ feat.リオン・ウェア Anan Ryoko feat.ジョヴァンカ ヌジャベス feat.ジョヴァンカ&ベニー・シングス リオン・ウェア Amazonで詳しく見る by G-Tools |
楽曲のほとんどをGIOVANCA自身が手がけ、それを自身もミュージシャンで、近年は鬼才プロデューサーとして名が知られるベニー・シングス
二人が共に「本物」の才人で、見事なコラボレーション・パートナーあることは、このYouTube画像を見てもわかる。↓
テイストはシャーディーにも通じるが、日本盤ボーナストラックにはそのシャーディーの「Kiss Of Love」も収録されている。さすがにこのカバーは、シャーディーに軍配をあげたいが、「都会的の夜」をイメージした本作の魅力がアルバム全編を満たしている。
(リードトラック「Everything」はこちらで試聴できる↓)
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【映画】アクロス・ザ・ユニバース ― 2010/09/14

『アクロス・ザ・ユニバース』(2007年・監督:ジュリー・テイモア)
ビートルズ・ナンバー33曲によって紡がれるミュージカル映画。これはもう、ビートルズ・ナンバーのPV集といっていいだろう。それ以上でも以下でもない。ビートルズやビートルズの楽曲に興味のない人は、観る必要のない映画だと思う。
ストーリーも凡庸な青春メロドラマで、途中ドラッグやベトナム反戦なども盛り込まれるが、それらも深刻ではなくメッセージとして伝わってこない。主人公の青年が「ジュード」(ジム・スタージェス)で、ヒロインが「ルーシー」(エヴァン・レイチェル・ウッド)というのもあまりにベタ。父親や友人たちのサイドストーリーもありきたり。ビートルズナンバー(歌詞)に合わせて、ストーリーをつくったわけだからだから(おそらく)高尚な脚本を求めてもそれは無理だというものだろう。
が、前述したようにこれをビートルズ・ナンバーの(当時は製作されなかった)新作PV集と観れば、それはそれで楽しめる。カラフルな映像と奇抜なアイデアで、次々とその名曲群に新たな光を与えていくわけだから、製作陣としてはきっと楽しい作業だったに違いない。キャストは吹き替えなしで歌っているというが、それもそうヒドいしろものではない。造船会社の老職員が年を聞かれて「64歳」と答えたり、ビルの屋上の演奏シーンなど、ビートルズファンならニャッとさせられる「オマージュ」もたっぷり。
むしろワタシにとって発見だったのは、その「歌詞」たちが「セリフ」として十分「使える」ものだったことだ。英語に堪能ではないこともあるが、ビートルズ・ソングの「歌詞」がこれほど魅力的なものだったとは!さらにはこの「歌詞」をこの場面で使う!? という意表を突かれることもしばしば。それはビートルズが生み出した「言葉」たちが時代を超えて、普遍的かつ万華鏡の如く、ワタシたちに何か伝えている証左ではないだろうか。
そうした意味では、解散して40年も経つのにいまだにワタシたちに新たな発見、新たな楽しみ方を教えてくれるビートルズの偉大さに改めて敬服するのみ。まさに、墓場までビートルズ、骨の髄までビートルズだ。
こうなると、シルク・ドゥ・ソレイユによる『ラブ』公演を早く観てみたい。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


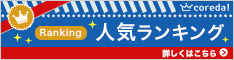

ビートルズ・ナンバー33曲によって紡がれるミュージカル映画。これはもう、ビートルズ・ナンバーのPV集といっていいだろう。それ以上でも以下でもない。ビートルズやビートルズの楽曲に興味のない人は、観る必要のない映画だと思う。
ストーリーも凡庸な青春メロドラマで、途中ドラッグやベトナム反戦なども盛り込まれるが、それらも深刻ではなくメッセージとして伝わってこない。主人公の青年が「ジュード」(ジム・スタージェス)で、ヒロインが「ルーシー」(エヴァン・レイチェル・ウッド)というのもあまりにベタ。父親や友人たちのサイドストーリーもありきたり。ビートルズナンバー(歌詞)に合わせて、ストーリーをつくったわけだからだから(おそらく)高尚な脚本を求めてもそれは無理だというものだろう。
が、前述したようにこれをビートルズ・ナンバーの(当時は製作されなかった)新作PV集と観れば、それはそれで楽しめる。カラフルな映像と奇抜なアイデアで、次々とその名曲群に新たな光を与えていくわけだから、製作陣としてはきっと楽しい作業だったに違いない。キャストは吹き替えなしで歌っているというが、それもそうヒドいしろものではない。造船会社の老職員が年を聞かれて「64歳」と答えたり、ビルの屋上の演奏シーンなど、ビートルズファンならニャッとさせられる「オマージュ」もたっぷり。
むしろワタシにとって発見だったのは、その「歌詞」たちが「セリフ」として十分「使える」ものだったことだ。英語に堪能ではないこともあるが、ビートルズ・ソングの「歌詞」がこれほど魅力的なものだったとは!さらにはこの「歌詞」をこの場面で使う!? という意表を突かれることもしばしば。それはビートルズが生み出した「言葉」たちが時代を超えて、普遍的かつ万華鏡の如く、ワタシたちに何か伝えている証左ではないだろうか。
そうした意味では、解散して40年も経つのにいまだにワタシたちに新たな発見、新たな楽しみ方を教えてくれるビートルズの偉大さに改めて敬服するのみ。まさに、墓場までビートルズ、骨の髄までビートルズだ。
こうなると、シルク・ドゥ・ソレイユによる『ラブ』公演を早く観てみたい。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【本】19歳 一家四人惨殺犯の告白 ― 2010/09/15
 | 19歳―一家四人惨殺犯の告白 (角川文庫) 永瀬 隼介 角川書店 2004-08 売り上げランキング : 26120 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
一家四人を惨殺した19歳の少年の「心の闇」に迫った作品だが、とにかく前半の少年が殺人に至るまでの描写は陰惨だ。読んでいて気分が悪くなってくる。気が滅入る。
そして後半--筆者と少年による書簡と面会のやりとりがつぶさに語られる。
その少年の書簡に驚かされる。例えば、少年が心酔したジミ・ヘンドリックスについての記述はこうだ。
「ジミ・ヘンドリックスのよく哭き、よく吼え、ひたすら唸りまくるギター・サウンドは、理解できない人にとっては、ただのノイズ(雑音)、騒音でしかないでしょうが、混沌と渦巻くをアヴァンギャルドな爆発力は、眩しいほどに輝いて素晴らしく、鬱々とした気分を突き刺してくれる。(中略)なぜ他の人達のように自分は、学校や地域社会、家庭、世界のすべてに対してつながりを感じられないか。そういったことへの返答を示してくれました。(中略)とくべつルックスに恵まれているわけでもなく、背も高くなければ声もいまいちなのに叡知を自在にあやつる優美さを有していて、且つ、血の通ったなまぐささ、埃っぽいあたたかさもある。(中略)あのアンプをめいっばいフィードバックさせたサウンド、剥き出しになった神経を鉋(かんな)で削ぎ落とすかのように独特のシンコペーションで疾走する爆音がたまりません。皮膚の毛穴のひとひひとつから肌に染み込んでくる刺激が、ズタズタにされていた自尊心にちょうど良く、癒される感じがしました」
というように、ヘタな音楽ライターよりも豊かな表現力で、この「軌道を逸した、ワイルドで破壊を求め続けた」ギターヒーローを描写している。ほかにも「凶暴な殺人犯」とは思えぬ、繊細な表現で記した手紙がいくつも紹介される。
また、被害者が眠る菩提寺の住職と少年との交流も感動的だ。住職は語る。「残酷な許しがたい事件です。しかし、わたしは彼の心の変わりようも見ています。拘置所で、彼に“あとから食料を差し入れるから、何か欲しいものはありますか”と告げると“できれば缶詰は避けてください。缶詰は担当の警務官の方に開けてもらわなければなりません。余計な手間をかけたくないのです”と言うほど、周囲への配慮を示すようにもなっています。わたしは、でき得るならば、死刑にしてほしくない、というのが本音です」
この住職のことを問われて少年は答える。「ああいう人が親戚にいたら、よかったなあ、と。外で出会えていたら、僕の人生も替わっていたかもしれませんね」…。
しかし、本書の最後になって、この少年と2年にわたって向き合った筆者がそうであったように、読者も「闇」に放り出される。
自分の人生を振り返って「なかったことにしてほしい」と口にする少年の「真意は、もはや理解不能だった」(少年が)「抱える心の闇は、わたしの想像を遥かに越えて、冥(くら)く、深く、広がっていた」と筆者は無力感を吐露するのだ。単行本はここで終わっていた。
が、この文庫版ではその後の顛末が書かれ、まさに命を削ってこの取材にかけていた筆者の心情が赤裸々に書かれ、その思いを救いとるかのように重松氏が本書の「意味」を解説している。
理解不能な「業」を抱えたそれもまた「人間」という存在なのだということを、衝撃を持ってワタシたちに突きつけているのが本書なのだ。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【CD】Five Finger Discount(万引き)/Phew ― 2010/09/16
 | ファイヴ・フィンガー・ディスカウント(万引き) PHEW BeReKet/Pヴァイン・レコード 2010-09-02 売り上げランキング : 2747 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
先頃亡くなった加藤和彦の「オーブル街」でこのアルバムは、静かに始まる。そのPhewの浮遊感漂う声を聴いただけで、ギクリとする。音程も安定もせず、声量もあるわけでもない。しかしその圧倒的な存在感は何なのだろう。「唄」とは何なのだろう?と思わせる強烈な求心力。
蚊の鳴くような声で「世界の果てまで連れてって」と歌われれば、本当に「世界の果て」に連れて行かれたような気分になり、「どこかであなたが生きている」と歌われれば、「本当に生きていてほしい」と思うようになり、そして「素晴らしい人生」と歌われれば「素晴らしい人生」とは一体何なのだろうと考え込まされる…。
それらの「唄」たちに、ジム・オルークや山本精一、ビッケら、腕っこきかつひとクセもふたクセもあるなミュージシャンたちが、影をしのばせるよう音を添えていく。
一転して、「青年は荒野をめざす」で力強くパンキッシュに。最後に「夢で逢いましょう」と囁かれてしまえば、ワタシはPhewの唄声にまた「逢い」たくなる…。
万人に薦められる作品ではないが、抗し難い魅力を放つ異形の逸品。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【映画】本日休診 ― 2010/09/17

『本日休診』(1952年・監督:渋谷実)
これだから旧作漁りは止められない。これは、はっきり言って傑作です!
井伏鱒二の短編(未読)をもとに、休診日の老医師とそれを取り巻く人びとの悲喜劇を見事に活写し、笑いに満ちた一篇に編みあげたもう一つの『赤ひげ』ともいうべき作品。
戦後の混乱のなかで、さまざまな災難や貧困とたたかいながらも希望をもって生き抜く庶民の姿…それを地域で慕われる老医師が暖かい目で見守り、ときに笑い飛ばす。
それを最も象徴するのが、三國連太郎扮する元兵隊…彼は戦争の後遺症で精神に障害をきたしている(今でいうPTSDだろうか)が、彼と周囲の人びととの笑いを誘うやりとりだろう。老医師は彼の奇行に笑いながらもつきあい、彼をとりまく人びともけっして彼を「排除」をしない。傷ついた「鳥」を飛行兵と思い込む彼と一緒に、飛んでいく「飛行兵」を見送るシーンなど笑いながら泣ける…お見事。
とにかくワンカット、ワンシーンに無駄がない。まさに、黒澤や溝口が言う連続する「写真」の美しさだ。それはかつての日本映画の矜持ともいえる「美」だと思う。
未見だが、この年、渋谷監督はこちらも名作とされる『現代人』という作品も撮っている。老医師を演じた柳栄二郎の老練な演技はもとより、若き日の鶴田浩二や淡島千景など、脇役陣も輝いている。今までノーマークだった渋谷監督作をもっと観たくなった。
◆『本日休診』のおすすめレビュー
5001:a cinema odyssey
銀の森のゴブリン
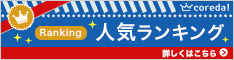

↓応援クリックにご協力をお願いします。


これだから旧作漁りは止められない。これは、はっきり言って傑作です!
井伏鱒二の短編(未読)をもとに、休診日の老医師とそれを取り巻く人びとの悲喜劇を見事に活写し、笑いに満ちた一篇に編みあげたもう一つの『赤ひげ』ともいうべき作品。
戦後の混乱のなかで、さまざまな災難や貧困とたたかいながらも希望をもって生き抜く庶民の姿…それを地域で慕われる老医師が暖かい目で見守り、ときに笑い飛ばす。
それを最も象徴するのが、三國連太郎扮する元兵隊…彼は戦争の後遺症で精神に障害をきたしている(今でいうPTSDだろうか)が、彼と周囲の人びととの笑いを誘うやりとりだろう。老医師は彼の奇行に笑いながらもつきあい、彼をとりまく人びともけっして彼を「排除」をしない。傷ついた「鳥」を飛行兵と思い込む彼と一緒に、飛んでいく「飛行兵」を見送るシーンなど笑いながら泣ける…お見事。
とにかくワンカット、ワンシーンに無駄がない。まさに、黒澤や溝口が言う連続する「写真」の美しさだ。それはかつての日本映画の矜持ともいえる「美」だと思う。
未見だが、この年、渋谷監督はこちらも名作とされる『現代人』という作品も撮っている。老医師を演じた柳栄二郎の老練な演技はもとより、若き日の鶴田浩二や淡島千景など、脇役陣も輝いている。今までノーマークだった渋谷監督作をもっと観たくなった。
◆『本日休診』のおすすめレビュー
5001:a cinema odyssey
銀の森のゴブリン
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【本】アッシュコンセプトの仕事―名児耶秀美と36人のデザイナー ― 2010/09/18
 | hello!design アッシュコンセプトの仕事―名児耶秀美と36人のデザイナー 名児耶 秀美 ラトルズ 2006-11 売り上げランキング : 443526 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
「生活者とデザイナーがともに楽しめるものづくり」をテーマに、若手デザイナーとコラボレートとしてデザインブランド「+d」を展開。本書では、その作品群が美しい写真とデザイン(レイアウト)ともに紹介され、それが「商品」に至るまでの経緯などが語られる。
こういう本は眺めているだけで楽しい。
第一号作品の「アニマルラバーバンド」は「落ちていたら拾ってもらえて掃除機にも吸われないサステイナブルな輪ゴム」をコンセプトに制作された動物のかたちをした色とりどりの輪ゴムたち。絵の具チューブやバナナのかたちをしたドアストッパー、さまざなアイデアが詰まったブックマーク(しおり)など、遊び心と実用性を備えた「商品」たちは、オトナの「萌え」をそそる。
だが本書は、同社の商品カタログではない。こうした商品が「つくることを前提したコンペ」など、さまざまなコラボのうえに成立している。そのことを巻末の名児耶代表らによる座談会などによって解き明かそうとしているのだが、どうも「思想」ばかりが先走って、どうもその協同作業、ものづくりの面白さ=裏側が見えてこない…。
刊行は2006年。「集合知」なる発想が、まだ日本でもに十分に周知されていなかった時代でもある。むべなるかな、ではあるがやや残念。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【アート】千代田芸術祭「3331アンデパンダン」 ― 2010/09/19

以前から気になっていた「千代田アーツ3331」で行われた「千代田芸術祭『3331アンデパンダン』」に足を運ぶ(9月18日)。
ここは廃校となった中学校の施設を活用し、アーティストが主導・運営する民設民営のスペース。こうした既存の施設を、新たなアートスペースとして活用した例といえば、今春に行われた「NO MAN'S LAND」が思い浮かぶが、あちらが旧フランス大使館の解体という期限を区切ったものに対して、こちらは地域に根ざした恒常的なアートセンターを目指すという。
それだけに施設・建物利用もこちらが一枚上で、明治以来から変わらない校舎・教室という学校文化・空間に、今も進化を続ける現代アートをマッチングさせるという妙が、じつに新鮮。校庭の跡地に緑広がる公園を配し、そこから入場すれば、どこか懐かしく、しかもモダンな異空間が広がる。
じつは会場に来る前は、「千代田」というローカルな冠詞が付いていたために、地域の趣味人が出展する学芸会的なものをイメージしていたのだが、これが大きな勘違い! 予想をはるかに超えた瞠目の展示会であった。
会場は1Fのギャラリー(元は職員室? 教室? 廊下だったなど推察しながら遊歩するのも楽しい)を利用して、19歳から70歳まで350点以上の作品がズラリと並ぶ。…だけでなく、壁を埋めつくし、天井から吊り下げられ、床に敷きつめられ…と多彩な展示。それも玉石混交ではなく、ほとんど「石」が見当たらない!
アニメ風のポップな人形が床に転がり、東南アジア風の仮面がぶら下がり、麻と布のオブジェからは内蔵(?)が飛び出し、凛とした生け花にクモの巣が絡む。キュービズムを模した粘土細工、女子高生ゴリコ を思わせる絵画、背中からキノコの生えた裸女、子どもが遊ぶような砂場が広がり、蕎麦のキノコ(脳ミソ?)が床が生えている…とガジェット感覚いっぱい。まさにニッポンの現代アートの活況ぶり、充実ぶりを示す「芸術祭」ではあるまいか!
を思わせる絵画、背中からキノコの生えた裸女、子どもが遊ぶような砂場が広がり、蕎麦のキノコ(脳ミソ?)が床が生えている…とガジェット感覚いっぱい。まさにニッポンの現代アートの活況ぶり、充実ぶりを示す「芸術祭」ではあるまいか!
たしか朝日新聞だったと思うが、現在「モダン」が冠される文化・芸術で、本当の意味で「モダン」なのは「モダン・アート」だけだ…という趣旨の記事を読んだことがある。その時に、なぜ自分が近年、モダン・アートに惹かれるのか、その理由がわかったような気がした。つまり、ワタシ(オヤジ)にとって「モダン」とは、「パンク!」なのだ。
パンクに革新を続けるニッポンのモダン・アートから、当分目が離せそうにない…。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


ここは廃校となった中学校の施設を活用し、アーティストが主導・運営する民設民営のスペース。こうした既存の施設を、新たなアートスペースとして活用した例といえば、今春に行われた「NO MAN'S LAND」が思い浮かぶが、あちらが旧フランス大使館の解体という期限を区切ったものに対して、こちらは地域に根ざした恒常的なアートセンターを目指すという。
それだけに施設・建物利用もこちらが一枚上で、明治以来から変わらない校舎・教室という学校文化・空間に、今も進化を続ける現代アートをマッチングさせるという妙が、じつに新鮮。校庭の跡地に緑広がる公園を配し、そこから入場すれば、どこか懐かしく、しかもモダンな異空間が広がる。
じつは会場に来る前は、「千代田」というローカルな冠詞が付いていたために、地域の趣味人が出展する学芸会的なものをイメージしていたのだが、これが大きな勘違い! 予想をはるかに超えた瞠目の展示会であった。
会場は1Fのギャラリー(元は職員室? 教室? 廊下だったなど推察しながら遊歩するのも楽しい)を利用して、19歳から70歳まで350点以上の作品がズラリと並ぶ。…だけでなく、壁を埋めつくし、天井から吊り下げられ、床に敷きつめられ…と多彩な展示。それも玉石混交ではなく、ほとんど「石」が見当たらない!
アニメ風のポップな人形が床に転がり、東南アジア風の仮面がぶら下がり、麻と布のオブジェからは内蔵(?)が飛び出し、凛とした生け花にクモの巣が絡む。キュービズムを模した粘土細工、女子高生ゴリコ
たしか朝日新聞だったと思うが、現在「モダン」が冠される文化・芸術で、本当の意味で「モダン」なのは「モダン・アート」だけだ…という趣旨の記事を読んだことがある。その時に、なぜ自分が近年、モダン・アートに惹かれるのか、その理由がわかったような気がした。つまり、ワタシ(オヤジ)にとって「モダン」とは、「パンク!」なのだ。
パンクに革新を続けるニッポンのモダン・アートから、当分目が離せそうにない…。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【写真】写真集を作る前に知っておきたい幾つかのこと ― 2010/09/20
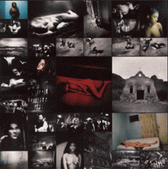
千代田アーツ3331を訪れたついでといっては何だが(失礼)、同会場の1F ラウンジ で開催されたトークセッション「写真集を作る前に知っておきたい幾つかのこと」に参加(9月18日)。
写真評論家の飯沢耕太郎氏、木村伊平衛賞を連発している赤々舎代表の姫野希美氏、丸善のバイヤー・山地恭子氏が、写真集の現在と未来、とり巻く状況などを語った2時間のトークライブで、会場にはカメラマンや編集関係者とおぼしき100人近い参加者が熱心にトークに耳を傾けた。司会は、雑誌「ecocolo」発行人で3331コーディネーターの粟田政憲氏で、ネット駆使しながら関連する事項をスクリーンに映し出しながらの進行(GJ)。
今回はレビューというよりも、以下その簡略な報告。なお各人の発言は大意で、正確でない場合もあると思うがご容赦いただきたい(敬称略)。
「写真集には一過性でない魅力がある」と飯沢が切り出せば、姫野は「写真展で写真を見るよりも、ページをめくる生理感覚で写真集が好き」として、「見たことのない写真、出会ったことのない写真」を写真集にしてきた、とその編集ポリシーを語る。
山地は書店で、どのような写真集を注文し、棚に並べるか、その部内会議の様子など内情を語る。
「写真集は写真家だけでなく、編集者やデザイナー、印刷業者などさまざまな人たちによる協同作業によってつくられる団体競技みたないなもの。だから写真家は鍛えられる」と笑いとばす飯沢だが、同時に「高い、重い、かさばる」と、“嫌われ者”の写真集の現状も指摘。
こうした状況に対しては姫野は、「『写真集を贈りたい人にプレゼントする日』をつくるなど、業界の横断的なキャンペーンやフェアや必要」と言えば、飯沢が即座に「全面的に賛成。今日からそれをやろう!」と呼応する。
ワタシが聞いてみたいと思っていた電子出版との関わりについても言及した。
「電子出版を試してみたい気持ちはある」(姫野)、「電子出版はどんどんやったらいい」(飯沢)と、電子出版に対して前向きな意見が聞かれた一方で、「電子出版に向いた写真があると思うがまだ見つけていない」(姫野)、「自分が電子出版の写真を評論する気はない」(飯沢)、「丸善に来るお客さんは年配の方が多いのでまだ現実的ではない」(山地)と、やはりまだ手さぐり状態のよう。
「まだまだ(写真集を見る)アプリがない」(飯沢)というが、ワタシだって写真集をi-phoneやi-padで見たいとは思わない。ただ、例えば現在のデジタルフォトフレームがもっと大型化し、壁かけ式になったらどうだろうか? i-padにダウンロードした写真集をフォトフレームに無線で飛ばせば、そこでプライベート写真展ができる。フォトフレームの特性よろしく写真が次々に変化していく…そんな使い方が出来るようになれば、また新たな「写真集の意味」が発見されるのではないだろうか?
あるいは、ネット上に転がる著作権フリーの画像を集めてお気に入りのデジタル写真集をつくる。それをまたネット上に公開する。ワタシは「写真集の未来」として、そんな妄想を膨らませてしまうのだが…。
後半はビールも投入され(笑)、3者のトークもますます冴えわたる。
ワタシ的には、姫野が言う「アイドル写真集はアートの棚には置かれない。アイドル写真集売り場に置かれるような写真集をつくることで、今まで写真集を興味がなかった人たちを惹きつけたい」という、マーケットを広げようとする姿勢に強い共感を覚えた。
さて最後に、会場からの質問「好きな写真集を一冊挙げたら?」への回答をここ記しておこう。
姫野… 『Vortex』 (渦) アントワーン・ダガタ
飯沢…ライアン・マクギンレー
山地…『空の名前』 高橋健司(角川書店)
高橋健司(角川書店)
↓応援クリックにご協力をお願いします。


写真評論家の飯沢耕太郎氏、木村伊平衛賞を連発している赤々舎代表の姫野希美氏、丸善のバイヤー・山地恭子氏が、写真集の現在と未来、とり巻く状況などを語った2時間のトークライブで、会場にはカメラマンや編集関係者とおぼしき100人近い参加者が熱心にトークに耳を傾けた。司会は、雑誌「ecocolo」発行人で3331コーディネーターの粟田政憲氏で、ネット駆使しながら関連する事項をスクリーンに映し出しながらの進行(GJ)。
今回はレビューというよりも、以下その簡略な報告。なお各人の発言は大意で、正確でない場合もあると思うがご容赦いただきたい(敬称略)。
「写真集には一過性でない魅力がある」と飯沢が切り出せば、姫野は「写真展で写真を見るよりも、ページをめくる生理感覚で写真集が好き」として、「見たことのない写真、出会ったことのない写真」を写真集にしてきた、とその編集ポリシーを語る。
山地は書店で、どのような写真集を注文し、棚に並べるか、その部内会議の様子など内情を語る。
「写真集は写真家だけでなく、編集者やデザイナー、印刷業者などさまざまな人たちによる協同作業によってつくられる団体競技みたないなもの。だから写真家は鍛えられる」と笑いとばす飯沢だが、同時に「高い、重い、かさばる」と、“嫌われ者”の写真集の現状も指摘。
こうした状況に対しては姫野は、「『写真集を贈りたい人にプレゼントする日』をつくるなど、業界の横断的なキャンペーンやフェアや必要」と言えば、飯沢が即座に「全面的に賛成。今日からそれをやろう!」と呼応する。
ワタシが聞いてみたいと思っていた電子出版との関わりについても言及した。
「電子出版を試してみたい気持ちはある」(姫野)、「電子出版はどんどんやったらいい」(飯沢)と、電子出版に対して前向きな意見が聞かれた一方で、「電子出版に向いた写真があると思うがまだ見つけていない」(姫野)、「自分が電子出版の写真を評論する気はない」(飯沢)、「丸善に来るお客さんは年配の方が多いのでまだ現実的ではない」(山地)と、やはりまだ手さぐり状態のよう。
「まだまだ(写真集を見る)アプリがない」(飯沢)というが、ワタシだって写真集をi-phoneやi-padで見たいとは思わない。ただ、例えば現在のデジタルフォトフレームがもっと大型化し、壁かけ式になったらどうだろうか? i-padにダウンロードした写真集をフォトフレームに無線で飛ばせば、そこでプライベート写真展ができる。フォトフレームの特性よろしく写真が次々に変化していく…そんな使い方が出来るようになれば、また新たな「写真集の意味」が発見されるのではないだろうか?
あるいは、ネット上に転がる著作権フリーの画像を集めてお気に入りのデジタル写真集をつくる。それをまたネット上に公開する。ワタシは「写真集の未来」として、そんな妄想を膨らませてしまうのだが…。
後半はビールも投入され(笑)、3者のトークもますます冴えわたる。
ワタシ的には、姫野が言う「アイドル写真集はアートの棚には置かれない。アイドル写真集売り場に置かれるような写真集をつくることで、今まで写真集を興味がなかった人たちを惹きつけたい」という、マーケットを広げようとする姿勢に強い共感を覚えた。
さて最後に、会場からの質問「好きな写真集を一冊挙げたら?」への回答をここ記しておこう。
姫野… 『Vortex』 (渦) アントワーン・ダガタ
飯沢…ライアン・マクギンレー
山地…『空の名前』
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【TV】熱海の捜査官 ― 2010/09/21

ほとんどTVドラマは観ないワタシだが、最後まで観てしまったコメディー+ミステリー+クライムドラマ『熱海の捜査官』(テレビ朝日・全8回)。放送は終了してしまったが、いずれ再放送されるだろうしDVD発売も決まっているようなので、ここで取り上げる。
バスごと4人の女子高生が失踪した事件から、3年後。うち1一人の生徒が記憶を失くしたまま生還したことで、事件解明に動きだす捜査官のオダギリジョーと栗山千明…というのがストーリーの大枠だが、何しろ登場人物がすべて怪しく異様。そこにユルいギャグと意味のないシーンが重なり、まったくの「異世界」を舞台としてドラマは進行する。
しかも、第一回からオダギリが決めゼリフ「ははぁ~、だいたいわかりました」とつぶやくので、切れ者刑事による事件解決が展開するかと思いきや、ますます混沌とし、新たな怪しい人物、事件が次々と起こる。そしてオダギリは毎回同じセリフをつぶやく…。つまり事件解明ドラマの定石から大きくハズれた「何じゃ、コレは?」という展開。、最近はこーいうテイストのドラマが流行りなのか? と怪訝に思いつつ、いつの間にかハマッた。
同じくオダギリと三木聡監督による『時効警察』を観ていないので、比較はできないが、ネットでの感想を読むと一話完結だった(らしい)『時効~』とはだいぶ趣を異にするようだ。また、TV版『ツイン・ピークス』との類似を指摘するむきも散見されたが、こちらもワタシは未見。ただし、荒唐無稽で不合理な展開に、ワタシは『マルホランド・ドライブ』を想起していたし、田中哲司扮する鑑識官の髪形がもろ『イレイザー・ヘッド』だ(笑)。ワタシが敬愛するデイヴィッド・リンチへのオマージュであることは間違いない。
で、誰もが驚かされたであろう、最終回。犯人に異論はなく、共犯者がいたことも特段に破綻はない。が、しかしあのラストをどう説明するのか? エンドロールが流れた後に、唐突に終わるこの物語は、観る者にさまざまな解釈に委ね、「異世界」のまま幕を閉じる。
それはそれでいい。ワタシだって『2001年宇宙の旅』を最初に観たときは、あのラストを説明できなかった。しかし、ドラマの展開の中でさまざまに張られた「伏線」は何だったのか、まったく説明がないまま終わってしまう。ワタシはその潔さ(?)に、驚き、呆れ、称賛を惜しまない。ニッポンのドラマの「進化」…あるいは「異化」に対して。
(ほぼ)深夜枠という自由さはあれど、ここまで「カルト」に徹して虚構をつくりあげた制作陣に拍手を送りたい。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


バスごと4人の女子高生が失踪した事件から、3年後。うち1一人の生徒が記憶を失くしたまま生還したことで、事件解明に動きだす捜査官のオダギリジョーと栗山千明…というのがストーリーの大枠だが、何しろ登場人物がすべて怪しく異様。そこにユルいギャグと意味のないシーンが重なり、まったくの「異世界」を舞台としてドラマは進行する。
しかも、第一回からオダギリが決めゼリフ「ははぁ~、だいたいわかりました」とつぶやくので、切れ者刑事による事件解決が展開するかと思いきや、ますます混沌とし、新たな怪しい人物、事件が次々と起こる。そしてオダギリは毎回同じセリフをつぶやく…。つまり事件解明ドラマの定石から大きくハズれた「何じゃ、コレは?」という展開。、最近はこーいうテイストのドラマが流行りなのか? と怪訝に思いつつ、いつの間にかハマッた。
同じくオダギリと三木聡監督による『時効警察』を観ていないので、比較はできないが、ネットでの感想を読むと一話完結だった(らしい)『時効~』とはだいぶ趣を異にするようだ。また、TV版『ツイン・ピークス』との類似を指摘するむきも散見されたが、こちらもワタシは未見。ただし、荒唐無稽で不合理な展開に、ワタシは『マルホランド・ドライブ』を想起していたし、田中哲司扮する鑑識官の髪形がもろ『イレイザー・ヘッド』だ(笑)。ワタシが敬愛するデイヴィッド・リンチへのオマージュであることは間違いない。
で、誰もが驚かされたであろう、最終回。犯人に異論はなく、共犯者がいたことも特段に破綻はない。が、しかしあのラストをどう説明するのか? エンドロールが流れた後に、唐突に終わるこの物語は、観る者にさまざまな解釈に委ね、「異世界」のまま幕を閉じる。
それはそれでいい。ワタシだって『2001年宇宙の旅』を最初に観たときは、あのラストを説明できなかった。しかし、ドラマの展開の中でさまざまに張られた「伏線」は何だったのか、まったく説明がないまま終わってしまう。ワタシはその潔さ(?)に、驚き、呆れ、称賛を惜しまない。ニッポンのドラマの「進化」…あるいは「異化」に対して。
(ほぼ)深夜枠という自由さはあれど、ここまで「カルト」に徹して虚構をつくりあげた制作陣に拍手を送りたい。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
 | 熱海の捜査官オフィシャル本 オダギリ ジョー 栗山 千明 三木 聡 テレビ朝日『熱海の捜査官』スタッフ 太田出版 2010-09-18 売り上げランキング : 29 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
 | 熱海の捜査官 三木 聡 角川書店(角川グループパブリッシング) 2010-09-18 売り上げランキング : 211 Amazonで詳しく見る by G-Tools |


最近のコメント