【LIVE】Marsh-Mallow(マーシュ・マーロウ) ― 2010/12/23

「ミングルマングルジングルベル~Marsh-Mallowのクリスマス at Starpine's cafe」と題された、Marsh-Mallow(マーシュ・マーロウ)のライブに足を運ぶ(12月22日・吉祥Starpine's cafe)。
Marsh-Mallow(マーシュ・マーロウ)は、上野洋子、猪野陽子、落合さとこ、高田みち子、丸尾めぐみ各氏5名の女性ユニット。今年5月にセカンドアルバム『mingle-mangle marsh』 をリリースしているが、じつはそこでクレジットを見るまで、「上々颱風」のメンバー陽子サン(2006年加入)がこんな“課外活動”をしているとは知らなんだ。
をリリースしているが、じつはそこでクレジットを見るまで、「上々颱風」のメンバー陽子サン(2006年加入)がこんな“課外活動”をしているとは知らなんだ。
それで、9月に行われたライブに行くつもりが、なんとチケット完売で、この日の初見となった次第。
チラシには、「珍しい楽器達を奏でユニークなコラースを響かせる、5人のおんな」とあるが、Marsh-Mallowの音楽をひとことで表せば、パーカッション+ポリフォニーコーラスの魅力、といったところか。
ステージには所狭しとさまざまな楽器が並べられているが、ピアノ、ギター、ベース、アコーディオンらはまだしも、マリンバや鉄琴(?)、そして見たこともないようなタイコ類や笛、擬音(?)奏でるものまで、さながら楽器工房の趣。
そこへ見目麗しき5人の“美女”が登場し、独特のコーラスを響かせる。いわゆる通常の、同時に異なる音を重ねてハーモニー(和声)を象(かたど)るスタイルではなく、いくつもの音(歌)を次々に歌い継ぎながら、同時に和声も協和させていくというユニークなもの。
一聴すると、打楽器を中心としたその簡素なサウンドと相まって、北欧のトラッド系音楽を思い浮かべる。
マリンバ、鉄琴伴奏によるオープニングの「雪が降っている」、続く流麗なハンドベルの「mutation」でクリスマス気分に徐々に引き込まれ、続く「真っ赤な平行線」ではアフロ風、6/8拍子(?)で彩られた「北へ」はフィンランドのヴァルテナを思わせ、「しずく」ではクラシカル風に、「雨が降っている」では明らかにピグミーのコラースを模すなど、多彩な多国籍サウンドを聴かせる。
このあたりで、カバー曲が聴きたいなと思っていた矢先に「X'mas メドレー」で賛美歌を、アンコールでジョン・レノンの「Happy X'mas 」を演ったのだが、これが意外に従来の西欧コーラスっぽくて、今イチMarsh-Mallowらしさが感じられなかった。
もう一つ意外だったのは、各種の音楽を採り入れているのに、“和モノ”がまったく聴かれず、三味線や和太鼓など和楽器伴奏によるMarsh-Mallowも聴いてみたかったな…というのがワタシの感想。
メンバーの経歴からもわかるように、みなそれぞれが長いキャリアを持ち、独自の活動をしている人ばかり。だからこそ、自身の活動にはないものを求めて、Marsh-Mallowを続けているのだと思う。全員が得意とする鍵盤楽器をあえて封印して、打楽器や弦楽器を基調にしたアンサンブルにこだわるのもそのせいかと思う。
その“女子会的”なノリは貴重であるとも思うが、なにかその「珍しい楽器達を奏でユニークなコラース」に縛られすぎて、やや窮屈な印象も受けた。
終盤にノイジーな「ドロケイごっこ」でわずかに弾けぶり垣間見せたが、例えば、先に挙げた和モノやエロクトロニカを導入するなど、もっともっと弾けた女子会パーティー芸も観てみたい気がする。
なにしろ芸達者で、ビジュアルも“華”のある人たちなのだから、音の方でも、もうひと“華”ほしい…というのが正直なところ。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


Marsh-Mallow(マーシュ・マーロウ)は、上野洋子、猪野陽子、落合さとこ、高田みち子、丸尾めぐみ各氏5名の女性ユニット。今年5月にセカンドアルバム『mingle-mangle marsh』
それで、9月に行われたライブに行くつもりが、なんとチケット完売で、この日の初見となった次第。
チラシには、「珍しい楽器達を奏でユニークなコラースを響かせる、5人のおんな」とあるが、Marsh-Mallowの音楽をひとことで表せば、パーカッション+ポリフォニーコーラスの魅力、といったところか。
ステージには所狭しとさまざまな楽器が並べられているが、ピアノ、ギター、ベース、アコーディオンらはまだしも、マリンバや鉄琴(?)、そして見たこともないようなタイコ類や笛、擬音(?)奏でるものまで、さながら楽器工房の趣。
そこへ見目麗しき5人の“美女”が登場し、独特のコーラスを響かせる。いわゆる通常の、同時に異なる音を重ねてハーモニー(和声)を象(かたど)るスタイルではなく、いくつもの音(歌)を次々に歌い継ぎながら、同時に和声も協和させていくというユニークなもの。
一聴すると、打楽器を中心としたその簡素なサウンドと相まって、北欧のトラッド系音楽を思い浮かべる。
マリンバ、鉄琴伴奏によるオープニングの「雪が降っている」、続く流麗なハンドベルの「mutation」でクリスマス気分に徐々に引き込まれ、続く「真っ赤な平行線」ではアフロ風、6/8拍子(?)で彩られた「北へ」はフィンランドのヴァルテナを思わせ、「しずく」ではクラシカル風に、「雨が降っている」では明らかにピグミーのコラースを模すなど、多彩な多国籍サウンドを聴かせる。
このあたりで、カバー曲が聴きたいなと思っていた矢先に「X'mas メドレー」で賛美歌を、アンコールでジョン・レノンの「Happy X'mas 」を演ったのだが、これが意外に従来の西欧コーラスっぽくて、今イチMarsh-Mallowらしさが感じられなかった。
もう一つ意外だったのは、各種の音楽を採り入れているのに、“和モノ”がまったく聴かれず、三味線や和太鼓など和楽器伴奏によるMarsh-Mallowも聴いてみたかったな…というのがワタシの感想。
メンバーの経歴からもわかるように、みなそれぞれが長いキャリアを持ち、独自の活動をしている人ばかり。だからこそ、自身の活動にはないものを求めて、Marsh-Mallowを続けているのだと思う。全員が得意とする鍵盤楽器をあえて封印して、打楽器や弦楽器を基調にしたアンサンブルにこだわるのもそのせいかと思う。
その“女子会的”なノリは貴重であるとも思うが、なにかその「珍しい楽器達を奏でユニークなコラース」に縛られすぎて、やや窮屈な印象も受けた。
終盤にノイジーな「ドロケイごっこ」でわずかに弾けぶり垣間見せたが、例えば、先に挙げた和モノやエロクトロニカを導入するなど、もっともっと弾けた女子会パーティー芸も観てみたい気がする。
なにしろ芸達者で、ビジュアルも“華”のある人たちなのだから、音の方でも、もうひと“華”ほしい…というのが正直なところ。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
 | mingle-mangle marsh Marsh-Mallow tildedisc 2009-05-13 売り上げランキング : 88632 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
 | 上々颱風主義 森口 秀志 上々颱風 晶文社 1994-08 売り上げランキング : 468698 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
【落語+演劇】『ラクエン!』柳家喬太郎+松村武 ― 2010/12/24

「柳家喬太郎と松村武がお贈りする落語と演劇のコラボレーション!」と、銘打たれた『ラクエン!』を観に行く(12月23日夜・天王洲 銀河劇場)。
終わってみれば、結局は“柳家喬太郎ショー”だった。やはり並みの噺家ではない。そんな感想を抱いた一夜だった。
本作は四部構成になっており、一部でまず喬太郎師匠が古典落語の「抜け雀」を演り、二部の演劇ではその後日談が展開される。休憩を挟んで三部では、別の角度からやはり後日談を新作落語で、さらに四部で演劇、最後に再び喬太郎師匠の新作という進行。
なにしろ3時間にわたる落語と演劇のコラボだ。テーマとなるしょばなの「抜け雀」は時間も関係もあるのか、師匠の高座の“お楽しみ”であるマクラもなく、いきなり本筋に。
この噺は以前、喬太郎師匠の“師匠”である柳家さん喬師匠で聴いたことがあるが、さん喬師匠のどっしりと構えた芸風を踏襲しながら、喬太郎師匠ならではの落差のある人物像、演じ分けで無難にまとめる。
まずは、本日の“お題”の提示といったところ。
それを受けての芝居は、「抜け雀」が描かれた屏風を二千両出して買いたいと申し出た小宮山家での後日譚。“籠の鳥”の生活に厭いた若殿が屏風の中に入り、自由に戯れるものの、お家の大事に屏風より出でてケレン味よろしく活躍するというもの。
再び登場した喬太郎師匠も、やはり後日譚ではあるものの、「抜け雀」で栄えたその後の宿に場面を換えて、「なぜ絵師ばかりが讃えられる?」と憤慨する屏風職人が屏風に変身してしまうというゴシック・ホラーテイストな新作。
人間屏風が空を飛んで行く描写に、会場は大爆笑。
その“しゃべる屏風”を手に入れようと探索する泥棒一家が、屏風の罠に翻弄されるマクベス的な展開から、アクション劇へと転じる芝居を挟んで、最後に〆るは喬太郎師匠。
今回のコラボはどのように創作していったのか?
これはまったくの想像だが、二部の芝居は「抜け雀」を基にした松村氏の創作。屏風師の噺も、芝居と関係なく喬太郎師匠が「抜け雀」の後日譚として創作。
そのキテレツな噺を村松氏が膨らませて芝居として揚げ、それらをすべてを引き受けて、強力(ごうりき)で壮大なイリュージョン落語にまとめ上げたのが喬太郎師匠ではなかなろうか。
それほど、このコラボを〆た最後の噺は、まさに喬太郎ワールド。喬太郎落語の真骨頂だった。
舞台は現代で、小宮山家の屏風伝説を研究する大学教授とその教え子たちを軸に話が進むのだが、なにしろ“二人”の男子学生と二股をかける女子学生と彼らの会話からして喬太郎節が全開し、時流を捉えた(外れた)ネタとリアルな言葉と形態がコロコロと転がる。
やがて、失踪した女子学生を探しに教授と男子学生は、四部の芝居に登場した“屏風墓場”に行き着き、“しゃべる屏風”と対決するのだが…。
もうここまで来ると、噺の強引な展開はどうでもよくなり(笑)、羽織を屏風に見立てるという“芸”を繰り出し、顔を真っ赤にして“屏風”になりきる喬太郎師匠。怒号撒き散らし、のたうち回り、これまでの登場実物を全て登場させて合戦を再現するという熱演。
ここで喬太郎師匠の“爆笑王”たる所以は、客の集中力が切れかかると「お客さん、怒っていませんか~!?」「この噺、もう二度と演やらないから」などと、間一髪のクスグリ(?)を入れて、客を飽きさずにそのバカバカしい世界に最後までつき合わせてしまう手練だ。
これはもう喬太郎師匠ならでは芸当だろう。
一方でワタシは、“人気劇団”という「カムカムミニキーナ」も、松村武氏の関わった芝居も未見なので何とも判然としないのだが、役者が突然唄い出して「ふるさときゃらばん」化したり、これは新国劇か!?とツッコミを入れたくなるような古くさい(失礼)演出に、これはパロディか? と脳内に?マーク浮かぶことしばし。
今までありそうでなかったコラボという意味では、面白い試みだったが、今後は芝居の中で落語が演じられるなどの“入れ子”構造にしたり、落語の中に芝居のシーンを入れ込むなどの、さらなる“ケミストリー”も期待したい。
奇才・喬太郎師匠ならば、それも可能だと思うから。
◆『ラクエン!』の参考レビュー一覧
環状日記帖
yotaro-3の日記
きーさん元気にしています
Kazooの感激記
一番ステキな体で行こう!
↓応援クリックにご協力をお願いします。


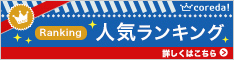

終わってみれば、結局は“柳家喬太郎ショー”だった。やはり並みの噺家ではない。そんな感想を抱いた一夜だった。
本作は四部構成になっており、一部でまず喬太郎師匠が古典落語の「抜け雀」を演り、二部の演劇ではその後日談が展開される。休憩を挟んで三部では、別の角度からやはり後日談を新作落語で、さらに四部で演劇、最後に再び喬太郎師匠の新作という進行。
なにしろ3時間にわたる落語と演劇のコラボだ。テーマとなるしょばなの「抜け雀」は時間も関係もあるのか、師匠の高座の“お楽しみ”であるマクラもなく、いきなり本筋に。
この噺は以前、喬太郎師匠の“師匠”である柳家さん喬師匠で聴いたことがあるが、さん喬師匠のどっしりと構えた芸風を踏襲しながら、喬太郎師匠ならではの落差のある人物像、演じ分けで無難にまとめる。
まずは、本日の“お題”の提示といったところ。
それを受けての芝居は、「抜け雀」が描かれた屏風を二千両出して買いたいと申し出た小宮山家での後日譚。“籠の鳥”の生活に厭いた若殿が屏風の中に入り、自由に戯れるものの、お家の大事に屏風より出でてケレン味よろしく活躍するというもの。
再び登場した喬太郎師匠も、やはり後日譚ではあるものの、「抜け雀」で栄えたその後の宿に場面を換えて、「なぜ絵師ばかりが讃えられる?」と憤慨する屏風職人が屏風に変身してしまうというゴシック・ホラーテイストな新作。
人間屏風が空を飛んで行く描写に、会場は大爆笑。
その“しゃべる屏風”を手に入れようと探索する泥棒一家が、屏風の罠に翻弄されるマクベス的な展開から、アクション劇へと転じる芝居を挟んで、最後に〆るは喬太郎師匠。
今回のコラボはどのように創作していったのか?
これはまったくの想像だが、二部の芝居は「抜け雀」を基にした松村氏の創作。屏風師の噺も、芝居と関係なく喬太郎師匠が「抜け雀」の後日譚として創作。
そのキテレツな噺を村松氏が膨らませて芝居として揚げ、それらをすべてを引き受けて、強力(ごうりき)で壮大なイリュージョン落語にまとめ上げたのが喬太郎師匠ではなかなろうか。
それほど、このコラボを〆た最後の噺は、まさに喬太郎ワールド。喬太郎落語の真骨頂だった。
舞台は現代で、小宮山家の屏風伝説を研究する大学教授とその教え子たちを軸に話が進むのだが、なにしろ“二人”の男子学生と二股をかける女子学生と彼らの会話からして喬太郎節が全開し、時流を捉えた(外れた)ネタとリアルな言葉と形態がコロコロと転がる。
やがて、失踪した女子学生を探しに教授と男子学生は、四部の芝居に登場した“屏風墓場”に行き着き、“しゃべる屏風”と対決するのだが…。
もうここまで来ると、噺の強引な展開はどうでもよくなり(笑)、羽織を屏風に見立てるという“芸”を繰り出し、顔を真っ赤にして“屏風”になりきる喬太郎師匠。怒号撒き散らし、のたうち回り、これまでの登場実物を全て登場させて合戦を再現するという熱演。
ここで喬太郎師匠の“爆笑王”たる所以は、客の集中力が切れかかると「お客さん、怒っていませんか~!?」「この噺、もう二度と演やらないから」などと、間一髪のクスグリ(?)を入れて、客を飽きさずにそのバカバカしい世界に最後までつき合わせてしまう手練だ。
これはもう喬太郎師匠ならでは芸当だろう。
一方でワタシは、“人気劇団”という「カムカムミニキーナ」も、松村武氏の関わった芝居も未見なので何とも判然としないのだが、役者が突然唄い出して「ふるさときゃらばん」化したり、これは新国劇か!?とツッコミを入れたくなるような古くさい(失礼)演出に、これはパロディか? と脳内に?マーク浮かぶことしばし。
今までありそうでなかったコラボという意味では、面白い試みだったが、今後は芝居の中で落語が演じられるなどの“入れ子”構造にしたり、落語の中に芝居のシーンを入れ込むなどの、さらなる“ケミストリー”も期待したい。
奇才・喬太郎師匠ならば、それも可能だと思うから。
◆『ラクエン!』の参考レビュー一覧
環状日記帖
yotaro-3の日記
きーさん元気にしています
Kazooの感激記
一番ステキな体で行こう!
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【映画】マイケル・ジャクソン THIS IS IT ― 2010/12/25

遅まきながら、『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』(2009年・監督:ケニー・オルテガ)をテレビ放映で鑑賞。
本作をひとことで言うならば、“マイケル・ジャクソンのつくり方”、メイキング・オブ・MJステージを描いたドキュメンタリーといえる。
というのも、本作でのステージ・シーンはすべてリハーサル映像・音声であって、“本番”の記録はジャクソン5時代などの“過去”のものしか使われていない。
つまり天才パーフォーマーであるマイケル・ジャクソンが、あまたのスタッフを率いて、どのようにそのステージ・パフォーマンスをつくり上げていくのか、それを克明に繙(ひもと)いた映画なのだ。
冒頭、マイケルの急逝によって幻となったロンドン公演「THIS IS IT」に向けて、ダンサーたちのオーディション風景が現れる。そこからカメラは一気にリハーサル風景へとなだれ込み、あとはひたすらマイケルの一挙手一投足が映し出される。
例えば、オープニングの「Wanna Be Startin' Somethin' 」(だったと思うが…)では、4種の衣装をまとったマイケルが歌い、踊る様が繋ぎ合わされている。つまり、この曲の衣装だけで、4パターンの衣装案があったということであり、それだけ細かく演出案を重ねていることがわかる。
一般的に、アーティストがコンサート・ステージにどの程度関与しているのかワタシには比較する見聞がないのだが、本作を観るといかにマイケルがステージ全般の演出・構成・音楽・映像すべてに関わっているかがわかる。
先のダンサー・オーディションの審査にしても然り。バンド・メンバーに演奏の強弱を細かく指示する様はまさにコンダクターだし、ステージの立ち位置やきっかけまでにまでアイデアを提供する。
しかも、アイデアを出した後に、すぐさま自身が魅力的な振り付けをして踊ってみせるのだから、現場ではいかにも説得力があるやに違いない。
コンサート中に流される映像作品のチェックでも、監督と一緒になって嬉々として役者の動きに反応する。
その姿は、キング・オブ・ポップスというよりもキング・オブ・パーフォーマー…。
最強の現場監督であり、演出家であり、そしてパーフォーマー。ここでのマイケルは、それらすべてを一人でやってのけているかのように見える。
終盤の「Billie Jean 」では、マイケルの素晴らしい即興ダンスにスタッフたちが歓喜する姿が映し出される。その高揚感に溢れる現場に、ワタシたちもそこに居合わせたかのような錯覚に陥り、この稀代のパーフォーマーの早逝に改めて慚愧(ざんき)の念を抱く。
巨大なステージ、華麗ですご腕のバック・バンド、壮観たるダンサーたち、「火のチェイス」に「3Dスリラー」映像と、この「THIS IS IT」コンサートに用意された演出やスタッフ陣を絵巻のように見せられて、改めてこの豪華なエンターテイメント・ショーの壮大さがわかるというもの。
1992年の東京公演(Dangerous World Tour)に足を運んだものの、じつはほとんどその印象が残っていないワタシだが、たしかに本作は、この「THIS IS IT」は観てみたいと思わせるオーラを感じさせる“未完の予告編”となっている。
さらに本作の成功によって、この“ステージのメイキング”という手法は、今後の音楽ソフトの鉱脈になるのではないかという感すら抱かせる。
すでに、過去の“名盤のつくり方”を振り返ったドキュメンタリーDVD がシリーズ化されているが、同じように“伝説のステージ”のメイキング映像を編み直すことで、アーティストやその音楽の魅力にさらに光を当てることができるのではないだろうか?
がシリーズ化されているが、同じように“伝説のステージ”のメイキング映像を編み直すことで、アーティストやその音楽の魅力にさらに光を当てることができるのではないだろうか?
もちろんその前提として、リハーサル映像の記録と、マイケルに比するアーティスト・パワーが求められることは言うまでもないが…。
◆『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』の参考レビュー一覧
超映画批評(前田有一氏)
映画.com(清水節氏)
映画のメモ帳+α
映画通信シネマッシモ(渡まち子氏)
映画ジャッジ!(福本次郎氏)
LOVE Cinemas 調布
戦略財務の社長・実島誠のブログ
映画瓦版
堀江貴文オフィシャルブログ
↓応援クリックにご協力をお願いします。


本作をひとことで言うならば、“マイケル・ジャクソンのつくり方”、メイキング・オブ・MJステージを描いたドキュメンタリーといえる。
というのも、本作でのステージ・シーンはすべてリハーサル映像・音声であって、“本番”の記録はジャクソン5時代などの“過去”のものしか使われていない。
つまり天才パーフォーマーであるマイケル・ジャクソンが、あまたのスタッフを率いて、どのようにそのステージ・パフォーマンスをつくり上げていくのか、それを克明に繙(ひもと)いた映画なのだ。
冒頭、マイケルの急逝によって幻となったロンドン公演「THIS IS IT」に向けて、ダンサーたちのオーディション風景が現れる。そこからカメラは一気にリハーサル風景へとなだれ込み、あとはひたすらマイケルの一挙手一投足が映し出される。
例えば、オープニングの「Wanna Be Startin' Somethin' 」(だったと思うが…)では、4種の衣装をまとったマイケルが歌い、踊る様が繋ぎ合わされている。つまり、この曲の衣装だけで、4パターンの衣装案があったということであり、それだけ細かく演出案を重ねていることがわかる。
一般的に、アーティストがコンサート・ステージにどの程度関与しているのかワタシには比較する見聞がないのだが、本作を観るといかにマイケルがステージ全般の演出・構成・音楽・映像すべてに関わっているかがわかる。
先のダンサー・オーディションの審査にしても然り。バンド・メンバーに演奏の強弱を細かく指示する様はまさにコンダクターだし、ステージの立ち位置やきっかけまでにまでアイデアを提供する。
しかも、アイデアを出した後に、すぐさま自身が魅力的な振り付けをして踊ってみせるのだから、現場ではいかにも説得力があるやに違いない。
コンサート中に流される映像作品のチェックでも、監督と一緒になって嬉々として役者の動きに反応する。
その姿は、キング・オブ・ポップスというよりもキング・オブ・パーフォーマー…。
最強の現場監督であり、演出家であり、そしてパーフォーマー。ここでのマイケルは、それらすべてを一人でやってのけているかのように見える。
終盤の「Billie Jean 」では、マイケルの素晴らしい即興ダンスにスタッフたちが歓喜する姿が映し出される。その高揚感に溢れる現場に、ワタシたちもそこに居合わせたかのような錯覚に陥り、この稀代のパーフォーマーの早逝に改めて慚愧(ざんき)の念を抱く。
巨大なステージ、華麗ですご腕のバック・バンド、壮観たるダンサーたち、「火のチェイス」に「3Dスリラー」映像と、この「THIS IS IT」コンサートに用意された演出やスタッフ陣を絵巻のように見せられて、改めてこの豪華なエンターテイメント・ショーの壮大さがわかるというもの。
1992年の東京公演(Dangerous World Tour)に足を運んだものの、じつはほとんどその印象が残っていないワタシだが、たしかに本作は、この「THIS IS IT」は観てみたいと思わせるオーラを感じさせる“未完の予告編”となっている。
さらに本作の成功によって、この“ステージのメイキング”という手法は、今後の音楽ソフトの鉱脈になるのではないかという感すら抱かせる。
すでに、過去の“名盤のつくり方”を振り返ったドキュメンタリーDVD
もちろんその前提として、リハーサル映像の記録と、マイケルに比するアーティスト・パワーが求められることは言うまでもないが…。
◆『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』の参考レビュー一覧
超映画批評(前田有一氏)
映画.com(清水節氏)
映画のメモ帳+α
映画通信シネマッシモ(渡まち子氏)
映画ジャッジ!(福本次郎氏)
LOVE Cinemas 調布
戦略財務の社長・実島誠のブログ
映画瓦版
堀江貴文オフィシャルブログ
↓応援クリックにご協力をお願いします。
 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT(1枚組通常盤) マイケル・ジャクソン ジャクソンズ SMJ 2009-10-28 売り上げランキング : 230 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
【本】激変!日本古代史 卑弥呼から平城京まで ― 2010/12/26
 | 激変! 日本古代史 卑弥呼から平城京まで (朝日新書) 足立倫行 朝日新聞出版 2010-10-13 売り上げランキング : 13217 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
その足立氏が今回、題材として取り組んだのが「日本古代史」。
その動機について、氏はこう記している。
生まれ故郷である鳥取市境港で発見された「妻木晩田遺跡」の保存活用・検討委員に任命された氏に、やがて「『古代史は面白そうだ』という意識が芽生え」、日本古代史に関する著作を読み漁る一方で、遺跡やシンポジウムに足を運ぶなどを「数年続けているうちに、私は行き詰まってしまった」のだという。
「見聞を広め、新たな知識を得るたびに、古代史に関する情報は増えていく。けれどもそれらは、異なる時代の異なる事象に関するバラバラの知識であり、いつまでたってもひとつながりの“歴史のうねり”のようなものが感得できないのだ」---。
この感覚は、「この分野の情報の洪水に戸惑っている人」たちの多くが、共感できるものではないだろうか。
そして、「そういう古代史ファンの頭の整理や、次の段階への知的飛躍のために」本書は「多少はお役に立てる」べくというのが、そもそもの執筆動機のようである。
その手法は、「現場の発掘調査担当者の言葉に一番感銘を受けた」という氏が「原点に戻ろう!」とするもので、「テーマに沿って各地の発掘担当者を訪ねて歩いて話を聞き、合間に新旧の情報を入れて落差を埋め、私なりに細くても意味のある補助線を弾いて、歴史の流れに近いものを確認」するというものだ。
さて、それではその氏の“試み”は、うまく成就したであろうか?
本書は9章から成り、それぞれ卑弥呼、ヤマト王権、邪馬台国と、ここ数年来の古代史トピックスともいうべきキャッチーな話題が並び、さらに邪馬台国九州説、『日本書記』と聖徳太子の真偽、大化改新の「真相」、伊勢神宮の謎に迫っていく。
いずれも、ワタシのような歴史オンチでも見聞きした覚えのある事象で、その選択眼はさすがにバランスが取れている。問題はその内容だ。
足立氏も本書をまとめるにあたって相当苦労したと思う。
なにしろ「情報の洪水」だ。何をどうすれば、読者にわかりやすく伝えられるか、苦心されたに違いない。
たしかに、遺跡や博物館の画像を多く掲載し、研究者や取材者だけでなく、一般の古代史ファンが訪れることのできる場所や展示物を紹介するなど、工夫を凝らしている。
しかながら、それでもワタシのような「門外漢」には、本書はまだ読みにくい。一読して頭の中で“歴史のうねり”が見えてこないのだ。
例えば、邪馬台国に「畿内説」と「九州説」があるのはさすがのワタシも識っているが、「考古学界で『邪馬台国=畿内説』が圧倒的に優勢」なのかが、よくわからない。
できれば、双方の論者がそう主張する論点を表組か何かでわかりやすく示してもらえなかったものか…。
あるいは、「『日本書紀』をドラマティックに否定する馬子=大王説と、『日本書紀』に基づく現在の説は、真っ向から対立する」としているのだから、その前提となる「『古事記』や『日本書紀』は、その記述をどこまで史実として信頼できるのだろうか?」とするポイントも、もう少しわかりやすく明示してほしかった。
もちろんこうしたイチャモンは、「古代史」に対するあまりに無知なワタシに非があるのやもしれず、「古代史」ファンの本書の評価はまた違ったものになるかもしれない。
ワタシはすっかり「渡来人」だと思い込んでいた蘇我氏にしても、「渡来人説もあるものの、根拠に乏しい」といった、見聞を新たにする記述も少なからずあり、それなりに勉強になった。
一方で、古代史研究において長年にわたって議論となっている「天皇陵」の調査・発掘問題について、まったく触れられていない点も気になった。
なので、こうした本こそ新たな情報や論点を適宜加え、「激変!」をヴィヴィットに伝える生きた書物として、“電子版”の刊行が望まれるのではないだろうか?
ワタシは、そうしてブラッシュアップした本書をもう一度読んでみたい。
◆『激変!日本古代史』の参考レビュー一覧
図書新聞(小嵐九八郎氏)
9892
読書日記
雑記帳
東洋経済(書評)
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【映画】借りぐらしのアリエッティ ― 2010/12/27

『借りぐらしのアリエッティ』(2010年・監督:米林宏昌)
英児童文学の『床下の小人たち』 を、舞台を50年代のイギリスから現代の日本に移して、現代のお伽話に仕立てた作品。宮崎駿企画・脚本のジブリ映画として、本年夏に“お約束”の大ヒットを記録したことは記憶に新しい。
を、舞台を50年代のイギリスから現代の日本に移して、現代のお伽話に仕立てた作品。宮崎駿企画・脚本のジブリ映画として、本年夏に“お約束”の大ヒットを記録したことは記憶に新しい。
なにしろ茅葺きの日本の古い民家が舞台なのに、内部はとても洒落た洋館。しかも、小人の名前は「アリエッティ」なのだがら、これはもう提示されたファンタジー世界に浸るしかない。
例によって精巧・緻密に描かれたジブリ・アニメの世界は、まるでポップアップ絵本の如く、きらびやかに拡がる。
しかしながら、『ガリバー旅行記』を持ち出すまでもなく、えてして“寓話”の多くは、毒を孕んだ物語であることが少なくない。
本作もその例外ではなく、現代社会に蔓延するさまざまな問題を暗喩・照射した作品であることは間違いない。なにしろ「小人たち」の存在からして、ヒトに寄生して生きる「借りぐらし」の種族なのだ。
その田舎の民家に、少年が祖母と共にやってくることから物語は始まるのだが、いきなり冒頭でアリエッティと遭遇し、その後小人一家の生活ぶりが丹念に描かれるという展開に、まず驚いた。
『となりのトトロ』では、越してきた家族たちとトトロ一家との“出会い”を、謎と期待感をたっぷりと含ませながら描いた宮崎監督だが、ここではやけにあっさりとそのカタルシスを放棄する。
そのかわり、小人一家の生活を丹念になぞることで、ワタシたちもまた「小人」となって、ヒト社会を覗き見ることができる。
物語はアリエッティと少年との接触によって、ヒトにその存在を知られてはならない小人一家のエクソダスへと転がっていくのだが、そこには当然の如くアリエッティと少年の“成長物語”がバックボーンとして強く描かれる。
おそらくこれは、本作に対する多くの批評・評論で指摘されていることだと思うが、ジブリ映画を体験してきたワタシたちはそこに、いくつもの名作ジブリ群の幻影を見てしまう。
アリエッティと少年との“共闘”は『天空の城ラピュタ』であるし、少年の肩に乗った姿は、まるで「シータ」とラピュタ・ロボットだ。
それだけでなく、気丈ながら傷つきやすいアリエティの“成長”は、『魔女の宅急便』の「キキ」のそれだし、ひらりひらりと見事な身体能力の高さでヒト社会を行き来するそれは、いやがうえにも「ナウシカ」を想起させる。アリエッティ膝の上で丸くなる団子虫は、王蟲(オーム)の幼虫のパロディかと思えるほど。
ほかにも、アリエッティと少年を交信する猫は、「ネコバス」を彷彿させ、二人の別れのシーンは『耳をすませば』の舞台を思わせる。
さらに、野性的な小人族の「スピラー」は男女の違いはあれど『もののけ姫』の「サン」か。そもそも、ヒトと小さき者という相いれない存在が、『もののけ姫』の設定と相似してやまない。
しかし、本作の登場人物たちは、ナウシカのように飛翔はしないし、パズーやシータのようなめくるめく冒険には旅立たない。
冒頭で記したように、ここでワタシたちが読む物語は、美しくもホロ苦い成熟したオトナの絵本だ。
宮崎監督が1979年に『ルパン三世 カリオストロの城』でアニメ・ファンを狂喜させてから30年。あの血沸き肉踊り、やがて深淵なる思いを抱く、神話的な宮崎ジブリ映画をもうワタシたちは、享受することができないだろうか…。
宮崎スピリット溢れる、そのチルドレンの本作を堪能した後さえも、その寂しさは拭いきれずにいる。
◆『借りぐらしのアリエッティ』の参考レビュー一覧
超映画批評(前田有一氏)
映画的・絵画的・音楽的
未完の映画評
映画.com(清水節氏)
映画通信シネマッシモ
内田樹の研究室
アニメ!アニメ!(氷川竜介氏)
みたいもん!
masalaの辛口映画館
LOVE Cinemas 調布
映画ジャッジ!(福本次郎氏)
【徒然なるままに・・・】
リアルライブ(コダイユキエ氏)
CINRA.NET(小泉凡氏インタビュー)
英児童文学の『床下の小人たち』
なにしろ茅葺きの日本の古い民家が舞台なのに、内部はとても洒落た洋館。しかも、小人の名前は「アリエッティ」なのだがら、これはもう提示されたファンタジー世界に浸るしかない。
例によって精巧・緻密に描かれたジブリ・アニメの世界は、まるでポップアップ絵本の如く、きらびやかに拡がる。
しかしながら、『ガリバー旅行記』を持ち出すまでもなく、えてして“寓話”の多くは、毒を孕んだ物語であることが少なくない。
本作もその例外ではなく、現代社会に蔓延するさまざまな問題を暗喩・照射した作品であることは間違いない。なにしろ「小人たち」の存在からして、ヒトに寄生して生きる「借りぐらし」の種族なのだ。
その田舎の民家に、少年が祖母と共にやってくることから物語は始まるのだが、いきなり冒頭でアリエッティと遭遇し、その後小人一家の生活ぶりが丹念に描かれるという展開に、まず驚いた。
『となりのトトロ』では、越してきた家族たちとトトロ一家との“出会い”を、謎と期待感をたっぷりと含ませながら描いた宮崎監督だが、ここではやけにあっさりとそのカタルシスを放棄する。
そのかわり、小人一家の生活を丹念になぞることで、ワタシたちもまた「小人」となって、ヒト社会を覗き見ることができる。
物語はアリエッティと少年との接触によって、ヒトにその存在を知られてはならない小人一家のエクソダスへと転がっていくのだが、そこには当然の如くアリエッティと少年の“成長物語”がバックボーンとして強く描かれる。
おそらくこれは、本作に対する多くの批評・評論で指摘されていることだと思うが、ジブリ映画を体験してきたワタシたちはそこに、いくつもの名作ジブリ群の幻影を見てしまう。
アリエッティと少年との“共闘”は『天空の城ラピュタ』であるし、少年の肩に乗った姿は、まるで「シータ」とラピュタ・ロボットだ。
それだけでなく、気丈ながら傷つきやすいアリエティの“成長”は、『魔女の宅急便』の「キキ」のそれだし、ひらりひらりと見事な身体能力の高さでヒト社会を行き来するそれは、いやがうえにも「ナウシカ」を想起させる。アリエッティ膝の上で丸くなる団子虫は、王蟲(オーム)の幼虫のパロディかと思えるほど。
ほかにも、アリエッティと少年を交信する猫は、「ネコバス」を彷彿させ、二人の別れのシーンは『耳をすませば』の舞台を思わせる。
さらに、野性的な小人族の「スピラー」は男女の違いはあれど『もののけ姫』の「サン」か。そもそも、ヒトと小さき者という相いれない存在が、『もののけ姫』の設定と相似してやまない。
しかし、本作の登場人物たちは、ナウシカのように飛翔はしないし、パズーやシータのようなめくるめく冒険には旅立たない。
冒頭で記したように、ここでワタシたちが読む物語は、美しくもホロ苦い成熟したオトナの絵本だ。
宮崎監督が1979年に『ルパン三世 カリオストロの城』でアニメ・ファンを狂喜させてから30年。あの血沸き肉踊り、やがて深淵なる思いを抱く、神話的な宮崎ジブリ映画をもうワタシたちは、享受することができないだろうか…。
宮崎スピリット溢れる、そのチルドレンの本作を堪能した後さえも、その寂しさは拭いきれずにいる。
◆『借りぐらしのアリエッティ』の参考レビュー一覧
超映画批評(前田有一氏)
映画的・絵画的・音楽的
未完の映画評
映画.com(清水節氏)
映画通信シネマッシモ
内田樹の研究室
アニメ!アニメ!(氷川竜介氏)
みたいもん!
masalaの辛口映画館
LOVE Cinemas 調布
映画ジャッジ!(福本次郎氏)
【徒然なるままに・・・】
リアルライブ(コダイユキエ氏)
CINRA.NET(小泉凡氏インタビュー)
【CD】Bellowhead(ベロウヘッド)/Hedonism ― 2010/12/28
 | Hedonism Bellowhead Navigator 2010-10-04 売り上げランキング : 116824 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
音楽評論家の五十嵐正氏の記事(ミュージック・マガジン12月号)を目にするまで、寡聞にしてワタシもこのバンドの存在は知らなかったのだが、最新作『Hedonism』(2010年)を一聴して、その魅力に惹きつけられた。
2004年英国デビューの同バンドは11人編成で、各自がギター、ブズーキ、フィドル、パイプス(笛)、フィドル、オーボエ、チェロ、フィドル、パーカッション、サックス、トランペット、トロンボーン、チューバといったさまざまな楽器を持ちかえて演奏する。
なんといってもこのバンドの新味は、通常ギターやフィドルを中心とするトラッドに、大胆に管弦楽器の導入したことで、その勢いあるブラスセクションは東欧のクレッツマーを彷彿させ、ストリングスはまるでオーケストラのように鳴り響く。通常のトラッドには収まりきらない、ダイナミックでミクスチャーなサウンドが魅力になっている。
本CDに収録された全11曲のうち9曲がトラッドだが、冒頭の①「New York Girls」からしてノリノリの出来。ブラスが冴える②「A-Begging I Will Go」、ポルカなインスト曲③「Cross-Eyed And Chinless」を挟んで、クラシカルな響きで始まるドラマティックなナンバー④「Broomfield Hill」へと続く。
ニューオリンズのブラス・バンドも思わせるボトムの効いた⑤「The Hand Weaver And The Factory Maid」ではストリングが大胆に挿入され、⑥「Captain Wedderburn」はメランコリックに、シャンソンの偉人・ジャック・ブレル作の⑦「Amsterdam」はドラスティックに謡いあげる。
⑧「Cold Blows The Wind」は猛々しく、⑨「Parson's Farewell」はダンサンブルに、まるでパンクな⑩「Little Sally Racket」…といった具合にそのサウンドはじつに多彩だ。
BBCラジオのフォーク・アワードで最優秀ライヴ・アクトに何度も選ばれているというからには、ライヴで本領を発揮するバンドなのだろうが、その勢いと高揚感は見事にこのCDにもパッケージされているように思える。
大編成でのスタジオ・ライヴ録音にするために、あのアビーロード・スタジオを選び、その広いスタジオで空間を生かした録音がなされたことも功を奏したようだ。
*参照:「New York Girls」のYou Tube映像↓
メンバーが勢揃いしたジャケット写真も、かつてのデラニー&ボニー&フレンズやジョー・コッカー マッド・ドッグス&イングリッシュメン
ぜひともそのライヴを観(聴い)てみたい注目のバンドにして、必聴の一枚。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【映画】荷車の歌 ― 2010/12/30

『荷車の歌』(1959年・監督:山本薩夫)
山本薩夫監督の名作群から、その代表作を以下に挙げてみる。
組織暴力に抵抗する人びとを描いた『暴力の街』(1950年)、戦争の残酷さを告発した『真空地帯』(1952年)、医学会にメスを入れた『白い巨塔』(1966年)、壮大なドラマとなった『戦争と人間(1970~73年)、金融界の内幕を暴いた『華麗なる一族』(1974年)、構造汚職に切り込んだ『金環蝕』(1975年)、政財界の内幕を描く『不毛地帯』(1976年)…。
どうだろう、その骨太な作風が目に浮かんでくるのではないだろうか。
その山本監督の作風が遺憾なく発揮されているのが本作だ。
冒頭からしてイタリアのネオ・リアリズム運動の影響を受けた、役者の汗が飛び散るかのような迫真の映像で、この物語を繙(ひもとき)始める。
時は明治時代。広島県の山村の娘セキ(望月優子)は、郵便配達夫の茂市(三國連太郎)と夫婦(めおと)となるが、すぐに「荷車引き」となって夫と茂市の老いた母(岸輝子)を支える。やがて2男、2女に恵まれるが、姑の“いびり”や夫の浮気に苦しめられ、さらに戦争や時代の流れに翻弄され続ける…。
全国の農村婦人のカンパによって制作されたというのもさもありなん。姑との関係をはじめ、これでもかというくらいに農家の嫁の苦難が“リアル”に描かれる。全国で上映運動されたというが、おそらく同時代の農村女性に大きな共感を呼んだであろうことは想像に難くない。
少々意地の悪い母親を演(や)らせたらピカ一の望月は、ここでは徹底して耐え忍ぶ女を演じ、時に若き日のリノ・ヴァンチュラを彷彿させる三國は、ひたすら情けない男になり切って20~70代までを演じ切る。
もちろん本作を傑作としているのは、そうした物語やディテールの“リアル”さだけではない。背景に大きな自然をたたえたその画面に、明治・大正・昭和へと激流する時代に抗う、ちっぽけなその人間の存在を置くことで、“映画的なるもの”への深みを照らし出す。
なんといってもラストの映像が素晴らしい。
孫たちに囲まれ、人生の終盤となってようやく安寧を手にいれたセキ。 そこへ、(ネタバレになるが)戦争で死んだはずの息子が帰還する。…息子に駆け寄るセキ。
それを山本監督とはなんと“引き”で撮ってみせた。
そこに、セキの表情は写らない。しかし、田舎道で結ばれる母子の姿をとらえたロングショットからは、セキの歓喜がみるみると溢れだしていく…。
これこそが、フィルム撮影によるスクリーン上映を前提とする作品=映画における“マジック”だとワタシは思うのだ。
◆『荷車の歌』の参照レビュー一覧
芸の不思議、人の不思議
Augustrait
アスカ・スタジオ
字幕翻訳者の戯言
↓応援クリックにご協力をお願いします。


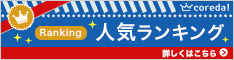

山本薩夫監督の名作群から、その代表作を以下に挙げてみる。
組織暴力に抵抗する人びとを描いた『暴力の街』(1950年)、戦争の残酷さを告発した『真空地帯』(1952年)、医学会にメスを入れた『白い巨塔』(1966年)、壮大なドラマとなった『戦争と人間(1970~73年)、金融界の内幕を暴いた『華麗なる一族』(1974年)、構造汚職に切り込んだ『金環蝕』(1975年)、政財界の内幕を描く『不毛地帯』(1976年)…。
どうだろう、その骨太な作風が目に浮かんでくるのではないだろうか。
その山本監督の作風が遺憾なく発揮されているのが本作だ。
冒頭からしてイタリアのネオ・リアリズム運動の影響を受けた、役者の汗が飛び散るかのような迫真の映像で、この物語を繙(ひもとき)始める。
時は明治時代。広島県の山村の娘セキ(望月優子)は、郵便配達夫の茂市(三國連太郎)と夫婦(めおと)となるが、すぐに「荷車引き」となって夫と茂市の老いた母(岸輝子)を支える。やがて2男、2女に恵まれるが、姑の“いびり”や夫の浮気に苦しめられ、さらに戦争や時代の流れに翻弄され続ける…。
全国の農村婦人のカンパによって制作されたというのもさもありなん。姑との関係をはじめ、これでもかというくらいに農家の嫁の苦難が“リアル”に描かれる。全国で上映運動されたというが、おそらく同時代の農村女性に大きな共感を呼んだであろうことは想像に難くない。
少々意地の悪い母親を演(や)らせたらピカ一の望月は、ここでは徹底して耐え忍ぶ女を演じ、時に若き日のリノ・ヴァンチュラを彷彿させる三國は、ひたすら情けない男になり切って20~70代までを演じ切る。
もちろん本作を傑作としているのは、そうした物語やディテールの“リアル”さだけではない。背景に大きな自然をたたえたその画面に、明治・大正・昭和へと激流する時代に抗う、ちっぽけなその人間の存在を置くことで、“映画的なるもの”への深みを照らし出す。
なんといってもラストの映像が素晴らしい。
孫たちに囲まれ、人生の終盤となってようやく安寧を手にいれたセキ。 そこへ、(ネタバレになるが)戦争で死んだはずの息子が帰還する。…息子に駆け寄るセキ。
それを山本監督とはなんと“引き”で撮ってみせた。
そこに、セキの表情は写らない。しかし、田舎道で結ばれる母子の姿をとらえたロングショットからは、セキの歓喜がみるみると溢れだしていく…。
これこそが、フィルム撮影によるスクリーン上映を前提とする作品=映画における“マジック”だとワタシは思うのだ。
◆『荷車の歌』の参照レビュー一覧
芸の不思議、人の不思議
Augustrait
アスカ・スタジオ
字幕翻訳者の戯言
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【本】誰も国境を知らない--揺れ動いた「日本のかたち」をたどる旅 ― 2010/12/31
 | 誰も国境を知らない―揺れ動いた「日本のかたち」をたどる旅 西牟田 靖 情報センター出版局 2008-09-26 売り上げランキング : 52693 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
日本の「国境」に位置する知られざる島々を、自身の目と足で確認するというノンフィクション・ジャーナリズムに立ち返った力作だ。
著者が旅したのは、北は国後島、色丹島から、南は沖ノ鳥島、硫黄島、小笠原諸島、そして西は与那国島、尖閣諸島、そして北西は対馬、竹島に至る島々。
その取材手法はいわゆる紀行文に類するものだが、副題に「揺れ動いた『日本のかたち』をたどる旅」とあるように、ワタシたちは著者の案内によって、“揺れ動いた「日本かたち」”を確認する旅へと誘われるのだ…。
「知床半島までは小型のボートで往復できる距離」にある「国後島」へ、サハリン・ルートから訪れた著者は、「日本のゴミが流れ着き、島にアンテナがなくても(日本に)形態電話が通じる」事実に興奮する一方で、「ゴミと電波がいとも簡単に越えられる海峡を、人だけは面倒な手続きを経なければ越えられない」ことに、複雑な思いを抱く…。
また、洋上には観測施設が浮かび、コンクリートで覆われた“岩”である「沖ノ鳥島」を目にした著者は、「そこが日本の領土であるという感慨と、二つの島に施された『延命治療』に対する疑問--」という、「相反する思いの間で振り子のように心が揺れ動くの」と、素直にその心情を吐露する。
そして、韓国側から「日本人であること隠して」上陸した「竹島」では、その“実行支配”の様を、「沖ノ鳥島の風景とどこか共通する印象があるのだ。どちらも国が実行支配をたしかなものにするために、本来持っていた人の定住を拒む厳しい環境に手を加え、一変させてしまった風景である」ととらえ、「日本と韓国では島への情熱や手間のかけ方にいまや天と地ほどの隔たりができてしまった」と、指摘する。
その著者の姿勢は、特定のイデオロギーにとらわれず、じつにフラットにその“現実”を見つめようとするものだ。
韓国人ツアーに混じっての「対馬」の旅もじつに興味深く、抗日運動家・崔益鉉(チェイクヒョン)の碑など、ワタシも知らないことだらけ。この島が、韓日の歴史をつなぐ要地であったことを、改めて知る。
ワタシが実際に訪れたことのある小笠原や与那国にしてもそうで、小笠原では統治者が替わることで翻弄されてきた家族の苦難の歴史が語られ、大琉球時代を思わせる与那国と台湾の親密な関係も「この島は国境が消えると栄えるし、できるとしぼむ」という島民の言葉に、やはり翻弄される島の歴史が明らかにされる。
いずれも著者の、丹念な取材とインタビューによって、その島の過去と今の暮らしが、くっきりと姿を現す。
とりわけ、さまざまな困難をはねのけての尖閣諸島への旅は、今に至る島そのものが持つ苦難の歴史と相まって、感動的ですらある。
まさしく、百聞は一見に如かず。
そこで著者が視たのは、「『国境の島』の不自然なありよう」だ。
著者は言う。「『国境の島』には実にさまざまで複雑な現実」があり、「ヒトとクニの歴史が交差し現実へとつながる場所だった」と。そして、「『国境の島』を直視することで見えるもうひとつの日本の姿」を晒(さら)しだす試みが本書であった、と。
本書は5年にわたる歳月をかけて書き上げられたものだ。雑誌取材を基にした原稿ではあるものの、そこに著者が注ぎ込んだ時間と労力、資金を思んばかれば、改めてこの労作には頭が下がるばかり。
同時に、本来ならばこうした仕事は、取材も資金力もある新聞やテレビ・ジャーナリズムが率先して行うべきものではなかったか…。
時代の記録という面でも、大きな意味のある仕事だと思う。
◆『誰も国境を知らない』の参考レビュー一覧
asahi.com(重松清氏)
日経ビジネス オンライン書評(朝山実氏)
アジアの真実
ミステリ読みまくり日記
↓応援クリックにご協力をお願いします。


最近のコメント