【芸能・落語】浪花ぶし 澤孝子の世界 ― 2011/08/24

これはいい企画だ。
当代きっての人気落語家・柳家喬太郎師匠がナビゲーターとなって、浪花節の世界を案内するという「浪花ぶし 澤孝子の世界」(8月23日・博品館劇場)を堪能した。
おそらくメイン・ターゲットは落語ファンなのだろう。ふだんは木馬亭でしか聴けない浪花節をおしゃれな(?)銀座にもってきての公演。これは「澤孝子氏の芸に圧倒された」という喬太郎師匠の計らいか?
というもの、落語好きならば講談を聞く機会はあっても、じつは近しい芸であるはずの浪花節をナマで聞いたことのある人は意外と少ないのではないだろうか。かくいうワタシもつい最近になって、浪花節に開眼したばかり…。
そういう意味でも鈴々舎風車による浪花節解説を冒頭にもってきたのもよかったし、ふだんは声を聞くこともない曲師(佐藤貴美江氏)にマイクに向けて、伴奏者から観た浪花節の魅力を伝えたのもよかった。
孝子×喬太郎対談も、両者さすがに堂にいったもので、二人の語りだけで「芸」になっていて、たっぷりと会場を沸かせる。
で、孝子氏の弟子である澤雪絵が露払いを務め、まずは語り始めたが、この人は高音に魅力がある。語りも低音部の唸りもまだまだだが、今後ののびしろが感じられる舞台。
もはやいつどこに出ても、何にも怖くない喬太郎師匠は、季節ネタをもってきた。四谷怪談をモチーフにしつつつもブラックジョークの効いた「お菊の皿」。かつてのこのネタを春風亭昇太師匠で聞いて、現代落語の魅力に憑りつかれワタシだが、さすがは喬太郎師匠。それをはるかに上回る面白さ、凄まじさ。今ドキ風若者からお菊の豹変する形態まで、ハチャメチャに演じわけ、観客の気持ちをガッチリ掴む。
立川志らく師匠は近著『落語進化論』 (新潮社)で、喬太郎師匠にも触れて「名人の基準は『江戸の風を吹かせられるか』にある」としているが、ワタシは「江戸の風」なんぞより、そよ風から台風まで変幻自在に吹かせまくる喬太郎師匠のふれ幅の大きな“喬風”が好きだ。
(新潮社)で、喬太郎師匠にも触れて「名人の基準は『江戸の風を吹かせられるか』にある」としているが、ワタシは「江戸の風」なんぞより、そよ風から台風まで変幻自在に吹かせまくる喬太郎師匠のふれ幅の大きな“喬風”が好きだ。
さて、澤孝子氏については事前にYou Tubeなどのチェックできず、まったく予備知識のないままその芸に接することに。が、一聴してその声に驚く。咽から絞り出すその強烈なコブシは、モンゴルのホーミーの如く倍音に響く。
そしてこの日の客層にあわせてか、落語でもお馴染みの「徂来豆腐」を可笑しく、情味たっぷりに演じ、語り、歌い、貫祿の舞台。その芸の確かさに舌を巻く。
先日も関西で活躍する三原佐知子師匠の“語り”に圧倒されたが、浪花節界は東西とも、女流がリードしているのだろうか? 寡聞にして浪花節界の現況については見当がつかないが、これだけ魅力ある芸(人)が確たる世界ならば、落語のように“再生”もあるやもしない。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


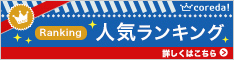

当代きっての人気落語家・柳家喬太郎師匠がナビゲーターとなって、浪花節の世界を案内するという「浪花ぶし 澤孝子の世界」(8月23日・博品館劇場)を堪能した。
おそらくメイン・ターゲットは落語ファンなのだろう。ふだんは木馬亭でしか聴けない浪花節をおしゃれな(?)銀座にもってきての公演。これは「澤孝子氏の芸に圧倒された」という喬太郎師匠の計らいか?
というもの、落語好きならば講談を聞く機会はあっても、じつは近しい芸であるはずの浪花節をナマで聞いたことのある人は意外と少ないのではないだろうか。かくいうワタシもつい最近になって、浪花節に開眼したばかり…。
そういう意味でも鈴々舎風車による浪花節解説を冒頭にもってきたのもよかったし、ふだんは声を聞くこともない曲師(佐藤貴美江氏)にマイクに向けて、伴奏者から観た浪花節の魅力を伝えたのもよかった。
孝子×喬太郎対談も、両者さすがに堂にいったもので、二人の語りだけで「芸」になっていて、たっぷりと会場を沸かせる。
で、孝子氏の弟子である澤雪絵が露払いを務め、まずは語り始めたが、この人は高音に魅力がある。語りも低音部の唸りもまだまだだが、今後ののびしろが感じられる舞台。
もはやいつどこに出ても、何にも怖くない喬太郎師匠は、季節ネタをもってきた。四谷怪談をモチーフにしつつつもブラックジョークの効いた「お菊の皿」。かつてのこのネタを春風亭昇太師匠で聞いて、現代落語の魅力に憑りつかれワタシだが、さすがは喬太郎師匠。それをはるかに上回る面白さ、凄まじさ。今ドキ風若者からお菊の豹変する形態まで、ハチャメチャに演じわけ、観客の気持ちをガッチリ掴む。
立川志らく師匠は近著『落語進化論』
さて、澤孝子氏については事前にYou Tubeなどのチェックできず、まったく予備知識のないままその芸に接することに。が、一聴してその声に驚く。咽から絞り出すその強烈なコブシは、モンゴルのホーミーの如く倍音に響く。
そしてこの日の客層にあわせてか、落語でもお馴染みの「徂来豆腐」を可笑しく、情味たっぷりに演じ、語り、歌い、貫祿の舞台。その芸の確かさに舌を巻く。
先日も関西で活躍する三原佐知子師匠の“語り”に圧倒されたが、浪花節界は東西とも、女流がリードしているのだろうか? 寡聞にして浪花節界の現況については見当がつかないが、これだけ魅力ある芸(人)が確たる世界ならば、落語のように“再生”もあるやもしない。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【演芸】浪曲定席木馬亭 ― 2011/06/04

先日木馬亭で聴いた三原佐知子師匠の名演にほだされて足を運んだ同席亭での定席「浪曲会」(6月4日)。
梅雨の晴れ間の浅草。観光やら散策を満喫する人波を抜けて、木馬亭に着いたときには、ちょうど神田陽司師匠による講談が始まっていた。
この人のプロフィールを読むと早稲田の一文を出て、あの「シティロード」編集部に入り演劇を担当、さらに副編集長まで務めていたというのだから驚く。
そうしたインテリ資質(?)を生かして、「レポート講談」なる新作を手がけているようで、本高座での「はやぶさ」を少年忍者に見立ての“サイエンス・ドキュメンタリー講談”も、そうした流れから創作されたものだろうか。
しかしながら、その着想や話の構成は面白いと思えるものの、ケレンというかキレというかが、もう一つ…。
もっともワタシの講談“生”見聞は、天才肌の神田山陽(3代目)、正統派ともいうべき宝井琴柳、中堅として安定感のある宝井琴調…の各師匠とわずかな体験なので、比較検討しようもないのだが。
続く、港家小柳師匠はハウリン・ウルフばりに唸るベテランの女流浪曲師だが、いかんせんお年のせいか(失礼)音程が不安定。
一方、三門柳師匠は高音を生かしての女性らしい(?)美声を聴かせる。ときとして“小唄”を聴いているような風情があり、さすが美声で鳴らした三門博門下。長谷川伸の名作「瞼の母」で座を沸かせ、トリの国本武春氏につなぐ。
“三味線ロック”などの活動で知られる国本氏の生ライブに触れるのもじつは初めて。若い女性(?)の固定客もついているようで、客席から黄色い声援が飛ぶ。
忠臣蔵「赤埴源蔵 徳利の別れ」を演ったが、これはもう安心して聴いていられる極上のパフォーマンス。迫力の唸りはもちろん、細かいビブラートを刻みながらケレン味たっぷりに聴かせる、聴かせる。情と笑いを交えた芝居でも、観客を見事に引き寄せて大団円。
もちろん浪曲界の現況などワタシごときには毛頭掴みようがないが、中堅からベテランの域に入り、実力もある人気者という国本師匠の立ち位置は、落語界の柳家喬太郎師匠のような存在なのかもしれない。
しかしながら、現在の落語界の興隆は喬太郎師匠に継ぐ中堅・若手の人材がワンサといる点にある。
はたして浪曲界はどのような状況下にあるのか。
Wilkiでチェックすると関東だけでも60名を超える浪曲師が散見できるのだが…。
モンガイカンであるワタシには、「浪曲の未来」を判断できずにいる。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


梅雨の晴れ間の浅草。観光やら散策を満喫する人波を抜けて、木馬亭に着いたときには、ちょうど神田陽司師匠による講談が始まっていた。
この人のプロフィールを読むと早稲田の一文を出て、あの「シティロード」編集部に入り演劇を担当、さらに副編集長まで務めていたというのだから驚く。
そうしたインテリ資質(?)を生かして、「レポート講談」なる新作を手がけているようで、本高座での「はやぶさ」を少年忍者に見立ての“サイエンス・ドキュメンタリー講談”も、そうした流れから創作されたものだろうか。
しかしながら、その着想や話の構成は面白いと思えるものの、ケレンというかキレというかが、もう一つ…。
もっともワタシの講談“生”見聞は、天才肌の神田山陽(3代目)、正統派ともいうべき宝井琴柳、中堅として安定感のある宝井琴調…の各師匠とわずかな体験なので、比較検討しようもないのだが。
続く、港家小柳師匠はハウリン・ウルフばりに唸るベテランの女流浪曲師だが、いかんせんお年のせいか(失礼)音程が不安定。
一方、三門柳師匠は高音を生かしての女性らしい(?)美声を聴かせる。ときとして“小唄”を聴いているような風情があり、さすが美声で鳴らした三門博門下。長谷川伸の名作「瞼の母」で座を沸かせ、トリの国本武春氏につなぐ。
“三味線ロック”などの活動で知られる国本氏の生ライブに触れるのもじつは初めて。若い女性(?)の固定客もついているようで、客席から黄色い声援が飛ぶ。
忠臣蔵「赤埴源蔵 徳利の別れ」を演ったが、これはもう安心して聴いていられる極上のパフォーマンス。迫力の唸りはもちろん、細かいビブラートを刻みながらケレン味たっぷりに聴かせる、聴かせる。情と笑いを交えた芝居でも、観客を見事に引き寄せて大団円。
もちろん浪曲界の現況などワタシごときには毛頭掴みようがないが、中堅からベテランの域に入り、実力もある人気者という国本師匠の立ち位置は、落語界の柳家喬太郎師匠のような存在なのかもしれない。
しかしながら、現在の落語界の興隆は喬太郎師匠に継ぐ中堅・若手の人材がワンサといる点にある。
はたして浪曲界はどのような状況下にあるのか。
Wilkiでチェックすると関東だけでも60名を超える浪曲師が散見できるのだが…。
モンガイカンであるワタシには、「浪曲の未来」を判断できずにいる。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【演芸】てなもんや浪漫バラエティー ― 2011/05/29

台風襲来で土砂降りのなか、浅草・木馬亭へ。「てなもんや浪漫バラエティー」と題された浪曲、音曲漫才、浪曲漫談のオムニバスショーを楽しむ(5月29日)。
聖書を脇に抱えた神父姿で登場した浪曲漫談のイエス玉川は、以前テレビでも観た記憶があるが、司会の澤田隆治氏(メディア・プロデューサー)によれば「テレビでは出来ないネタばかり」とのこと。
たしかに毒舌が持ち味だけあってそれも頷けるのだが、どうも過去に“売れた”経験があるから、グチっぽさが仇になってどうも乗り切れない。それが芸風なのか、それとも客の少なさのせいか…?
「宮川左近ショー」の三味線弾きとして活躍した暁照夫が、弟子の光夫と組んでの音曲漫才は、客席から左近ショーの記憶を引きずりだしながらの楽しいステージ。
上方と東京の気質を比べながら、ひとしきりくっちゃべった後、待ってましたの音曲に突入。左近ショーでも“売り”だった三味線早弾きは顕在で、「なんでこんなにうまいんやろ」と自惚れるギャグも、嬉しい決めゼリフ。
さすがに、お年のせいか(失礼)危なかっしい音程はご愛敬だが、とにかく左近ショウを追想できる上方の円熟芸に触れられたのは収穫。
圧巻だったのは浪曲の三原佐知子師匠。
じつは浪曲を“生”で聴くのは初めてだったのだが、その声量といい、声色・ヴォーカルコントロールといい、ケレンといい、浪曲という芸能の底力に圧倒された。
とにかくその声・節回しが気持ちイイ。ゾクゾクとする。
これはヌスラット・ファテ・アリ・ハーンのカッワリーや仏教声明に通じる身体に直接響くようにな快感だ。
浪曲(浪花節)という芸能は、明治期から戦前まで一斉を風靡した。
ラジオなどによって全国で愛聴され、当時の浪曲師は大変な人気だったという。なぜそれほどまでに、単純なこの語りと声の芸能が大きな人気を博したのか?
浪曲は今回確認できたように、じつに肉感的な芸能だ。
その語りと声が、心身に染みわたり、癒しや活力を与えてくれる…。
そこにワタシは、昨今の流行りのスピリチュアリズムや“癒し”に似たものを感じる。
だからこそ、浪曲師はヒーラーであり、小屋掛けは庶民にとってのホットスポットだったのではないだうろか?
そんな妄想を抱いてしまうほど、“生”の浪曲はパワーに溢れていた。
最後は出演者総出による歌謡ショーで、ここでも佐知子師匠は「無法松の一生」と「ろうきょく炭坑節」を唸り、さすがの貫祿を魅せた。
それにしても大雨とはいえ客席は寂しく、こんな豊熟な芸が安価で観賞できるのにじつにもったいない…。7月には、浪曲河内音頭を中心とした第二回が企画されているようで、こちらも期待したい。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


聖書を脇に抱えた神父姿で登場した浪曲漫談のイエス玉川は、以前テレビでも観た記憶があるが、司会の澤田隆治氏(メディア・プロデューサー)によれば「テレビでは出来ないネタばかり」とのこと。
たしかに毒舌が持ち味だけあってそれも頷けるのだが、どうも過去に“売れた”経験があるから、グチっぽさが仇になってどうも乗り切れない。それが芸風なのか、それとも客の少なさのせいか…?
「宮川左近ショー」の三味線弾きとして活躍した暁照夫が、弟子の光夫と組んでの音曲漫才は、客席から左近ショーの記憶を引きずりだしながらの楽しいステージ。
上方と東京の気質を比べながら、ひとしきりくっちゃべった後、待ってましたの音曲に突入。左近ショーでも“売り”だった三味線早弾きは顕在で、「なんでこんなにうまいんやろ」と自惚れるギャグも、嬉しい決めゼリフ。
さすがに、お年のせいか(失礼)危なかっしい音程はご愛敬だが、とにかく左近ショウを追想できる上方の円熟芸に触れられたのは収穫。
圧巻だったのは浪曲の三原佐知子師匠。
じつは浪曲を“生”で聴くのは初めてだったのだが、その声量といい、声色・ヴォーカルコントロールといい、ケレンといい、浪曲という芸能の底力に圧倒された。
とにかくその声・節回しが気持ちイイ。ゾクゾクとする。
これはヌスラット・ファテ・アリ・ハーンのカッワリーや仏教声明に通じる身体に直接響くようにな快感だ。
浪曲(浪花節)という芸能は、明治期から戦前まで一斉を風靡した。
ラジオなどによって全国で愛聴され、当時の浪曲師は大変な人気だったという。なぜそれほどまでに、単純なこの語りと声の芸能が大きな人気を博したのか?
浪曲は今回確認できたように、じつに肉感的な芸能だ。
その語りと声が、心身に染みわたり、癒しや活力を与えてくれる…。
そこにワタシは、昨今の流行りのスピリチュアリズムや“癒し”に似たものを感じる。
だからこそ、浪曲師はヒーラーであり、小屋掛けは庶民にとってのホットスポットだったのではないだうろか?
そんな妄想を抱いてしまうほど、“生”の浪曲はパワーに溢れていた。
最後は出演者総出による歌謡ショーで、ここでも佐知子師匠は「無法松の一生」と「ろうきょく炭坑節」を唸り、さすがの貫祿を魅せた。
それにしても大雨とはいえ客席は寂しく、こんな豊熟な芸が安価で観賞できるのにじつにもったいない…。7月には、浪曲河内音頭を中心とした第二回が企画されているようで、こちらも期待したい。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
 | THAT'S浪曲ショー 宮川左近ショー ミソラレコード 2011-03-20 売り上げランキング : 13953 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
若松若太夫独演会 ― 2010/06/05

そして、本日の演者は三代目・若太夫で、12回目の独演会だという。会場も板橋区立郷土芸能伝承館という趣ある建物、そして主催は説教節を保存・伝承する「若松会」。たしか代表の青木久子さんは、先代をアルコール禍から救い出したその人だったかと思う。そんなさまざまな人や思いに支えられてか、会場は年配の方を中心にゾロゾロと地域(?)の方々が集まってくる。
三代目の節は、(当たり前だが)先代の節を受け継いだ艶ある唸り。時として弱々しく聴こえるが、それも先代の持ち味だった。三味線にこんな多彩な弾き方があったかと思わせる、表情豊かな伴奏もイイ。(^_-)
日蓮上人の弟子の話「日朗上人佐渡の雪」でじっくりと、「日高川入相花王」で楽しくと、説教節の幅も魅せてくれた。まだ若いので、これからさらに期待できる三代目である。
三代目の節は、(当たり前だが)先代の節を受け継いだ艶ある唸り。時として弱々しく聴こえるが、それも先代の持ち味だった。三味線にこんな多彩な弾き方があったかと思わせる、表情豊かな伴奏もイイ。(^_-)
日蓮上人の弟子の話「日朗上人佐渡の雪」でじっくりと、「日高川入相花王」で楽しくと、説教節の幅も魅せてくれた。まだ若いので、これからさらに期待できる三代目である。
御名残三月大歌舞伎 ― 2010/03/20
忙しくなって更新が遅れ気味…のなか、足を運んだ「歌舞伎座さよなら公演」。
『御名残三月大歌舞伎』(3月17日・歌舞伎座)
『御名残三月大歌舞伎』(3月17日・歌舞伎座)

「語り草になる『道明寺』」という朝日新聞評につられて、初めて観る、初めて行くKABUKI!
で、「道明寺」だが、こーいうのを義太夫狂言というそうで、そうか、片岡仁左衛門演じる菅丞相は菅原道真がモデルなのかぁ…と。で、途中までその仁左衛門の出番はほとんどなく、なんだ結局、玉三郎の芝居じゃん!と思っていたら、後半の仁左衛門の語りだけで演じる芸の凄味が…圧巻。
一転して、つづく「石橋」は中国を舞台した「能」をもとにしている…とかで、ズラリと並んだ三味線や鼓の演者らが居並ぶ派手な舞台で、子役が活躍し、松本幸四郎の早変わり、トンボは切るわ群舞はあるは…と楽しい芝居。
で、結局、歌舞伎ってその名の通り、時空を超えた「歌舞く」エンターテインメントなんだなぁ…と実感。だって、殿様の衣装はまるで中世の騎士だし(楯まで持ってるし( ^ ^ ; )、やたらミエを切るし、なんだかみんな動きが可笑しいし(意味あるんだろうけど)、人情あり、滑稽あり、また乱舞ありと何でもあり…。
「出雲の阿国」が、400年にも前に四条の河原でカブキ者として踊った姿が、時代を経て「伝統芸能」として形をなし、今もまた多くの人たちを楽しませている…うーん、感慨深し。
( ′・`) フゥ‥‥
一転して、つづく「石橋」は中国を舞台した「能」をもとにしている…とかで、ズラリと並んだ三味線や鼓の演者らが居並ぶ派手な舞台で、子役が活躍し、松本幸四郎の早変わり、トンボは切るわ群舞はあるは…と楽しい芝居。
で、結局、歌舞伎ってその名の通り、時空を超えた「歌舞く」エンターテインメントなんだなぁ…と実感。だって、殿様の衣装はまるで中世の騎士だし(楯まで持ってるし( ^ ^ ; )、やたらミエを切るし、なんだかみんな動きが可笑しいし(意味あるんだろうけど)、人情あり、滑稽あり、また乱舞ありと何でもあり…。
「出雲の阿国」が、400年にも前に四条の河原でカブキ者として踊った姿が、時代を経て「伝統芸能」として形をなし、今もまた多くの人たちを楽しませている…うーん、感慨深し。
( ′・`) フゥ‥‥
弧の会「弧風」 ― 2010/03/06
「弧の会」による日本舞踊「弧風」公演(3月6日・神楽坂牛込箪笥ホール)を観る。

「弧の会」は日本舞踊の素晴らしさを多くの人に伝えようと、若手・中堅の踊り手(♂)12名によって1998年に結成された「日本舞踊界のヌーベルバーグ」だとかで、紋付袴姿での「素踊り群舞」を基本コンセプトにオリジナル作を発表し続けているという。
たしかに、足を振り上げ、ジャンプし、側転し、膝を軸にヒップホップまがいに回転し、はては海老ぞりイナバウワーまで飛び出すとあっては、もはや紋付袴姿のコンテンポラリー・ダンスと言っていい。いやぁ、日本舞踊がここまでモダンだとは、知りませんでしたぁ。(^_-)
ステージの構成も「ゲイ(芸)の花舞台へようこそ!」と国民放送の某番組をパロディに、演者を舞台にあげて「弧の会」や演目をわかりやすく説明するなど、とにかく「日本舞踊を知ってほしい、楽しんでほしい」というメンバーの心意気が伝わってくる。
序幕のめでたい「はじめ式」から、二人の踊り手の対照が効果を生む「龍虎」、そして最後は狂言舞踊&群舞で楽しく〆るという工夫に富んだ構成と演出もヨかった。
そして終演後に、演者たちが楽屋から飛び出して気さくに出口に並び、観客を一人ひとり送り出すという姿勢もまた好感↑。
たしかに、足を振り上げ、ジャンプし、側転し、膝を軸にヒップホップまがいに回転し、はては海老ぞりイナバウワーまで飛び出すとあっては、もはや紋付袴姿のコンテンポラリー・ダンスと言っていい。いやぁ、日本舞踊がここまでモダンだとは、知りませんでしたぁ。(^_-)
ステージの構成も「ゲイ(芸)の花舞台へようこそ!」と国民放送の某番組をパロディに、演者を舞台にあげて「弧の会」や演目をわかりやすく説明するなど、とにかく「日本舞踊を知ってほしい、楽しんでほしい」というメンバーの心意気が伝わってくる。
序幕のめでたい「はじめ式」から、二人の踊り手の対照が効果を生む「龍虎」、そして最後は狂言舞踊&群舞で楽しく〆るという工夫に富んだ構成と演出もヨかった。
そして終演後に、演者たちが楽屋から飛び出して気さくに出口に並び、観客を一人ひとり送り出すという姿勢もまた好感↑。
日本の伝統芸能絵巻 ― 2010/02/08
「神楽坂 伝統芸能2010」の一環として行われた「日本の伝統芸能絵巻~美しき日本の四季」(2月6日・夜の部 矢来能楽堂)に足を運ぶ。といってもこの分野はまったくのモンガイカン(>_<) …なので以下、ほとんどレビューになっていない簡単な報告。
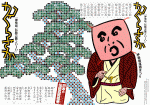
まず会場が素晴らしい。矢来能楽堂は東京では二番目に古い能楽堂だそうで、檜づくりの趣のある舞台。(他と比較できないが)音の響きもいいそうだ。
で、この催しは、能、長唄、箏曲、新内、日本舞踊それぞれの演目で副題となっている「日本の四季」を表現するというもので、まさしくに日本の伝統芸能・音楽(の一部)を俯瞰できるオムニバス形式の演奏会。二度の休憩をはさんで3時間近く、さまざまな演者による「芸」が披露された。
ところでワタシにとっては、「能」以外はいずれもナマで聴くのは初めてというものばかり。
で、能と箏曲はワタシには行儀良すぎてチョット退屈( ^ ^ ; 。長唄の東音宮田哲男サンは人間国宝(こういう呼称はあまり好きではないが)だけあって、さすがに声がイイ。
さらに新内の鶴賀若狭掾サン(やはり人間国宝)は、子どもから女房まで超絶技巧のごとく咽を使い分け、観客を舞台に引き込みサスガの芸。拍手もひときわ大きかった。
日本舞踊、それも男の踊り手は初めて観たが、よくわからんが、とてもエモーショナル!
初体験ということもあり、コンテンポラリーダンスなどとは違う独特の深みがあるような…。
うーん、この世界、もうちょっと探求せねば。
で、この催しは、能、長唄、箏曲、新内、日本舞踊それぞれの演目で副題となっている「日本の四季」を表現するというもので、まさしくに日本の伝統芸能・音楽(の一部)を俯瞰できるオムニバス形式の演奏会。二度の休憩をはさんで3時間近く、さまざまな演者による「芸」が披露された。
ところでワタシにとっては、「能」以外はいずれもナマで聴くのは初めてというものばかり。
で、能と箏曲はワタシには行儀良すぎてチョット退屈( ^ ^ ; 。長唄の東音宮田哲男サンは人間国宝(こういう呼称はあまり好きではないが)だけあって、さすがに声がイイ。
さらに新内の鶴賀若狭掾サン(やはり人間国宝)は、子どもから女房まで超絶技巧のごとく咽を使い分け、観客を舞台に引き込みサスガの芸。拍手もひときわ大きかった。
日本舞踊、それも男の踊り手は初めて観たが、よくわからんが、とてもエモーショナル!
初体験ということもあり、コンテンポラリーダンスなどとは違う独特の深みがあるような…。
うーん、この世界、もうちょっと探求せねば。


最近のコメント