【演劇】燐光群「推進派」 ― 2011/06/30
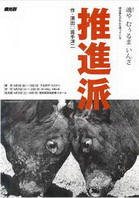
燐光群「推進派」の劇評らしきものを、レビューマガジン「ワンダーランド」に執筆したので、以下に紹介(一部)する。(全文は「ワンダーランド」参照、6月9日観劇)
うーむ、こういう芝居はどう評していいものかと、思わず腕組みしてしまう…。欠点を論(あげつら)えば、いくらでも挙げることができる。
まず、状況説明のために、登場人物が突然饒舌となりやたら詳しい解説を語りだす。〈解説〉が始まると役者は一歩前に踏み出し、声を張り上げるといった古くさい新劇テイスト。2日目の舞台のせいか、はたまたそのセリフの多さのせいか、役者がしばしばセリフを噛むこと。そして、話を詰め込みすぎて、十分に整理されていないこと…。
しかしながら、そうしたさまざまな〈欠点〉を補って余るほどの迫力と剛力(ごうりき)をもって、本作『推進派』はワタシたちの前に提起された。今ニッポンで進行している事態を、一つのエンターテイメント性ある〈物語〉として結実させた芝居として。
…続きは「ワンダーランド」を参照。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


うーむ、こういう芝居はどう評していいものかと、思わず腕組みしてしまう…。欠点を論(あげつら)えば、いくらでも挙げることができる。
まず、状況説明のために、登場人物が突然饒舌となりやたら詳しい解説を語りだす。〈解説〉が始まると役者は一歩前に踏み出し、声を張り上げるといった古くさい新劇テイスト。2日目の舞台のせいか、はたまたそのセリフの多さのせいか、役者がしばしばセリフを噛むこと。そして、話を詰め込みすぎて、十分に整理されていないこと…。
しかしながら、そうしたさまざまな〈欠点〉を補って余るほどの迫力と剛力(ごうりき)をもって、本作『推進派』はワタシたちの前に提起された。今ニッポンで進行している事態を、一つのエンターテイメント性ある〈物語〉として結実させた芝居として。
…続きは「ワンダーランド」を参照。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【演劇】大規模修繕劇団『地の婚礼』 ― 2011/06/27

蜷川幸雄氏が新たに立ち上げた<大規模修繕劇団>の旗揚げ公演『地の婚礼』(作・清水邦夫)をにしすがも創造舎体育館・特設会場に観に行った(6月26日)。
なんともお恥ずかしいかぎりだが、今までどうも機会がなく蜷川演出劇は初体験。清水+蜷川コンビによる「名作」と知られる『地の婚礼』を、窪塚洋介、中島朋子、髙橋和也、伊藤蘭という豪華キャストで再演するとだけあって、大いに期待して出かけて行ったのだが…。
芝居に限らずすぐれた芸術・文化には、えてして「暗喩」として観客に問いかける仕掛けが施される。その「暗喩」が何を意味するのか、観客一人ひとりが思考と想像力を巡らせながら、作品に臨む。芝居を観る楽しさとは、そうした作者や演出家からなげられた「暗喩」の中に潜む「問い」に対する、主体的な参加に依っている部分が大きい。
そして、本作にもそうしたいくつもの「暗喩」が提示されるのだが、その最たるものが舞台に降り続ける「雨」だろう。
なにしろ冒頭から90分間、雨はやむことなく舞台に降りしきる。
この雨はいったい何を意味をしているのだろうか?
清水氏によって芝居が書かれたのは、1986年。今から25年も前のことだ。
その時代ならば、「雨」は次第に息苦しさを増す管理社会の象徴か、あるいは希薄な人間関係を示す疎外感か、はたまた単なるイバラの青春期を表現したものなのだったのだろうか?
しかし、3.11を経て、いまだに収束しない福島原発事故に不安あ毎日を送るワタシたちは、どうしてもそれに放射能の雨を連想せずにいられない…。
舞台は繁華街のうらぶれた路地。路地と、路地を挟んで並ぶ小さなビデオ屋とコインランドリーだけで、この愛憎劇ともドタバタ劇ともとれる物語が展開していく。
スペインの詩人ガルシア・ロルカの『血の婚礼』に触発されて書かれたという本作をひと言で言ってしまえば、男女、血族の愛憎劇ということなのだが、そこに応答のないトランシーバーで報告を続ける青年(田島優成)や、ヘルマン・ヘッセの世界で耽溺する教師(青山達三)とその生徒、飲み屋の女たちや鼓笛隊までが乱入する。
その一つひとつが「暗喩」として提示され、まさに蜷川メタファー・ワールドが炸裂するのだが、どうもワタシにはしっくりこない。というかワタシの妄想・爆想導火線にいつまでたっても引火しない…。
25年前には斬新だっであろう舞台に降りしきる雨(総量7トンだとか)も、雨中で絶唱する役者たちのエネルギッシュな肉体も、ヘッセ的な苦悩を体現する詩的なセリフも、映像を駆使した欲望渦まく猥雑な舞台装置も、ワタシにはどうもシゲキが感じられない。“演出”に新味が感じられないのだ(ああ、とうとう言ってしまった!)。
だから、冒頭から「放射能」の雨が降り続けても、鼓笛隊が「権力者」のように路地を跋扈しても、路地裏を「希望」のように電車が走り抜けても、どうもその「暗喩」が生きてこない。
スクリーンではじつに魅力的な芝居を魅せる、窪塚洋介、中島朋子といった若手役者たちも、堅実な演技が身上の髙橋和也、伊藤蘭といった中堅俳優たちも、その魅力を舞台に十分放っているとは言い難い。舞台での大仰な演技に、その力が発揮できていない気がするのだ。
…という訳で、ワタシには退屈な芝居だった。(7/30日まで)
↓応援クリックにご協力をお願いします。


なんともお恥ずかしいかぎりだが、今までどうも機会がなく蜷川演出劇は初体験。清水+蜷川コンビによる「名作」と知られる『地の婚礼』を、窪塚洋介、中島朋子、髙橋和也、伊藤蘭という豪華キャストで再演するとだけあって、大いに期待して出かけて行ったのだが…。
芝居に限らずすぐれた芸術・文化には、えてして「暗喩」として観客に問いかける仕掛けが施される。その「暗喩」が何を意味するのか、観客一人ひとりが思考と想像力を巡らせながら、作品に臨む。芝居を観る楽しさとは、そうした作者や演出家からなげられた「暗喩」の中に潜む「問い」に対する、主体的な参加に依っている部分が大きい。
そして、本作にもそうしたいくつもの「暗喩」が提示されるのだが、その最たるものが舞台に降り続ける「雨」だろう。
なにしろ冒頭から90分間、雨はやむことなく舞台に降りしきる。
この雨はいったい何を意味をしているのだろうか?
清水氏によって芝居が書かれたのは、1986年。今から25年も前のことだ。
その時代ならば、「雨」は次第に息苦しさを増す管理社会の象徴か、あるいは希薄な人間関係を示す疎外感か、はたまた単なるイバラの青春期を表現したものなのだったのだろうか?
しかし、3.11を経て、いまだに収束しない福島原発事故に不安あ毎日を送るワタシたちは、どうしてもそれに放射能の雨を連想せずにいられない…。
舞台は繁華街のうらぶれた路地。路地と、路地を挟んで並ぶ小さなビデオ屋とコインランドリーだけで、この愛憎劇ともドタバタ劇ともとれる物語が展開していく。
スペインの詩人ガルシア・ロルカの『血の婚礼』に触発されて書かれたという本作をひと言で言ってしまえば、男女、血族の愛憎劇ということなのだが、そこに応答のないトランシーバーで報告を続ける青年(田島優成)や、ヘルマン・ヘッセの世界で耽溺する教師(青山達三)とその生徒、飲み屋の女たちや鼓笛隊までが乱入する。
その一つひとつが「暗喩」として提示され、まさに蜷川メタファー・ワールドが炸裂するのだが、どうもワタシにはしっくりこない。というかワタシの妄想・爆想導火線にいつまでたっても引火しない…。
25年前には斬新だっであろう舞台に降りしきる雨(総量7トンだとか)も、雨中で絶唱する役者たちのエネルギッシュな肉体も、ヘッセ的な苦悩を体現する詩的なセリフも、映像を駆使した欲望渦まく猥雑な舞台装置も、ワタシにはどうもシゲキが感じられない。“演出”に新味が感じられないのだ(ああ、とうとう言ってしまった!)。
だから、冒頭から「放射能」の雨が降り続けても、鼓笛隊が「権力者」のように路地を跋扈しても、路地裏を「希望」のように電車が走り抜けても、どうもその「暗喩」が生きてこない。
スクリーンではじつに魅力的な芝居を魅せる、窪塚洋介、中島朋子といった若手役者たちも、堅実な演技が身上の髙橋和也、伊藤蘭といった中堅俳優たちも、その魅力を舞台に十分放っているとは言い難い。舞台での大仰な演技に、その力が発揮できていない気がするのだ。
…という訳で、ワタシには退屈な芝居だった。(7/30日まで)
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【本】ドラマトゥルク 舞台芸術を進化/深化させる者 ― 2011/06/21
 | ドラマトゥルク―舞台芸術を進化/深化させる者 平田 栄一朗 三元社 2010-11 売り上げランキング : 281737 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
ドイツでは演劇界に古くから存在する「肩書」で、制作とは独立した権限を持つ専門職なのだという。オーストリアとスイスを含むドイツ語圏の公共事業などで500名以上が活動しているという。
また1960年前後からヨーロッパの周辺諸国やアメリカ・カナダの公共劇場や主要劇団がこの「ジャーマン・モデル」を参考にして「ドラマトゥルク」を採用するようになったという。
その「ドラマトゥルク」の活動内容や役割を、本邦で初めて詳らかにした本格的な書というわけだが、じつのところ読後を経ても、未だに「ドラマトゥルク」の職分イメージが十分に掴めずにいる…。
たしかに本書では、演出補やプロデューサー、あるいは演劇キュレーター的なイメージしか(ワタシには)持ちえていなかった「ドラマトゥルク」の多彩な活動や役割が、紹介・考察されている。
多くは劇場に所属し、舞台制作に関するさまざまな事例や問題に精通し、ときとして助言・提言を行う。あるいは観客までも教育・組織化し、舞台芸術の活動の輪を拡げていく。。それゆえ文学、美術など、深く広範な専門知識が要求される知的エキスパートなのだという。
しかしそれらの活動があまり多岐にわたり、またそれを追いかける本書の調査・研究もまた蜘蛛の巣のような八方広がりとなり、ワタシの頭の中は混濁する…。
というのも、どうも研究論文がベースになっているせいか、「ドラマトゥルク」の生身の姿が見えてこなのだ。フィールドワークやヒアリングは十分に重ねているのだろうが、ルポルタージュ的な表現が少ないので、そう感じてしまうのだろう。
それにほとんどがドイツでの話であって、ワタシにはとっては遠い。
もう少し研究の範囲を拡げて、「ジャーマン・モデル」を移築した他国の例などを挙げれてくれれば、後半で熱く展開される「日本におけるドラマトゥルク導入の可能性」についてももっと説得力を持ったのではないだろうか。
さらにいえば、日本ですでに「ドラマトゥルク」として活躍されている演劇人の活動が、なぜかほとんど紹介されていない。その「活動」は著書の説く「ドラマトゥルク」とは相いれないものなのか、紹介する値のないものと判断したのか、とにかく日本における「ドラマトゥルク」の活動を詳らかにしないでおいて、その「可能性」を語るというのもずいぶんと片手落ちな話ではないか…。
まあたしかに、今まで耳慣れなかった(しかも重要な存在らしい)「ドラマトゥルク」が、こうした形でも紹介されたことは喜ばしことだが、今後はルポや当事者からの発信といったさまざまな形での著書が編まれれば、その「可能性」についての議論が深まると思うのだが…。
◆『ドラマトゥルク』の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「日本の演劇界が抱える問題に一石を投じた書」--書評空間(西堂行人氏)
「ドラマトゥルクについて広範に論じた画期的な名著」--雄鶏とナイフ
「Dramaturg の訳には、「作劇家」がふさわしい」--仕事の日記(白石知雄氏)
「教科書的な概論・解説に陥らず、アップ・トゥ・デートな内容」--ella and louis BLOG
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【TV】トニー賞 ミュージカル特集「フェラ!」 ― 2011/06/20

これは驚いた。
フェラ・アニクラポ・クティの半生を描いた『フェラ!』なるミュージカルがブロードウェイで上演され、しかも2010年のトニー賞で11部門にノミネート、3部門を受賞していたとは!
その舞台ライブが、6月15日にNHK・BSプレミアムで放映された。
フェラ・クティといえば、70年代に腐敗しきったナイジェリア政府を攻撃し続けた先鋭的なミュージシャンで、「アフロビート」の創始者。いわばアフリカにおけるワールド・ミュージックの先駆者であり、ボブ・マーリーと比してもおかしくない存在だ。
しかしながらその知名度ははるかに低い…と思っていたので、こうしたミュージカルが製作・上演されていたことに大いに驚いた次第。
たしかに近年、アンティバラスなど若い世代の間で、フェラの遺伝子を引き継いだアフロ・ビート・バンドが注目を集めていることは知っていたが、まさかフェラがミュージカルになるとは…。
舞台設定は、フェラの活動根拠地であった「シュライン」。
観客はそのライブハウスに集まった「観客」という設定で、フェラの語り(演説)とライブ演奏で物語は進む。
「シュライン」といえば、ナイジェリア政府からの弾圧を何度も受け、たしか死者まで出したフェラの“聖地”。そこでのライブを再現するということで、観客は生前のフェラの聖地ライブを疑似体験できるという仕掛け。
なるほど、そこまではいい。
しかし、どんなに(風貌から声や喋りまでも)フェラに似せた男優(サ・ンガウジャ)が演じても、腕達者なミュージシャンやバンド演奏やコーラスが熱演を繰り広げても、あのフェラの呪術的なパフォーマンスは再現できないのだ…。
あのおどろあどろしいまでのカリスマ性、危険な香り、ヒリヒリとした感性と、あくことのないアグレッシブなサウンド…。ワタシがフェラの生ライブを体験した数少ない日本人(1984年グラストンベリー・フェスティバル)であるということを差し引いても、その舞台で演じられるものは実際のフェラには及びもつかないものなのだ。
しかも客席を埋めるのは、正装に近い大人げな紳士・淑女ばかりだ(収録はなぜかロンドン公演)。
ここはシュラインだ、と言われてもまったく現実感はなく、かえってエキゾチズムと正義感に彩どられた植民地ドラマを見せられているかのように、居心地が悪い。かつてボール・サイモンらもやり玉に挙げられた非西欧文化搾取の構図が頭をよぎる。
そうした批判が起こるのを予期してか(?)休憩を挟んでの後半では、フェラの活動と音楽に大きな影響を与えた神話的なヨルバ世界に迫ろうとするが、それほど舞台の深化に貢献しているとは思えず、むしろ冗長になった印象を受ける。
なんといっても休憩を挟んで3時間にも及ぶ舞台は長い。もうちょっと刈り込んでもよかったのではないか。ノミネートのわりに受賞が少なく、しかも主要な賞を逃していることからも、このミュージカルの評価がそう高くなかったことが伺い知れる。
そうは言っても、「Up Side Down」「Zombie」といった往年の名曲が流れればついこちらも熱くなる。それだけに、フェラが世に送り出した楽曲群が時代を超えた“名曲”であったことがはからずも証明されたわけで、それだけでもこのミュージカルが上演された意味があったかもしれない。
◆ミュージカル『フェラ!』の参考レビュー(*タイトル文責は森口)
「思わず腰ふる、エネルギー爆発ミュージカル『Fela!』」--NY Niche
「ニューヨーク公演は連日超満員」--Dance Cube チャコット webマガジン
↓応援クリックにご協力をお願いします。


フェラ・アニクラポ・クティの半生を描いた『フェラ!』なるミュージカルがブロードウェイで上演され、しかも2010年のトニー賞で11部門にノミネート、3部門を受賞していたとは!
その舞台ライブが、6月15日にNHK・BSプレミアムで放映された。
フェラ・クティといえば、70年代に腐敗しきったナイジェリア政府を攻撃し続けた先鋭的なミュージシャンで、「アフロビート」の創始者。いわばアフリカにおけるワールド・ミュージックの先駆者であり、ボブ・マーリーと比してもおかしくない存在だ。
しかしながらその知名度ははるかに低い…と思っていたので、こうしたミュージカルが製作・上演されていたことに大いに驚いた次第。
たしかに近年、アンティバラスなど若い世代の間で、フェラの遺伝子を引き継いだアフロ・ビート・バンドが注目を集めていることは知っていたが、まさかフェラがミュージカルになるとは…。
舞台設定は、フェラの活動根拠地であった「シュライン」。
観客はそのライブハウスに集まった「観客」という設定で、フェラの語り(演説)とライブ演奏で物語は進む。
「シュライン」といえば、ナイジェリア政府からの弾圧を何度も受け、たしか死者まで出したフェラの“聖地”。そこでのライブを再現するということで、観客は生前のフェラの聖地ライブを疑似体験できるという仕掛け。
なるほど、そこまではいい。
しかし、どんなに(風貌から声や喋りまでも)フェラに似せた男優(サ・ンガウジャ)が演じても、腕達者なミュージシャンやバンド演奏やコーラスが熱演を繰り広げても、あのフェラの呪術的なパフォーマンスは再現できないのだ…。
あのおどろあどろしいまでのカリスマ性、危険な香り、ヒリヒリとした感性と、あくことのないアグレッシブなサウンド…。ワタシがフェラの生ライブを体験した数少ない日本人(1984年グラストンベリー・フェスティバル)であるということを差し引いても、その舞台で演じられるものは実際のフェラには及びもつかないものなのだ。
しかも客席を埋めるのは、正装に近い大人げな紳士・淑女ばかりだ(収録はなぜかロンドン公演)。
ここはシュラインだ、と言われてもまったく現実感はなく、かえってエキゾチズムと正義感に彩どられた植民地ドラマを見せられているかのように、居心地が悪い。かつてボール・サイモンらもやり玉に挙げられた非西欧文化搾取の構図が頭をよぎる。
そうした批判が起こるのを予期してか(?)休憩を挟んでの後半では、フェラの活動と音楽に大きな影響を与えた神話的なヨルバ世界に迫ろうとするが、それほど舞台の深化に貢献しているとは思えず、むしろ冗長になった印象を受ける。
なんといっても休憩を挟んで3時間にも及ぶ舞台は長い。もうちょっと刈り込んでもよかったのではないか。ノミネートのわりに受賞が少なく、しかも主要な賞を逃していることからも、このミュージカルの評価がそう高くなかったことが伺い知れる。
そうは言っても、「Up Side Down」「Zombie」といった往年の名曲が流れればついこちらも熱くなる。それだけに、フェラが世に送り出した楽曲群が時代を超えた“名曲”であったことがはからずも証明されたわけで、それだけでもこのミュージカルが上演された意味があったかもしれない。
◆ミュージカル『フェラ!』の参考レビュー(*タイトル文責は森口)
「思わず腰ふる、エネルギー爆発ミュージカル『Fela!』」--NY Niche
「ニューヨーク公演は連日超満員」--Dance Cube チャコット webマガジン
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【演劇】イキウメ『散歩する侵略者』 ― 2011/05/28

前川知大率いる劇団「イキウメ」による『散歩する侵略者』を観劇(5月28日・三軒茶屋シアタートラム)。これは心に染みる芝居だ…。
不可解な「散歩者」(窪田道聡)の登場から物語は始まり、散歩者に接した家族(岸本幸子)や町の人びと(森下創、盛隆二)が次々に変調をきたしていく。やがて「散歩者」には、同類の仲間(大窪人衛、加茂杏子)がいることがわかり、自分たちは「宇宙人」だと名乗る。彼らの「仕事」は人が持つ「概念」の調査で、彼らと対面した人間たちは次々と「概念」を奪われていく…。
前川氏お得意のレイヤー構造は相変わらず見事で、舞台転換をまったく行わずにそこが、路上であったり、二組の夫婦の部屋であったり、病院内であったりと、さまざまに表情を変える。しかもその場でいくつかの物語が同時に、あるいは交錯しないがら進行していくという手法。
燐国との軍事緊張が高まるなかで、物語は次第に宇宙人(?)による「侵略」というSFチックな様相を帯びていくのだが、前川氏は最後に、それらをすべて吹っ飛ばす仕掛けを施した。
「宇宙人」の夫が妻(伊勢佳世)の一番大切なものを奪い、自身がそれを知ってしまったことで、本作を、せつない“愛”の物語にしてしまったのだ。
これには、やられた。
人間とは「概念」で生きる動物だという存在論的なテーマを突きつけ、平田オリザ氏が主導するロボット演劇に対する一つ回答を提示してみせたかのように思わせて、じつは、つかこうへい的な純愛人間ドラマへと物語を昇華させる…。
その手腕に見事にのせられてしまったのは、ワタシだけではないと思う。終演後の客席の拍手の大きさがそれを物語っている。
もちろんここで語られる「戦争」や「侵略者」、あるいは「概念」などは、さまざまな暗喩として捉えることもできる。とりわけ3.11を経て、未だに収束しない原発事故による放射能に晒されるワタシたちにとって、その妄想は果てしなく続く。
それにしてこの劇団の役者たちは、それぞれに味があり、芝居巧者が揃っている。荒唐無稽になりがちな物語世界に入っていけるのも、そうした力のある役者たちと作家・演出家とが、がっちりとタッグを組んでいるからなのだと思う。
◆イキウメ『散歩する侵略者』の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「スリリングな展開、巧みな状況設定、役者の語りで想像力を刺激」--YOMIURI ONLINE(祐成秀樹氏)
「現代演劇の最高峰の一つ」-- PLAYNOTE
「作り手は何を伝えたいかをより明確にすることが必要」--因幡屋ぶろぐ
「ひとつの小さな奇跡をかみした」--しのぶの演劇レビュー
「特異な独特の世界観にただただ感服」--Forgetting-BarⅡ
↓応援クリックにご協力をお願いします。


不可解な「散歩者」(窪田道聡)の登場から物語は始まり、散歩者に接した家族(岸本幸子)や町の人びと(森下創、盛隆二)が次々に変調をきたしていく。やがて「散歩者」には、同類の仲間(大窪人衛、加茂杏子)がいることがわかり、自分たちは「宇宙人」だと名乗る。彼らの「仕事」は人が持つ「概念」の調査で、彼らと対面した人間たちは次々と「概念」を奪われていく…。
前川氏お得意のレイヤー構造は相変わらず見事で、舞台転換をまったく行わずにそこが、路上であったり、二組の夫婦の部屋であったり、病院内であったりと、さまざまに表情を変える。しかもその場でいくつかの物語が同時に、あるいは交錯しないがら進行していくという手法。
燐国との軍事緊張が高まるなかで、物語は次第に宇宙人(?)による「侵略」というSFチックな様相を帯びていくのだが、前川氏は最後に、それらをすべて吹っ飛ばす仕掛けを施した。
「宇宙人」の夫が妻(伊勢佳世)の一番大切なものを奪い、自身がそれを知ってしまったことで、本作を、せつない“愛”の物語にしてしまったのだ。
これには、やられた。
人間とは「概念」で生きる動物だという存在論的なテーマを突きつけ、平田オリザ氏が主導するロボット演劇に対する一つ回答を提示してみせたかのように思わせて、じつは、つかこうへい的な純愛人間ドラマへと物語を昇華させる…。
その手腕に見事にのせられてしまったのは、ワタシだけではないと思う。終演後の客席の拍手の大きさがそれを物語っている。
もちろんここで語られる「戦争」や「侵略者」、あるいは「概念」などは、さまざまな暗喩として捉えることもできる。とりわけ3.11を経て、未だに収束しない原発事故による放射能に晒されるワタシたちにとって、その妄想は果てしなく続く。
それにしてこの劇団の役者たちは、それぞれに味があり、芝居巧者が揃っている。荒唐無稽になりがちな物語世界に入っていけるのも、そうした力のある役者たちと作家・演出家とが、がっちりとタッグを組んでいるからなのだと思う。
◆イキウメ『散歩する侵略者』の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「スリリングな展開、巧みな状況設定、役者の語りで想像力を刺激」--YOMIURI ONLINE(祐成秀樹氏)
「現代演劇の最高峰の一つ」-- PLAYNOTE
「作り手は何を伝えたいかをより明確にすることが必要」--因幡屋ぶろぐ
「ひとつの小さな奇跡をかみした」--しのぶの演劇レビュー
「特異な独特の世界観にただただ感服」--Forgetting-BarⅡ
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【演劇】バナナ学園純情乙女組『バナナ学園★王子大大大大大作戦』 ― 2011/05/22

智恵と努力と情熱満載の怒濤の80分。
噂の「バナナ学園純情乙女組」公演に初参戦したが、これはもう諸手を挙げて全面支持するしかない。凄まじいエネルギー溢れる『バナナ学園★王子大大大大大作戦』を堪能した(5月22日・王子小劇場)。
この日は楽日の最終公演。
入場の際には「場内は汚れています。レインコートをお配りしています」と声がけがあり、既にコスプレを施した出演者たちがうろつく“汚し”の入った劇場内に入れば、「いろいろなものが飛び散ります。“精液”が飛び散るかもしれません」というアナウンス(笑)。
それだけでもうすでにそこには、祝祭感とまがい物感が溢れ、一体何が始まるのかという観客の期待を嫌がうえにも盛り上げる。
ステージは全4場。冒頭からフルスロットルで、レビュー形式の舞台が繰り広げられる。戦闘服、セーラー服、半裸、被りもの、女装、男装、和服、紙オムツ(!)…さまざまなコスプレに身を包んだ30名にも及ぶ若い男女たちが、ステージ狭しと歌い、舞い、踊る。
思想、ジェンダー、年齢…あらゆるものを蹴散らかすように、強烈なリズムにのって、エナジーを発散しながら疾走をやめない。
しかし、よく目を凝らしてみれば、それらの動きは緻密に計算されており、てんでバラバラの動きから一転して一糸乱れぬ場面にスムースに転換するなど、相当修練を積んでいるかようなの印象を受ける。
例えば、しばしば客席にのしかかかるように、ステージ中央にモッシュするが、そのスクラムはけっして崩れることなく、スムーズに集散を繰り返す。
しかも、2F屋も含めたステージ上ではさまざなアクションが同時に進行しするので、一瞬たりとも目が離せない。それどころか、役者たちがしばしば客席に乱入し、さまざまなモノや“液体”が飛び散るので、観客はまったく気が抜けない。
いや、じつにスリリングな体験。じつに、エキサイティングなエンターテイメント!
役者たちがコンパクトカメラで客席に向かって一斉にフラッシュを炊き、糸電話(!)をうまく取り入れたパーフォーマンスを魅せるなど、80分余りのステージに一体どれこだけのアイデアが詰まっているのだろうかと、感心することしきり。
終演後は(これもステージの一部なのだろう)、観客一人ひとりにお茶が配られ「任務遂行(観劇)」の「表彰状」が手渡される。観客に参加意識を持たせ、この“祝祭”を自分たちのものだけにしない演出で、見事に最後を締めた。
「毛皮族」のエンディングも祝祭感溢れるレビューが売りだが、「バナ学」のそれは、それはもはや祝祭そのもの。ヒトが持つあらゆる欲望と業を、すべて発散して魅せる極上の祭りだ。
ボブ・ディランがエレキギターを手にしたとき、その“詩”を知覚から体感へと解き放ったように、“物語”を超えたパワーがここにある。
もしポスト「静かな演劇」があるとすれば、この「バナナ学園」こそ、その対極を疾走する存在として評価すべきだろう。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


噂の「バナナ学園純情乙女組」公演に初参戦したが、これはもう諸手を挙げて全面支持するしかない。凄まじいエネルギー溢れる『バナナ学園★王子大大大大大作戦』を堪能した(5月22日・王子小劇場)。
この日は楽日の最終公演。
入場の際には「場内は汚れています。レインコートをお配りしています」と声がけがあり、既にコスプレを施した出演者たちがうろつく“汚し”の入った劇場内に入れば、「いろいろなものが飛び散ります。“精液”が飛び散るかもしれません」というアナウンス(笑)。
それだけでもうすでにそこには、祝祭感とまがい物感が溢れ、一体何が始まるのかという観客の期待を嫌がうえにも盛り上げる。
ステージは全4場。冒頭からフルスロットルで、レビュー形式の舞台が繰り広げられる。戦闘服、セーラー服、半裸、被りもの、女装、男装、和服、紙オムツ(!)…さまざまなコスプレに身を包んだ30名にも及ぶ若い男女たちが、ステージ狭しと歌い、舞い、踊る。
思想、ジェンダー、年齢…あらゆるものを蹴散らかすように、強烈なリズムにのって、エナジーを発散しながら疾走をやめない。
しかし、よく目を凝らしてみれば、それらの動きは緻密に計算されており、てんでバラバラの動きから一転して一糸乱れぬ場面にスムースに転換するなど、相当修練を積んでいるかようなの印象を受ける。
例えば、しばしば客席にのしかかかるように、ステージ中央にモッシュするが、そのスクラムはけっして崩れることなく、スムーズに集散を繰り返す。
しかも、2F屋も含めたステージ上ではさまざなアクションが同時に進行しするので、一瞬たりとも目が離せない。それどころか、役者たちがしばしば客席に乱入し、さまざまなモノや“液体”が飛び散るので、観客はまったく気が抜けない。
いや、じつにスリリングな体験。じつに、エキサイティングなエンターテイメント!
役者たちがコンパクトカメラで客席に向かって一斉にフラッシュを炊き、糸電話(!)をうまく取り入れたパーフォーマンスを魅せるなど、80分余りのステージに一体どれこだけのアイデアが詰まっているのだろうかと、感心することしきり。
終演後は(これもステージの一部なのだろう)、観客一人ひとりにお茶が配られ「任務遂行(観劇)」の「表彰状」が手渡される。観客に参加意識を持たせ、この“祝祭”を自分たちのものだけにしない演出で、見事に最後を締めた。
「毛皮族」のエンディングも祝祭感溢れるレビューが売りだが、「バナ学」のそれは、それはもはや祝祭そのもの。ヒトが持つあらゆる欲望と業を、すべて発散して魅せる極上の祭りだ。
ボブ・ディランがエレキギターを手にしたとき、その“詩”を知覚から体感へと解き放ったように、“物語”を超えたパワーがここにある。
もしポスト「静かな演劇」があるとすれば、この「バナナ学園」こそ、その対極を疾走する存在として評価すべきだろう。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【演劇】北京蝶々×中屋敷法仁『パラリンピックレコード』 ― 2011/04/09

さまざまなことが重なり1週間ぶりのブログ執筆。震災以降、なかなか調子が戻らない…。というなかで久々の鑑劇となった劇団「北京蝶々」が「柿食う客」の中屋敷法仁氏とタッグを組んだ『パラリンピックレコード』(4月9日・三軒茶屋シアタートラム)
初見の「北京蝶々」だが、資料によると2003年に早稲田劇研を母体に旗挙げし、電子マネーや介護ロボットなど日常に浸透しつつあるテクノロジーをモチーフに近未来の日常を描く舞台を展開しているらしいが、今回の公演もそうした延長線上にあるのだろう。
一方、今回の演出を担当した中屋敷法仁氏(柿食う客)は、「演劇の虚構性を重視し、『圧倒的なフィクション』の創作を続ける」(劇団HPより)とある。
なるほど、この二つの個性がマッチングするとこういう芝居になるのか…という展開をみせてくれた芝居だった。
着想は面白い。二度目のオリンピックを控えた近未来の東京が舞台。親子二代で都知事となったイシハラのもとに、特殊な義手や義足を身につけた障害者アスリートが結集する。日本選手の金メダルが難しくなったオリンピックよりも、彼らをパラリンピックで活躍させるというアイデアが採用されるが、それまで差別され続けてきたアスリートたちが突然テロリストと化し、イシハラ都知事を人質にする…。
早くから配布されていたチラシにもそのような内容が記されているが、震災後に改訂が行われたのだろう。「震災での復興にはオリンピックが必要だ」と叫ぶイシハラのセリフは、よりリアルに聞こえる。
東京都知事選にぶつけるタイミングもよいし、「二代目」という構想も実際にあの親子のなかにはあったかと思う。
さらに、先頃まで表現規制問題で揺れていた東京の未来が「言論統制下にある」というのも、特殊なギアによって障害者や高齢者が常人以上の身体能力を持つというも、けっして荒唐無稽な話ではなく、そうした意味でも“近未来感”溢れるエンターテイメントといえる。
しかしながら、ワタシにはその作劇(風)がどうも80年代にさんざん使い古された手法や構造にみえて、“新しさ”が感じられなかった。たしかに「虚構性の高い発話法/演技法を追求し、人間存在の本質をシニカルに描く」というのは“新しさ”なのかしれないが、その発語される単語や装飾語が新しいだけで、どうもかつての「第三エロチカ」や「演劇団」などの芝居とダブって仕方がないのだ。
そういう意味では、中屋敷氏が「その姿勢から『反・現代口語演劇』の旗手」とされるのもよく理解できた。気のせいか客席の年齢層も高かったように思える。
ワタシには、本作のようなテーマ一発のノリでつっ走る活劇よりも、平田オリザ氏の“ロボット演劇”のほうが、よほど近未来的で、刺激的に思えるのだが…。
◆『パラリンピックレコード』の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「グルーブ感とボディをしなやかに持ち合わせた舞台」--RClub Annex
「スタイリッシュなリズムが躍動する演出」--江森盛夫の演劇袋
↓応援クリックにご協力をお願いします。


初見の「北京蝶々」だが、資料によると2003年に早稲田劇研を母体に旗挙げし、電子マネーや介護ロボットなど日常に浸透しつつあるテクノロジーをモチーフに近未来の日常を描く舞台を展開しているらしいが、今回の公演もそうした延長線上にあるのだろう。
一方、今回の演出を担当した中屋敷法仁氏(柿食う客)は、「演劇の虚構性を重視し、『圧倒的なフィクション』の創作を続ける」(劇団HPより)とある。
なるほど、この二つの個性がマッチングするとこういう芝居になるのか…という展開をみせてくれた芝居だった。
着想は面白い。二度目のオリンピックを控えた近未来の東京が舞台。親子二代で都知事となったイシハラのもとに、特殊な義手や義足を身につけた障害者アスリートが結集する。日本選手の金メダルが難しくなったオリンピックよりも、彼らをパラリンピックで活躍させるというアイデアが採用されるが、それまで差別され続けてきたアスリートたちが突然テロリストと化し、イシハラ都知事を人質にする…。
早くから配布されていたチラシにもそのような内容が記されているが、震災後に改訂が行われたのだろう。「震災での復興にはオリンピックが必要だ」と叫ぶイシハラのセリフは、よりリアルに聞こえる。
東京都知事選にぶつけるタイミングもよいし、「二代目」という構想も実際にあの親子のなかにはあったかと思う。
さらに、先頃まで表現規制問題で揺れていた東京の未来が「言論統制下にある」というのも、特殊なギアによって障害者や高齢者が常人以上の身体能力を持つというも、けっして荒唐無稽な話ではなく、そうした意味でも“近未来感”溢れるエンターテイメントといえる。
しかしながら、ワタシにはその作劇(風)がどうも80年代にさんざん使い古された手法や構造にみえて、“新しさ”が感じられなかった。たしかに「虚構性の高い発話法/演技法を追求し、人間存在の本質をシニカルに描く」というのは“新しさ”なのかしれないが、その発語される単語や装飾語が新しいだけで、どうもかつての「第三エロチカ」や「演劇団」などの芝居とダブって仕方がないのだ。
そういう意味では、中屋敷氏が「その姿勢から『反・現代口語演劇』の旗手」とされるのもよく理解できた。気のせいか客席の年齢層も高かったように思える。
ワタシには、本作のようなテーマ一発のノリでつっ走る活劇よりも、平田オリザ氏の“ロボット演劇”のほうが、よほど近未来的で、刺激的に思えるのだが…。
◆『パラリンピックレコード』の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「グルーブ感とボディをしなやかに持ち合わせた舞台」--RClub Annex
「スタイリッシュなリズムが躍動する演出」--江森盛夫の演劇袋
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【パントマイム】湘南亀組「越境の身体」 ― 2011/02/28

パントマイム劇団・湘南亀組の30周年記念公演「越境の身体(からだ)」に足を運ぶ(2月26日・北とぴあ)
寡聞にしてこの劇団のことは本公演の案内で知ったのだが、「平塚養護学校寄宿舎パントマイム同好会」からスタートして、かれこれ30年に及ぶ活動歴をもつという。おそらく養護学校の先生を中心とした、素人マイム集団なのだろうと思って公演を観たのだが、その予想は大きく覆された。
まず、舞台に登場するパーフォーマーたちは、障害のある無しを問わないさまざまな人たちだ。そのさまざまな身体性と集団性を活かし、パントマイムの枠を超えた多様なパフォーマンスを魅せてくれた。
もう30年も前のことだが、在日韓国人で身体に障害に持つ金満里氏率いる「劇団態変」の公演で、カラフルな衣装をまとった金氏が細いを手足を“でんでん太鼓”のようにくねらせ舞台を転がる姿を観たときに、その身体は本当に“美しい”と思った。金満里は天才だと思った。
本公演で、そのシーンがまざまざと思い返された。
黒タイツに上半身裸体のパフォーマーたちが舞台に居並び、次第に身をくねらせ始める。足に障害をもつ男性は、座った状態から両腕だけでひょいとその身体を浮かせ“歩行”してみせる。
舞台に身を横たえたほとんど身体の自由がきかない男性を、健常(?)の男性パーフォーマーがゆっくりと持ち抱え、慈母のように慈しむ…。
その息をのむようなパーフォーマンスはまさに、本公演タイトルである「身体の越境」を視るかのように、幻想的で美しい…。
また、「瞽女」というパーフォーマンスでは、着物を着た二人の障害をもつ女性を“瞽女”さんたちが、とり囲む。それだけで、そこには“物語”が立ち上がる。
圧巻は「ひ」と題された男女二人による舞踏で、身をくねらせ異彩を放つ男性パフォーマーが、身体的にはより自由であるはずの(健常?)女性舞踏家を圧倒する。まさに身体が“越境”した瞬間をそこに観るかのように…。
冒頭のライティングに工夫を凝らした“影絵マイム”や名作映画の一番面をコミカルに再現した舞台など、さすがに30年のキャリアの中で培ってきた研究と演出で、観客を厭きさせない。
途中、朴保ライブと東京朝鮮中高級学校による朝鮮舞踊や民族楽器演奏も挟み込み、特大新聞紙を出演者たちが思い思いにぶち破るというカタルシス溢れるフィナーレで、2時間余の“ショー”の幕を閉じた。
すでに海外公演もいくつもこなしている同劇団だが、もっと多くの人に知られてもいい、本格的なノーマライゼーション・パフォーマンス集団だと思う。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


寡聞にしてこの劇団のことは本公演の案内で知ったのだが、「平塚養護学校寄宿舎パントマイム同好会」からスタートして、かれこれ30年に及ぶ活動歴をもつという。おそらく養護学校の先生を中心とした、素人マイム集団なのだろうと思って公演を観たのだが、その予想は大きく覆された。
まず、舞台に登場するパーフォーマーたちは、障害のある無しを問わないさまざまな人たちだ。そのさまざまな身体性と集団性を活かし、パントマイムの枠を超えた多様なパフォーマンスを魅せてくれた。
もう30年も前のことだが、在日韓国人で身体に障害に持つ金満里氏率いる「劇団態変」の公演で、カラフルな衣装をまとった金氏が細いを手足を“でんでん太鼓”のようにくねらせ舞台を転がる姿を観たときに、その身体は本当に“美しい”と思った。金満里は天才だと思った。
本公演で、そのシーンがまざまざと思い返された。
黒タイツに上半身裸体のパフォーマーたちが舞台に居並び、次第に身をくねらせ始める。足に障害をもつ男性は、座った状態から両腕だけでひょいとその身体を浮かせ“歩行”してみせる。
舞台に身を横たえたほとんど身体の自由がきかない男性を、健常(?)の男性パーフォーマーがゆっくりと持ち抱え、慈母のように慈しむ…。
その息をのむようなパーフォーマンスはまさに、本公演タイトルである「身体の越境」を視るかのように、幻想的で美しい…。
また、「瞽女」というパーフォーマンスでは、着物を着た二人の障害をもつ女性を“瞽女”さんたちが、とり囲む。それだけで、そこには“物語”が立ち上がる。
圧巻は「ひ」と題された男女二人による舞踏で、身をくねらせ異彩を放つ男性パフォーマーが、身体的にはより自由であるはずの(健常?)女性舞踏家を圧倒する。まさに身体が“越境”した瞬間をそこに観るかのように…。
冒頭のライティングに工夫を凝らした“影絵マイム”や名作映画の一番面をコミカルに再現した舞台など、さすがに30年のキャリアの中で培ってきた研究と演出で、観客を厭きさせない。
途中、朴保ライブと東京朝鮮中高級学校による朝鮮舞踊や民族楽器演奏も挟み込み、特大新聞紙を出演者たちが思い思いにぶち破るというカタルシス溢れるフィナーレで、2時間余の“ショー”の幕を閉じた。
すでに海外公演もいくつもこなしている同劇団だが、もっと多くの人に知られてもいい、本格的なノーマライゼーション・パフォーマンス集団だと思う。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【演劇】焼肉ドラゴン ― 2011/02/12

鳴りやまぬ拍手とスタンディングオベーション…。
2008年に初演され、その年の演劇賞を総なめにした『焼肉ドラゴン』の再演を観たが、やはりこれは歴史に残る名作だと確信した(2月12日・新国立劇場)
会場に入るともうそこは島次郎氏が手がけた秀逸な舞台セットによって、“昭和”の朝鮮人部落が出現していた。まるで舞台からホルモン焼きの臭いが漂ってくるかのような、濃厚な世界。ワタシたちは、すぐにその異空間に誘われる…。
じつはワタシは、テレビ放送でこの初演版を観ている。
したがって、“語り部”である一人息子・時生(トキオ)の運命も、ホルモン焼店とその家族の行く末も、既に知っている。
しかしストーリーもセリフも、ほぼ初演版のまま演じられる舞台に、初見でないことを悔やんだのは、10分にも満たなかったのではないか。
役者の姿を追いがちなテレビカメラの目線ではない、舞台全体から立ち上る“物語”に一気に引き込まれた…。
高度成長真っ只中の1970年前後を時代背景に、関西の朝鮮人部落でホルモン焼店「焼肉ドラゴン」を営む在日コリアン一家が、歴史と社会に翻弄されながらもたくましく生きる様を描く。
そこに詰め込まれるたのは、日韓の歴史はもとより、差別、教育、結婚、ジェンダーの問題や「在日」と韓国人の確執、影を落とす済州島四・三事件など、在日コリアンの苦難の歴史を紐解く一大パノラマのよう。
それらの在日コリアンが抱える象徴的な課題や問題を、ほぼすべてといっていいほど詰め込みながら、教条的にもならず、破綻することなく、ユーモアをたっぷりまぶしたエンターテイメントに仕上げた鄭義信(作・演出)の手腕は讃えて然るべきだろう。
日韓合同による役者陣のイキもぴったりで、ワタシたちもまるで「焼肉ドラゴン」の店内に居るかのように、臨場感溢れるその悲喜劇に巻き込まれていく…。
そんな役者陣のなかでも、店主夫婦を演じた韓国人俳優二人(申哲振・高秀喜)の存在感はバツグンで、とりわけ寡黙な店主を演じた申が自身の過去を静かに独白する場面では、一瞬にして観客すべてを惹きつける。
ふだんは本作のようなストレートな芝居はあまり観ないワタシだが、休憩を挟んで3時間余りという上演も、この小さな空間から放たれる壮大な歴史物語のスケールを考えると、必要な時の流れだったのかと思う。
桜散るなかリアカーをひくラストのシーンはまるで、美しい映画(映像)を観ているかのように息を呑む。その後に引き続く、在日コリアンのさまざまな“苦難の歴史”に向かって一家はそれぞれの道を歩み出すのだ…。
◆『焼肉ドラゴン』の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「必死で生きる普遍的な家族の物語」--しのぶの演劇レビュー
「『在日』を真正面から描いた渾身の力作だが…」--因幡屋ぶろぐ
「笑いに紛らせて大きな課題を突きつけた」--変様する港街から
「在日問題に留まらない、普遍性を感じさせる作品」--松井今朝子ホームページ
↓応援クリックにご協力をお願いします。


2008年に初演され、その年の演劇賞を総なめにした『焼肉ドラゴン』の再演を観たが、やはりこれは歴史に残る名作だと確信した(2月12日・新国立劇場)
会場に入るともうそこは島次郎氏が手がけた秀逸な舞台セットによって、“昭和”の朝鮮人部落が出現していた。まるで舞台からホルモン焼きの臭いが漂ってくるかのような、濃厚な世界。ワタシたちは、すぐにその異空間に誘われる…。
じつはワタシは、テレビ放送でこの初演版を観ている。
したがって、“語り部”である一人息子・時生(トキオ)の運命も、ホルモン焼店とその家族の行く末も、既に知っている。
しかしストーリーもセリフも、ほぼ初演版のまま演じられる舞台に、初見でないことを悔やんだのは、10分にも満たなかったのではないか。
役者の姿を追いがちなテレビカメラの目線ではない、舞台全体から立ち上る“物語”に一気に引き込まれた…。
高度成長真っ只中の1970年前後を時代背景に、関西の朝鮮人部落でホルモン焼店「焼肉ドラゴン」を営む在日コリアン一家が、歴史と社会に翻弄されながらもたくましく生きる様を描く。
そこに詰め込まれるたのは、日韓の歴史はもとより、差別、教育、結婚、ジェンダーの問題や「在日」と韓国人の確執、影を落とす済州島四・三事件など、在日コリアンの苦難の歴史を紐解く一大パノラマのよう。
それらの在日コリアンが抱える象徴的な課題や問題を、ほぼすべてといっていいほど詰め込みながら、教条的にもならず、破綻することなく、ユーモアをたっぷりまぶしたエンターテイメントに仕上げた鄭義信(作・演出)の手腕は讃えて然るべきだろう。
日韓合同による役者陣のイキもぴったりで、ワタシたちもまるで「焼肉ドラゴン」の店内に居るかのように、臨場感溢れるその悲喜劇に巻き込まれていく…。
そんな役者陣のなかでも、店主夫婦を演じた韓国人俳優二人(申哲振・高秀喜)の存在感はバツグンで、とりわけ寡黙な店主を演じた申が自身の過去を静かに独白する場面では、一瞬にして観客すべてを惹きつける。
ふだんは本作のようなストレートな芝居はあまり観ないワタシだが、休憩を挟んで3時間余りという上演も、この小さな空間から放たれる壮大な歴史物語のスケールを考えると、必要な時の流れだったのかと思う。
桜散るなかリアカーをひくラストのシーンはまるで、美しい映画(映像)を観ているかのように息を呑む。その後に引き続く、在日コリアンのさまざまな“苦難の歴史”に向かって一家はそれぞれの道を歩み出すのだ…。
◆『焼肉ドラゴン』の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「必死で生きる普遍的な家族の物語」--しのぶの演劇レビュー
「『在日』を真正面から描いた渾身の力作だが…」--因幡屋ぶろぐ
「笑いに紛らせて大きな課題を突きつけた」--変様する港街から
「在日問題に留まらない、普遍性を感じさせる作品」--松井今朝子ホームページ
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【演劇】ひょっとこ乱舞『ロクな死にかた』 ― 2011/02/06

広田淳一氏が主宰する劇団「ひょっとこ乱舞」の新作『ロクな死にかた』を観劇(2月6日・東京芸術劇場小ホール)。
今年で結成10周年を迎える同劇団の公演数は、本公演で24回を数えるというからちょうど年2回のペースで公演を行ってきたことになる。全作品の脚本・演出を担当してきた広田氏に、それだけ表現したい欲求があるのだろう。本作も、そうした氏の“思い”がたくさん詰まった作品となっている。
テーマは「死」と、その表裏を成す「生」だ。
冒頭から魅力的な滑りだしで、この物語は始まる。
元恋人の死を受け入れられずに引きこもり、精神的に不安定になった妹を思んばかって、姉は会社の同僚を連れてくる。
妹は元恋人が「生きている」と主張する。その根拠は、彼しか知り得ないようなエピソードが綴られたブログで、それは今も更新されているというのだ…。
そこから、“死んだ”はずの彼の生前が語られ、現・恋人や彼の友人たちとの会話ややりとりが描かれるなかで、意外とあっさりブログの“秘密”が明かされる。
そして、死後もネット上に漂うブログやツィッターを巡って、生と死の曖昧な境がテーマとして立ち上がってくるのだ…。
以下は学術的な裏付けがあっての話ではないが、アフリカやラテンアメリカの伝統的死生観では、「死」は肉体の死を意味するのものではなく、その人を知る人たちのその人にまつわる記憶がなくなったときに初めて「死」として認知される、と聞いたことがある。
やし酒飲みが“死者の国”を旅するキテレツな冒険譚であるエイモス・チュツオーラの小説『やし酒飲み』 などは、そうした死生観から生み出された作品だという。
などは、そうした死生観から生み出された作品だという。
そうした死生観がある以上、ネット社会的ならではの、新しい死生観が出現してもたしかに不自然ではないだろう。
それだけに、舞台で語られる「死んだ奴から『臨終なう。』『納骨なう。』なんてメールが届いたら、怖くね?」という会話も、不気味さをもってリアルに響く。
舞台上にはジェットコースターの曲線を思わせる柱組と、鉄板のようなテーブル(?)しかなく、簡素な舞台を効果的に生かした演出が施される。細く曲がったテーブル上に窮屈そうに寝そべり、平均台よろしく歩く様は、ワタシたち自信が曖昧な生と死の境界線を危なかしく生きる姿を写し出しているかのようだ。
1時間40分という上演時間はけっして長いものではないが、恋人同士の回想場面や“狂言回し”の「たっくん」の存在など、やや冗長だったり不要に感じられるシーンもあり、もう少し刈り込んでもいいような気がした。
また、電子音に乗せて踊るダンス/群舞など、スタイリッシュな演出が光る一方で、セリフ/発声がいかにも70~80年代小劇場的なセンスにとどまっているのはあえて“狙い”なのだろうか?
↓応援クリックにご協力をお願いします。


今年で結成10周年を迎える同劇団の公演数は、本公演で24回を数えるというからちょうど年2回のペースで公演を行ってきたことになる。全作品の脚本・演出を担当してきた広田氏に、それだけ表現したい欲求があるのだろう。本作も、そうした氏の“思い”がたくさん詰まった作品となっている。
テーマは「死」と、その表裏を成す「生」だ。
冒頭から魅力的な滑りだしで、この物語は始まる。
元恋人の死を受け入れられずに引きこもり、精神的に不安定になった妹を思んばかって、姉は会社の同僚を連れてくる。
妹は元恋人が「生きている」と主張する。その根拠は、彼しか知り得ないようなエピソードが綴られたブログで、それは今も更新されているというのだ…。
そこから、“死んだ”はずの彼の生前が語られ、現・恋人や彼の友人たちとの会話ややりとりが描かれるなかで、意外とあっさりブログの“秘密”が明かされる。
そして、死後もネット上に漂うブログやツィッターを巡って、生と死の曖昧な境がテーマとして立ち上がってくるのだ…。
以下は学術的な裏付けがあっての話ではないが、アフリカやラテンアメリカの伝統的死生観では、「死」は肉体の死を意味するのものではなく、その人を知る人たちのその人にまつわる記憶がなくなったときに初めて「死」として認知される、と聞いたことがある。
やし酒飲みが“死者の国”を旅するキテレツな冒険譚であるエイモス・チュツオーラの小説『やし酒飲み』
そうした死生観がある以上、ネット社会的ならではの、新しい死生観が出現してもたしかに不自然ではないだろう。
それだけに、舞台で語られる「死んだ奴から『臨終なう。』『納骨なう。』なんてメールが届いたら、怖くね?」という会話も、不気味さをもってリアルに響く。
舞台上にはジェットコースターの曲線を思わせる柱組と、鉄板のようなテーブル(?)しかなく、簡素な舞台を効果的に生かした演出が施される。細く曲がったテーブル上に窮屈そうに寝そべり、平均台よろしく歩く様は、ワタシたち自信が曖昧な生と死の境界線を危なかしく生きる姿を写し出しているかのようだ。
1時間40分という上演時間はけっして長いものではないが、恋人同士の回想場面や“狂言回し”の「たっくん」の存在など、やや冗長だったり不要に感じられるシーンもあり、もう少し刈り込んでもいいような気がした。
また、電子音に乗せて踊るダンス/群舞など、スタイリッシュな演出が光る一方で、セリフ/発声がいかにも70~80年代小劇場的なセンスにとどまっているのはあえて“狙い”なのだろうか?
↓応援クリックにご協力をお願いします。


最近のコメント