【映画】ロンゲスト・ヤード ― 2011/09/18

『ロンゲスト・ヤード』(1974年・監督:ロバート・アルドリッチ)
なぜか縁なく見過ごしていた37年前の作品だが、「スポーツ映画の名作」と謳われるに恥じない爽快な一作だ。
刑務所送りになったフットボールの元名プレーヤー(バート・レイノルズ)が、受刑者チームをつくり、仇ともいえる看守チームと相対するという、言ってみればたわいないストーリーだが、随所に名匠アルドリッチ監督の薬味が効いて厭きさせない。
冒頭で主人公ポールの自堕落な生活ぶりを簡潔に写し出し、続く逮捕に至るまではカーチェイスで楽しませ、刑務所内ではその微妙な人間関係をジョークやウィットで一気に見せてしまう。
一癖も二癖もある受刑者の中から、チームメンバーを選んでいく様は野武士集団を形成していく『七人の侍』からの影響も感じられ、後の『少林サッカー』にも連なる集団形成ドラマの妙がそこにある。
もちろんクライマックスは受刑者対看守の試合シーンで、ブライアン・デ・パルマばりのマルチ画面やサム・ペキンパーばりのスローモーションを駆使して、臨場感あふれる名場面をつくりあげている。
それにしても男臭い映画だ。単に女性キャストが少ないというだけなく刑務所長のエディ・アルバートや看守長のエド・ローターをはじめ、まるで西部劇か犯罪ドラマの如き布陣。
ボールをあれだけ虐待し続けた看守長が、試合後に刑務所長の行為に抗してみせた“スポーツマンシップ”なる振る舞いも、本作観賞後の清々しさに見事に貢献している。
そうした細部に怠りのないアルドリッチ監督の手腕は、後に“女性”を主人公に描いスポーツ映画『カリフォルニア・ドールズ』(1981年)でも十分に生かされている。
↓応援クリックにご協力をお願いします。


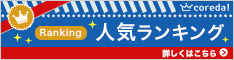

なぜか縁なく見過ごしていた37年前の作品だが、「スポーツ映画の名作」と謳われるに恥じない爽快な一作だ。
刑務所送りになったフットボールの元名プレーヤー(バート・レイノルズ)が、受刑者チームをつくり、仇ともいえる看守チームと相対するという、言ってみればたわいないストーリーだが、随所に名匠アルドリッチ監督の薬味が効いて厭きさせない。
冒頭で主人公ポールの自堕落な生活ぶりを簡潔に写し出し、続く逮捕に至るまではカーチェイスで楽しませ、刑務所内ではその微妙な人間関係をジョークやウィットで一気に見せてしまう。
一癖も二癖もある受刑者の中から、チームメンバーを選んでいく様は野武士集団を形成していく『七人の侍』からの影響も感じられ、後の『少林サッカー』にも連なる集団形成ドラマの妙がそこにある。
もちろんクライマックスは受刑者対看守の試合シーンで、ブライアン・デ・パルマばりのマルチ画面やサム・ペキンパーばりのスローモーションを駆使して、臨場感あふれる名場面をつくりあげている。
それにしても男臭い映画だ。単に女性キャストが少ないというだけなく刑務所長のエディ・アルバートや看守長のエド・ローターをはじめ、まるで西部劇か犯罪ドラマの如き布陣。
ボールをあれだけ虐待し続けた看守長が、試合後に刑務所長の行為に抗してみせた“スポーツマンシップ”なる振る舞いも、本作観賞後の清々しさに見事に貢献している。
そうした細部に怠りのないアルドリッチ監督の手腕は、後に“女性”を主人公に描いスポーツ映画『カリフォルニア・ドールズ』(1981年)でも十分に生かされている。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【本】師匠は針 弟子は糸 ― 2011/09/19
 | 師匠は針 弟子は糸 古今亭 志ん輔 講談社 2011-03-26 売り上げランキング : 44416 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
前者の代表作といえば、立川談志師匠による『現代落語論』
古今亭志ん輔師匠の本書も、やはり後者に分けられると思うが、その胆(ウリ)となっているのは書名にも象徴されるように、今は亡き志ん朝師匠との想い出に尽きる。なにしろ“名人”の誉れ高い三代目・志ん朝が逝く間際まで、側に仕えた愛弟子だ。志ん輔師匠自身の言葉から、昭和の大名人の芸やしぐさ、生活の息吹まで識りたいという落語ファンは少なくないだろう。
じつはワタシもそのつもりで読み始めたのだが…、じつは瞠目は別にあった。
2章145ページにわたって、小さな文字でビッシリと1年間の日常が記された日記。「志ん輔のケータイ日記」と題されたこの日記を、当初ワタシは読みとばすつもりでいた。
ところが読み始めて、これがめっぽう面白い。
何がオモシロイって、現代の芸人がどのような日常を送っているか、のぞき眼鏡で覗いているかの如く(今ならさしずめライブか)、その生活ぶりがつぶさに開示されているのだ。
例えば、師匠は高座の前にしばしばカラオケに立ち寄る。咽ならしをカラオケで行っているのだ。考えてみれば合理的かつ経済的で道理のいく話なのだが、なんだか噺家→咽慣らし→カラオケというイメージ(絵柄)に意外性があって妙に可笑しい。
東京だけでも500人近い噺家がいるというが、ほかの噺家も師匠と同じようにカラオケを利用しているならば、カラオケ業界は落語協会に感謝状を贈るべきだろう。
そんな具合に、この日記では(ご本人以外も含めて)現代落語家の生態がつぶさに明らかにされる。
そこには、健康に注意を払い、高座での観客に一喜一憂し、寄席と落語会場の行き来に右往左往し、ときに深酒をしては後悔をし、時間を工面して一人孤独に稽古に励み、弟子の態度に腹を立てては雷を落とし、弟子のことで内儀サンと夫婦喧嘩をし、娘の進学を心配する一人の芸人であり、生活人がいる…。
これはれっきとした日記文学ではないか。本書を100年後に読んだ人たちは、きっとこのビビットな生活感溢れる当時(現代)の芸人の生活ぶりに驚くことだろう。
ある時代を生きた、ある一人の芸人の貴重な「記録」だ。ならば志ん輔師匠以外の噺家たちの日記も、覗いてみたくなる…。志ん輔師匠と対極にあるような(芸風です!)白鳥師匠などは、いったいどんな生活を送っているのだろうか?…なんて、ああ妄想モード(笑)。
例えば、(高座を共にすることが多い)三人ぐらいの噺家の日記をそれぞれ載せて、それぞれの立場から観た高座や落語観の違いが浮き立てば、それもまた興味深し。どこかで企画してくれないかなぁ。
↓応援クリックにご協力をお願いします。
【本】市民社会政策論―3・11後の政府・NPO・ボランティアを考えるために― ― 2011/09/30
 | 市民社会政策論―3・11後の政府・NPO・ボランティアを考えるために― 田中 弥生 明石書店 2011-08-20 売り上げランキング : 38384 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
…との紹介文を付してみた本書であるが、そのNPOが東日本大震災では「以前のような活気をみせていない」というのが、どうやら著者の執筆動機であるようだ。
筆者は、「阪神・淡路大震災から16年。NPO法人数は4.2万団体になった。NPO法の目的と法人数を考えると、[被災]現地でボランティアを募集している団体が50というのはあまりに少ないのではないか」として、「被災地にボランティアを派遣する学生団体のメンバーは50以上のNPOに連絡をして学生ボランティアの受入れを頼んだが、殆どがボランティアを受入れていなかった」「NPOは市民との連携が弱いのではないか」という学生の証言を引いて「最も痛い指摘」と結論づけているが、被災当初の現地の混乱とその対応に奮迅するNPOやボランティアの活動を多少なりとも知るワタシには素直には腑に落ちず、首を傾けざるをえない。
それはさておき、現状のNPOに課題がないわけではなく、NPOを「市民性」「社会変革性」「組織安定性」という三つの「基本条件」から「エクセレントNPO」の理念を考察するという姿勢は、その上から目線的なネーミングはともかく、抗うものではない。
簡単にいえば、NPO活動に「評価」基準を持ち込もうというもので、本書はその研究書(論文)ということになる。したがって、耳を傾けるべき考察や論考であることは重々認めたうえで、おそらく被災現地で奮闘するNPO/ボランティアからは、「現場も知らないでケッ!」と一瞥すらされない…という光景も浮かんでしまう。
そもそも、NPO の「評価」というのもけっして新しいアプローチではなく、ワタシ自身も10年も前にすでにNPO業界で「評価」が話題にのぼっていたことを知っている。そうした意味では、10年経ってもこの「評価」がNPO間に浸透せず、本書のような提言がなされることこそが、NPOが抱え続ける「課題」なのかもしれない。
それにしても、ワタシもドラッガーの『非営利組織の経営』


最近のコメント