【アート】ヨコハマトリエンナーレ2011(その1) ― 2011/08/14
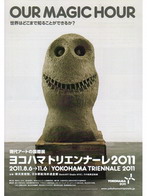
8月6日から開催されている「ヨコハマトリエンナーレ2011」に足を運ぶ(8月13日)。といっても、今回は主に三つある会場のうち横浜美術館での展示を眺めただけなので、まずは(その1)といったところ。
人波でゴッタ返す「みなとみらい駅」からほどなく歩いて会場に着くと、そこもまた奇妙な高揚感に包まれていた。その高揚感の原因は、若いカップルや子ども連れなど、おおよそ現代アート展ではあまりお目にかかれない入場者たちによるものであることに気づく。
まずそれをもって、会場入り口に掲げられた主催者・キューレーターらの「意図」を見事に満たしている。「みる、そだてる、つなげる」の三つのテーマを掲げ、「子どもや家族連れまで楽しめるアート展」というのが、本展のコンセプトなのだ。
さて、会場に入るとまず目に飛び込んでくるのが、衣服からほどいた糸をフィルム状に巻いて、それらをとぐろ状に並べた尹秀珍(イン・シウジェン)の「ワンセンテンス」。その回路をたどりながら間近に見ているだけではそれほど面白みのある作品には思えなかったのだが、その後改めて二階から見下してみると、その表情を一気に変えてきた。
これが現代アートの面白さであり、大型展示・作品の面目躍如たるところ。
透明なアクリル板による迷路の終点に電話が置かれ、そこにときたま作者本人から電話がかかってくるという趣向は、ジョン・レノンを一気に惹きつけたかつての「YES」を彷彿させて、いかにもオノ・ヨーコ氏らしいコミュニュケーション・アート。
そんなふうに、一つひとつの作品に言及している余裕も技量もないワタシだが、「天転劇場」を思わせる静寂のパフォーマンス作品「五つの点が人を殺す」(ジェイムス・リー・バイヤース)、色とりどりの幻想的なミニチュア都市「シティ」(マイク・ケリー)、工事現場のような巨大な足場の下で音が鳴り響く「オルガン」(マッシモ・バルトリーニ)といった海外アーティストの作品よりも、どうしても日本の若い作家たちの作品群に惹かれたてしまう。
早世した石田徹也の孤独を抱きしめたような作品には胸が締めつけられるような思いにかられるし、今回は多数の動植物のスケッチ(デッサン?)を出展してきた池田学氏の筆致には改めて舌をまくし、『ナウシカ』(原作本)に登場する一つ目の「神聖皇帝」を模したかのようなメタルチックな陶芸(!)作品を創出した金理有氏も注目の作家だ。
佐藤允氏のリアリズム画も池田氏とはまた違った迫真があり、立石大河亜氏のレトロフューチャーな木馬ロボ世界にもまた惹かれる。
そして、「湯本憲一コレクション」で展示された名もなき作家による妖怪映画ポスターと並んだパチンコ台のなんたるキュートでエレガントなデザイン!
新旧の商品看板やいん石まで展示し、「すべてマルセル・デュシャンへのオマージュ」とした杉本博司作品も含めて、“なんでもあり”の現代アートを堪能できるまさに「マジック・アワー」を満喫。
◆「ヨコハマトリエンナーレ2011」の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「様々なアプローチで横浜を舞台に繰り広げられるアートの祭典」--弐代目・青い日記帳
「真の強さにつながる複眼的な発想」--朝日新聞(大西若人氏)
「バラエティに富んだ作品群」--日毎に敵と懶惰に戦う
人波でゴッタ返す「みなとみらい駅」からほどなく歩いて会場に着くと、そこもまた奇妙な高揚感に包まれていた。その高揚感の原因は、若いカップルや子ども連れなど、おおよそ現代アート展ではあまりお目にかかれない入場者たちによるものであることに気づく。
まずそれをもって、会場入り口に掲げられた主催者・キューレーターらの「意図」を見事に満たしている。「みる、そだてる、つなげる」の三つのテーマを掲げ、「子どもや家族連れまで楽しめるアート展」というのが、本展のコンセプトなのだ。
さて、会場に入るとまず目に飛び込んでくるのが、衣服からほどいた糸をフィルム状に巻いて、それらをとぐろ状に並べた尹秀珍(イン・シウジェン)の「ワンセンテンス」。その回路をたどりながら間近に見ているだけではそれほど面白みのある作品には思えなかったのだが、その後改めて二階から見下してみると、その表情を一気に変えてきた。
これが現代アートの面白さであり、大型展示・作品の面目躍如たるところ。
透明なアクリル板による迷路の終点に電話が置かれ、そこにときたま作者本人から電話がかかってくるという趣向は、ジョン・レノンを一気に惹きつけたかつての「YES」を彷彿させて、いかにもオノ・ヨーコ氏らしいコミュニュケーション・アート。
そんなふうに、一つひとつの作品に言及している余裕も技量もないワタシだが、「天転劇場」を思わせる静寂のパフォーマンス作品「五つの点が人を殺す」(ジェイムス・リー・バイヤース)、色とりどりの幻想的なミニチュア都市「シティ」(マイク・ケリー)、工事現場のような巨大な足場の下で音が鳴り響く「オルガン」(マッシモ・バルトリーニ)といった海外アーティストの作品よりも、どうしても日本の若い作家たちの作品群に惹かれたてしまう。
早世した石田徹也の孤独を抱きしめたような作品には胸が締めつけられるような思いにかられるし、今回は多数の動植物のスケッチ(デッサン?)を出展してきた池田学氏の筆致には改めて舌をまくし、『ナウシカ』(原作本)に登場する一つ目の「神聖皇帝」を模したかのようなメタルチックな陶芸(!)作品を創出した金理有氏も注目の作家だ。
佐藤允氏のリアリズム画も池田氏とはまた違った迫真があり、立石大河亜氏のレトロフューチャーな木馬ロボ世界にもまた惹かれる。
そして、「湯本憲一コレクション」で展示された名もなき作家による妖怪映画ポスターと並んだパチンコ台のなんたるキュートでエレガントなデザイン!
新旧の商品看板やいん石まで展示し、「すべてマルセル・デュシャンへのオマージュ」とした杉本博司作品も含めて、“なんでもあり”の現代アートを堪能できるまさに「マジック・アワー」を満喫。
◆「ヨコハマトリエンナーレ2011」の参考レビュー一覧(*タイトル文責は森口)
「様々なアプローチで横浜を舞台に繰り広げられるアートの祭典」--弐代目・青い日記帳
「真の強さにつながる複眼的な発想」--朝日新聞(大西若人氏)
「バラエティに富んだ作品群」--日毎に敵と懶惰に戦う


最近のコメント